失業保険とは? 申請に必要なものや受給までの流れ、注意点を解説

※この記事は6分30秒で読めます。
「失業保険ってどんなもの?」
「失業保険ってどんな人がもらえるの?」
など、失業保険に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
失業保険は、離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、失業期間に一定の条件を満たしている失業者が受給できる手当です。
今回は、失業保険をもらえる人の条件、申請方法や給付までの流れ、注意点などを解説します。この記事を読めば失業保険への理解が深まり、自分が受給できるのかどうかの判断やその後の手続きがスムーズにできるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.失業保険とは?
失業保険とは、失業してしまった人が生活の心配をせずに新しい仕事を探し、一日でも早く再就職するための手当が支給される制度です。
労働者を雇用する企業は、会社の規模や種類や労働者の数に関係なく、失業保険を支給するための「雇用保険」加入することになります。
会社に勤める労働者は、一定の条件を満たしていれば雇用保険に自動的に加入することになります。なお、保険料は給与額に応じて変わります。
1-1.雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は以下の2つです。
(1)1日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
雇用契約が31日以内の有期契約で、雇用契約書に期間満了で雇い止めの明記がない限り、すべての労働者が当てはまります。
また、契約時には31日未満の短期雇用の予定でも、その後31日以上の雇用が見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
雇用契約時は短時間の労働であっても、徐々にシフトが増えるなどして労働時間が増え、恒常的に1週間の労働時間が20時間を超える状態になった場合は、その時点で雇用保険適用対象になります。
-
(※)参照:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
1-2.失業給付の給付日数、支給額、受給期間
雇用保険によって適用される失業時の手当てを「失業給付」と呼びます。その給付日数や支給額は、離職前に在籍していた職場の勤続年数や給与額によって変わってきます。
給付日数は以下のとおりです。
○一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合離職)
| 離職した日の満年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 65歳未満共通 | 90日 | 120日 | 150日 | ||
○倒産・解雇などにより再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた場合
| 離職した日の満年齢 |
被保険者であった期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
なお、就職困難者については、特例として定められた給付日数があります。
このように、失業給付の給付日数は一般の離職者で3ヵ月~5ヵ月、会社都合の離職者で勤続年数が長い人でも1年未満の期間であることがわかります。給付期間を超えると失業給付は受け取れないため、計画的に転職活動を進めていく必要があります。
失業保険の支給額は、離職前の給与をもとに計算します。最初に1日あたりの給与「賃金日額」を求めます。賃金日額を求める計算式は以下のとおりです。
賃金日額=離職前6ヵ月に支払われた給与の合計額÷180日
この計算で求めた賃金日額と、厚生労働省が定めた賃金日額の上限と下限を比べます。求めた額が上限を上回る場合には上限額を、下限を下回る場合には下限額を賃金日額として採用します。
○賃金日額の上限と下限(厚生労働省)
| 離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 13,670円 | 2,657円 |
| 30~44歳 | 15,190円 | |
| 45~59歳 | 16,710円 | |
| 60~64歳 | 15,950円 |
賃金日額が求められたら、それに所定の給付率をかけた「基本手当日額」を求めます。
○基本手当日額給付率
| 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|
| 2,657円以上 | 80% |
| 5,030円以上、12,380円未満 | 80%~50% |
| 12,380円以上 | 50% |
基本手当日額=賃金日額×50%~80%(所定の給付率)
さらに、この基本手当日額と厚生労働省が定める基本手当日額の上限と下限を比べます。求めた額が上限を上回る場合には上限額を、下限を下回る場合には下限額を採用します。
○基本手当日額の上限と下限
| 離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 6,835円 | 2,125円 |
| 30~44歳 | 7,595円 | |
| 45~59歳 | 8,355円 | |
| 60~64歳 | 7,177円 |
こうして算出した基本手当日額を最初に説明した給付日数にかけることで、失業手当の支給総額を出すことができます。
支給総額=基本手当日額×給付日数
このように、支給額はいくつもの段階を踏んで算出するため、個々人の状況により額が変わってくるのです。
1-3.パートやアルバイトでも加入対象になる
パートやアルバイトであっても、雇用保険の加入条件である「週20時間以上の所定労働時間があり、雇用期間に定めのない人や31日以上の雇用期間が見込める者」は雇用保険に加入することになります。
万が一、未加入の場合は職場に相談してみてください。加入を断られた場合は所轄のハローワークに相談しましょう。労働時間や労働契約内容を調べたうえで、加入条件を満たしていれば必ず加入できるようになります。
ただし、学生の場合は雇用保険の認める労働者に該当しないため、労働条件を満たしていても雇用保険には加入できないため注意が必要です。
2.失業保険を受給するための条件
雇用保険に加入していた失業者が受給できる失業保険。しかし、無条件に受け取れるわけではありません。次に失業保険を受給するための条件をご説明します。
2-1.働く意思があっても失業状態である
ただ離職し仕事がないだけでは、雇用保険の定める失業の状態とは認められません。失業保険を受給できる失業とは、以下のすべての条件を満たす状態を指します。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業についていないこと。
つまり、離職をしても次の仕事を探していない人や、妊娠出産や病気・けがなどですぐに就職できる状況にない人、家事や学業に専念する人などは受給の対象になりません。
-
(※)参照:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
2-2.保険加入期間が規定を満たしているか
雇用保険に加入したばかりですぐに離職した場合、失業保険の受給はできません。
離職前の職場での保険加入期間が「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヵ月以上ある」という条件を満たしている必要があるためです。
この月数は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある(または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)月をひと月としてカウントします。
2-3.失業保険は工場勤務でも受け取れる?
失業保険の受給に職種の制限はありません。そのため、工場勤務の人でも条件を満たしていれば必ず受給することができます。
また、期間の定めがある期間工も、働いた期間が保険加入期間の規定を満たしていれば問題なく給付を受けることができます。
3.失業保険の受給手続きに必要なもの
失業保険受給の条件を満たし実際に受給したい場合は、まずは受給手続きに必要なものを揃えましょう。
3-1.雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入手続きをした際にハローワークから発行され、職場が労働者に渡すものです。労働者番号や職場の名前が確認できます。
万が一、会社から受け取っていなかったり、紛失したりしている場合には、その旨を窓口で相談しましょう。
3-2.離職票
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、会社がハローワークに対して労働者の離職の手続きをし終わったあとにハローワークから交付されるものです。
会社は離職票が交付されると「離職票-1」と「離職票-2」を離職した労働者に渡します。失業保険の受給手続きはこの離職票がないと始まらないため、基本的に離職票の交付を待つことになります。
あまりにも交付が遅い場合は会社の手続きがおこなわれていない可能性もあるので、管轄のハローワークに確認しましょう。
また、事業主が行方不明などの場合においても、ハローワークに相談すれば手続きを進めることができます。
3-3.本人確認書類
本人確認書類とは、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなどです。
これらがない場合には、公的医療保険被保険者証、住民票、年金手帳、児童扶養手当証書などのなかから2点を提示します。
3-4.証明写真
失業保険受給手続きが終わると「雇用保険受給資格者証」が発行されますが、この書類に添付する証明写真が必要です。
3cm×2.5cm、3ヵ月以内の撮影で、正面上三分身、カラーの写真を2枚用意しましょう。
3-5.印鑑
受給に必要な書類に押印するため準備します。押印が不要な書類も増えていますが、訂正などの際には訂正印として必要になることもあるため、忘れずに用意しましょう。シャチハタは使えないため注意が必要です。
3-6.振込口座が確認できるもの
受給する失業給付の振込口座を確認するものです。本人名義の預金通帳やキャッシュカードで、銀行名や口座番号、支店名がわかるようにしていきます。
4.失業給付受給の手続きと流れ
必要なものがそろったら、失業給付受給の手続きに行きましょう。手続きの方法と受給までの流れを解説します。
4-1.ハローワークで求職の申し込みをする
手続きはすべてハローワークにておこないます。
最初に渡される「受付票」に氏名や住所、経歴や職種希望などを書いて求職の申し込みをすることがスタート地点です。用意した書類もこのときに提出します。
ここで失業状態であると認められると、受給資格が決定し「受給資格者のしおり」が交付されます。
4-2.待期期間
手続き後、7日間の待期期間があります。この間にハローワークは申請者が本当に失業状態にあるのか、失業給付を支給して良いのかを判断します。
この期間中にアルバイトをしたり再就職先が決まったりした場合には、失業保険の受給対象から外れてしまいます。
4-3.雇用保険受給説明会に参加
待期期間の終了後に「雇用保険受給説明会」に参加します。約2時間の説明会で、失業手当受給中の手続きや失業認定申告書の書き方などの説明を受けます。
この説明会で「雇用保険受給資格者証」が交付されることが多いようです。この資格者証はこの先の手続きで常に必要になるため、大切に保管しましょう。
4-4.失業認定
受給資格が決定すると、約3週間後に1回目の「失業認定日」が設けられます。失業認定日はハローワークが指定します。
失業認定を受けるには、仕事の有無や求職活動の状態、健康状態などを失業認定申告書に記載して提出します。この際、必ず受給資格書をもって本人が手続きをしなければなりません。
失業認定日は4週間ごとに設定されます。つまり、4週間ごとにハローワークに対して求職活動の報告をおこなう必要があるということです。
自己都合退職の場合は、1回目の失業認定のあとに「給付制限期間」があります。制限期間中は特に報告はなく、制限期間が明けるときに2回目の失業認定日が設定されます。
会社都合退職の場合は給付制限期間がないため、1回目の失業認定日から4週間ごとに失業認定をしていくことになります。なお、認定日の間の4週間のうちに求人の応募や職業相談など、求職活動実績が原則2回以上必要です。
4-5.給付制限期間
正当な理由のない自己都合退職の場合、待機期間満了の翌日から2ヵ月間(※)は「給付制限期間」として失業手当の給付はありません。
失業保険は原則として、会社の倒産など本人の意思に反して仕事がなくなってしまった人の生活を保障し再就職を援助するための制度です。そのため、自分の意思による離職の場合はその原則から外れてしまうことになります。
しかし、自己都合の離職であっても、一定の期間再就職が困難であれば、生活の保障が必要な状態と考えられます。そのため、自己都合退職の場合には離職後の2ヵ月間に給付制限期間が設けられているのです。
この給付制限期間中に再就職が決まった場合には、失業手当は受給できません。アルバイトなどで収入を得ることは可能ですが、その旨をハローワークに申告します。
アルバイトであってもその働き方が事実上の再就職だとみなされた場合、失業給付の受給ができなくなる場合もあるため、事前にハローワークに確認しておきましょう。
-
(※)参照:「給付制限期間」が2か月に短縮されます|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
4-6.受給開始
会社都合退職の場合は1回目の失業認定日から、正当な理由のない自己都合退職の方は2回目の失業認定日から、おおよそ一週間程度で失業手当が振り込まれます。
失業給付の対象となる始まりの日は、会社都合退職の場合が7日間の待期期間が明けた日になります。
また、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間と2ヶ月間の待機期間が明けたあとに1回目の失業手当が振り込まれることになります。
5.失業保険の受給中にアルバイトはできる?
求職の申し込み前や受給中でも、基本的にアルバイトはできます。しかし、その際は必ずハローワークに報告の義務があります。また、一定の条件を超えてしまうと失業手当受給不可になってしまうため注意が必要です。
5-1.注意したい受給不可になる例
待機期間中の7日間にアルバイトをすると、失業手当が受給できなくなってしまいます。
また、1日4時間以上のアルバイトをしている間は失業給付の支給がなく、アルバイトのない状態になるとまた支給が始まるという仕組みです。この後ろ倒し状態が受給期間の1年間を過ぎてしまうと、受給日数が残っていたとしても残りの分を受給できなくなるので注意が必要です。
週40時間以上働くと事実上の再就職とみなされ、受給資格はなくなります。また、1日の受給額の80%以上を稼いでしまうとその場合も受給が停止となります。
1日4時間以内で受給額80%を超えない稼ぎのアルバイトであれば受給期間中であっても可能ですが、働いた収入のぶん給付が減額になることもあるため、事前にハローワークに確認しましょう。
5-2.受給中におすすめの仕事
受給不可にならないように、期間限定や単発で働けるお仕事もあります。
5-2-1.期間限定で働ける工場の仕事
受給中は長期アルバイトより期間限定アルバイトが断然おすすめです。
アルバイト中は失業手当の受給がありませんが、期間が終わればまた手当の受給を受けることができるので、無期限のアルバイトに比べ受給期間を過ぎるという心配も少なくなります。
工場勤務なら、繰り返し作業が多いためすぐに仕事を覚えて働きやすくおすすめです。繁忙期のみの期間限定アルバイトもたくさんあるため、自分に合った仕事を探してみましょう。
5-3.単発のアルバイト
単発(1日や数時間のみ)で働ける仕事もおすすめです。
試験監督やイベントスタッフなどの仕事があります。その日その日で入れるので収入の調整もしやすく、働きやすいお仕事です。
期間限定でも単発でも、受給資格がなくなったり受給額が減額になったりしないように注意しましょう。
待期期間7日間は働いてはいけない、1日4時間以上週20時間未満で働く、働いていることをハローワークに報告するなどのルールを守って働きましょう。
6.まとめ
今回は失業保険について、申請に必要なものや需給の条件、受給までの流れなどをご紹介しました。
離職・転職の機会は誰にでもあることです。そのときに自分の生活をどうするのか、なるべく早く転職先を見つけて仕事をするのか、失業給付を最大限受け取りながらじっくり再就職を探すのか、その選択は人それぞれです。
しかし、確かな知識がないと、もらえるものももらえなくなってしまうかもしれません。失業手当を受給したい人は今回の記事を参考に手続きをし、安心して新しい仕事を探せるようにしましょう。
JOBPALではさまざまな業種の求人を掲載しています。ハローワークに掲載していない求人もあるので、転職活動の参考にしてください。
関連記事
人気ランキング
-
2024年01月30日
 正社員の給料・お金
正社員の給料・お金 手取り20万円の年収は?家賃や生活費の目安、年収アップを狙える仕事
-
2024年01月10日
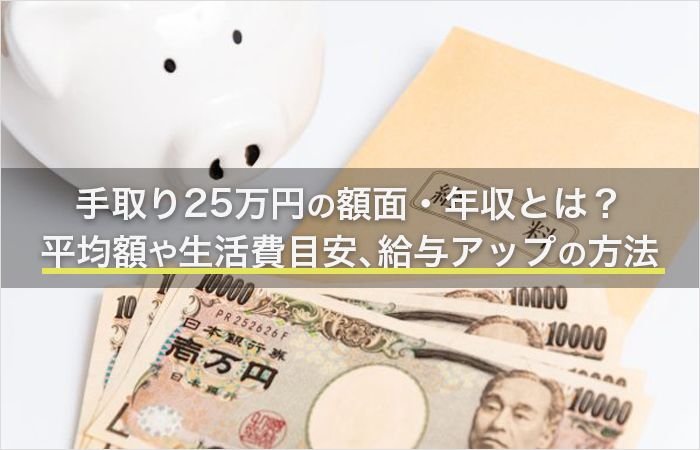 正社員の給料・お金
正社員の給料・お金 手取り25万円の額面・年収とは?生活レベルや生活費目安、給与アップの方法
-
2024年01月26日
 正社員の給料・お金
正社員の給料・お金 手取り30万の年収はいくら?生活レベルや給与をアップさせる方法、額面・年収計算の方法を解説
-
2022年11月28日
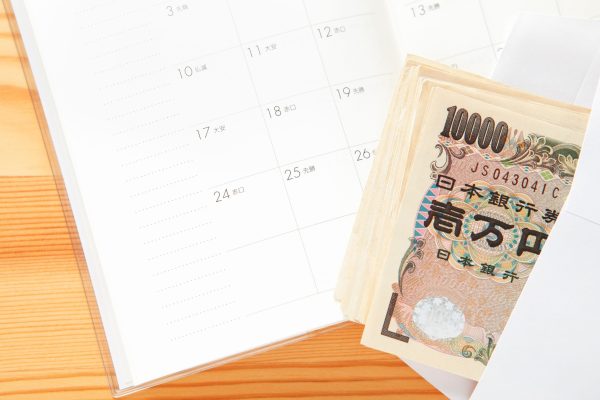 正社員の給料・お金
正社員の給料・お金 手取り15万は安い?給与をアップさせる方法や生活費の目安、額面・年収の計算方法も解説
-
2022年11月28日
 正社員の給料・お金
正社員の給料・お金 失業保険とは? 申請に必要なものや受給までの流れ、注意点を解説
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す

























