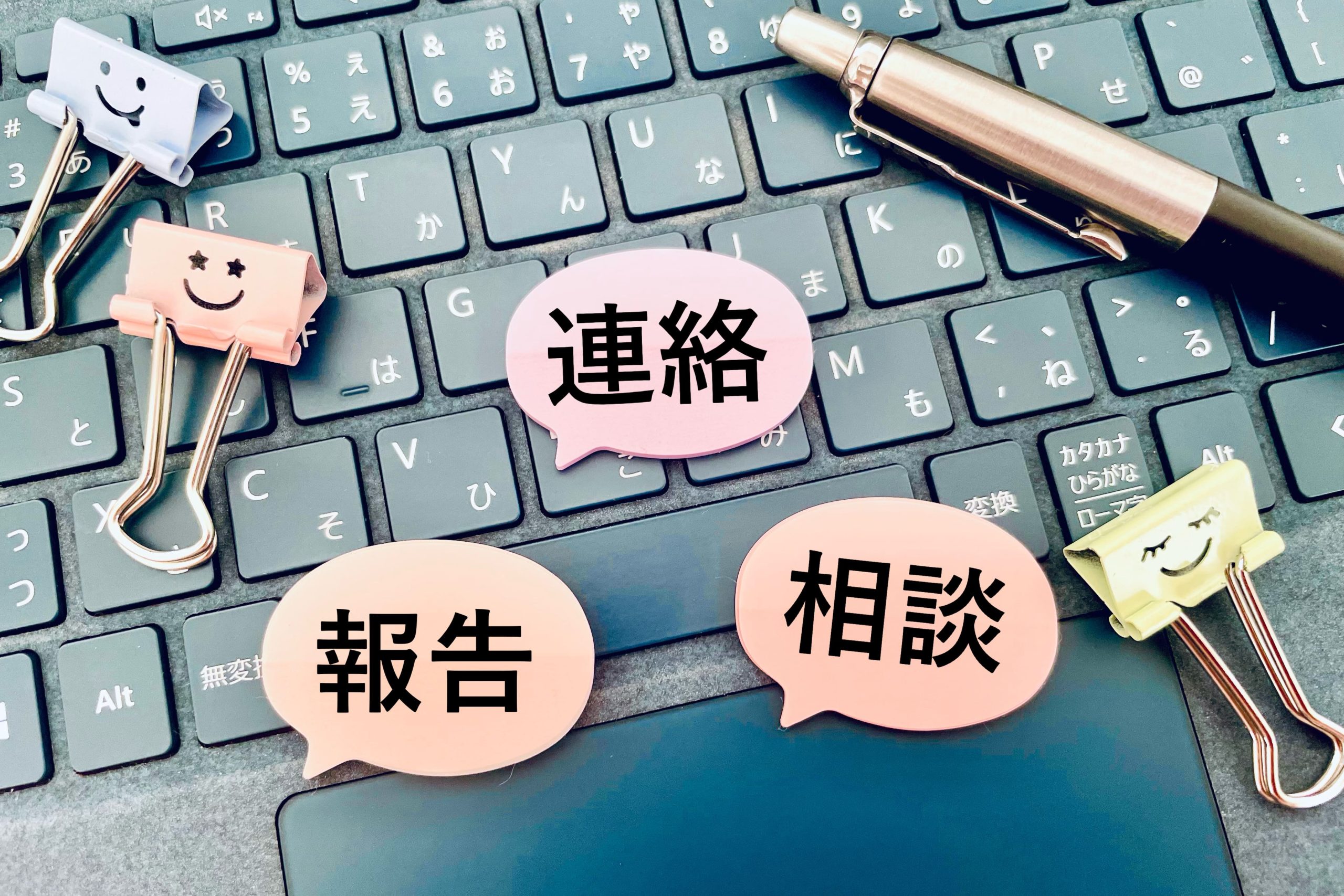PDCAサイクルとは?意味やメリット、工場・製造業の例を紹介

※この記事は6分30秒で読めます。
「PDCAってどういう意味?」
「PDCAを回すメリットを知りたい」
など、PDCAに関して疑問を持っている方もいるでしょう。
PDCAは業務改善のための基本的なフレームワークであり、何度もサイクルを回すことで業務の質を上げられます。
今回は、PDCAの意味や各プロセスの役割、効果的にPDCAサイクルを回すコツなどを解説します。この記事を読めば、PDCAのことがよくわかり、工場や製造業務においても事例を載せておりますので、業務改善に役立てられるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.PDCAとは?
PDCAは、Plan(プラン・計画)、Do(ドゥ・実行)、Check(チェック・評価)、Action(アクション・改善)の頭文字をとったフレームワークです。PDCAのサイクルを回すことで連続的なフィードバックが可能となり、業務効率の改善が期待できます。
PDCAは、アメリカの統計学者ウィリアム・エドワーズ・デミング博士、ウォルター・シューハート博士によって提唱されたものです。Actionが終了したら最初のPlanに戻って循環させることから「PDCAサイクル」とも呼ばれます。
2.PDCA各プロセスごとの役割
続いて、PDCAを構成するPlan、Do、Check、Actionの各プロセスの役割や、プロセスを進めるうえで意識すべき事柄についてご紹介します。
2-1.Plan(計画)
Planは目標を設定するプロセスです、単純に目標を設定するだけでなく、目標を達成するために求められるアクションプランも作成します。
アクションプランを作成する際は、以下の5W2Hを意識して作ることになります。
- 誰が(Who)
- いつ(When)
- どこで(Where)
- 何を(What)
- なぜ(Why)
- どのように(How)
- いくらで(How much)
5W2HはPDCAのスタート地点となるものです。目標数値を具体的に設定するなど、誰が見てもわかりやすい具体的なプランにすることが重要です。
その際に用いる目標は、過去の実績をもとに数値化(定量化)します。この際に現実的でない目標設定をしてしまうと、無理な計画を策定してしまい、Do以降のプロセスが破綻する恐れがあります。
2-2.Do(実行)
Doのサイクルでは、Planで立案した目標とアクションプランをもとに実務をおこないます。Planで練った計画を日々のタスクに落としこみ、プロセスや結果を随時記録していきます。
また、計画を実行して終わるのではなく、次のCheckにつながるように、
- 実行結果が有効なものだったのか
- 別の方法が良かったのではないか
という検証をすることも求められます。
実行で問題が生じた際は正確に記録し、計画と現実のギャップを把握することで、次のCheckがより効果を発揮します。
2-3.Check(評価)
Checkでは、Planで練り上げDoで実行した目標が達成できたかを振り返ります。目標数値が達成できたかを確認するのはもちろん、計画の妥当性や具体的に得られた成果・課題など、分析内容は多岐にわたります。
計画的に進まなかった、あるいは目標の数値に届かなかった場合は、その原因の分析をすることもCheckの重要な役割です。
また、計画どおりに遂行できた場合もそれで終わりにするのではなく、成功した要因の分析をおこないます。
2-4.Action(改善)
Actionは、Checkで明らかになった課題について改善点を考えるサイクルです。良かった点は成功要因を分析して次の計画でも同様に成功できるように、悪かった部分は改善案を検討して次の計画で改善できるようにします。改善策が複数出てきた場合は、優先順位をつけることも必要でしょう。
また、改善を考えると同時に、このまま計画を進めれば良いのか、計画を続けるなかで改善できるところはないか、計画を中止したほうが良いか、といったプロジェクトの方向性についても議論します。
3.PDCAサイクルを回すメリット
PDCAは1度やって終わりではなく、Action(改善)のサイクルで検証した改善案をもとに新しいPlan(計画)を練る必要があります。何度もPDCAを繰り返すことを俗に「PDCAを回す」と表現します。
PDCAを回すことによって得られるメリットには、以下の4つが挙げられます。
3-1.個人やチームの目標が明確になる
PDCAでは最初のPlanで定量的な数値目標を決めてからサイクルを回していくため、チームや個人が達成すべき目標が明確になります。
目標の数値から逆算して毎日の仕事の道筋を立てたり、軌道修正をしたりといったことが可能になるため、目標数値に向かってブレずに業務を遂行できます。
3-2.自分のタスク・やるべきことがわかる
目標を達成するための計画を最初に立て、計画通りに動いていくため、今自分が何をやるべきかがわかりやすくなります。また、 今自分がどのくらい目標達成に近づいているかも具体的な数値で明らかになります。
何をやれば良いかが明確になることで目の前の作業に集中でき、結果として生産性の向上や残業時間の削減も期待できるでしょう。
3-3.自分の課題や弱点が見つかる
PDCAでは、最初に計画を立て、それを達成していくために日々の業務を遂行していきます。ただ、途中で失敗したり、精いっぱいやったのにうまく成果がでなかったりすることはよくあります。
PDCAでは、ただ単に「うまくいった」「失敗した」と結果に一喜一憂するのではなく、成功や失敗から自分の弱点を明確にし、課題を見つけることが重要です。
成功や失敗の要因を分析して次に生かすことで、自分の課題や弱点を見つける能力や、その弱点や課題を改善するためにどうすべきかを考える能力が身につくでしょう。
課題や弱点が明確になれば、あとは改善に向かって努力する作業に集中できます。
3-4.一度きりではなく継続的にサイクルを回せる
PDCAは一度きりで終わりではありません。Checkで見つけた問題点・課題に対してActionで改善案を作成し、それを踏まえてまたPlanに戻って改善策を計画に落とし込み、再度Actionを起こすプロセスを繰り返します。
中長期的にサイクルを回して改善点をどんどん洗い出すことで、業務の質はどんどん高くなり、今までより高い目標を達成できる能力が身についていきます。
4.PDCAサイクルを回すデメリット
PDCAは業務改善をするうえでは欠かすことができない考え方ですが、一方でデメリットとなりえる部分もあります。業務でPDCAを回す際には、以下のようなデメリットがあることを知っておきましょう。
4-1.PDCAサイクルを回すことが目標になりがち
PDCAの一番のデメリットとして、PDCAを回すことが目標になってしまいがちであることが挙げられます。
PDCAを回すことだけに意識が集中していると、肝心の業務改善のプロセスが雑になり、PDCAを回す意味がなくなってしまいます。
PDCAはそれ自体が目標ではありません。目標をしっかり立てて、業務を改善していくためのものです。業務に携わる全員がPDCAの本質を理解して業務に臨むことで、はじめて効果が期待できるようになります。
4-2.改善に至るまでに一定の時間がかかる
PDCAを使った改善は、結果が出るまでに一定の時間がかかります。
PDCAの4つのプロセスはすべて踏む必要があり、A(Action)の改善に至るまでに一定の時間が必要になります。
途中で新たな課題が見つかったとしても、サイクルを止めずに最後までやり抜き、Actionのサイクルではじめて改善提案をする流れとなります。
また、一度目のサイクルでは改善点を絞り出しきれず、何度もPDCAを回してやっと課題にたどり着くケースもあるでしょう。そのため、業務改善について迅速な意思決定をしたいときにPDCAを採用すると、スピーディに判断できない可能性があります。
5.PDCA各段階ごとの注意点
PDCAの4つのサイクルでは、それぞれに進め方の注意点があります。途中で挫折してしまわないよう、これからご紹介するサイクルごとの注意点を意識してPDCAを回していきましょう。
5-1.Plan(計画)の注意点
Planでよくある失敗は、計画段階で設定する目標数値が現実的な範囲を大きく超えてしまっていることです。
理想だけで非現実的な目標を立ててしまうと、個人に設定される業務分担も非現実的なものになり、達成するためのアクションプランが見えてこなくなります。
また、早い段階で目標達成が不可能なことがわかると、Actionまで回すまでもなくサイクルが破綻(はたん)したり、社員のモチベーションが低下したりする可能性があります。
計画を立てることは重要なサイクルですが、そればかりに時間を使ってしまうのは良くありません。PDCAのサイクルに必要な時間から、Planに使える時間を逆算して計画を決めましょう。
5-2.Do(実行)の注意点
Doの段階では、Planで立てた計画を100%実行できるように行動することが重要です。
- 最終的な目標達成を考えずにがむしゃらに頑張る
- 優先順位を考えずに簡単なところから始める
- 言われたことだけやる
といった進め方をすると、改善点が見えず、効果的なPDCAにはなりません。
5-3.Check(評価)の注意点
Checkのサイクルでは、評価の内容や基準があいまいになることは絶対に避けたいところです。
評価基準があいまいで「全体に良い感じだった」という抽象的な評価では、具体的な課題や解決策が見えてきません。Planの段階で誰がみても明確かつ定量的な目標を作成し、誰が見てもわかりやすい形で評価をすることが重要です。
検証作業をおこなうときも、具体的な数値指標を基準にしておこないます。
5-4.Action(改善)の注意点
Actionのサイクルでは、最初のPlanで立てた定量的な目標に対して、なぜ成果が出たのか、なぜ成果が出なかったのかを具体的かつ論理的に分析し、改善点を洗い出すことが大切です。
数値を使わずに適当な振り返りをしてしまうと、次のPlan作成につながる明確な改善策が出てこない可能性があります。
また、改善案を作成する際、チーム内だけで検証すると甘い改善案ができあがる可能性もあります。上司や顧客、別のチームなど、外部の視点から改善案を検証してもらうことで、次のPDCAを回す際のさらなる改善案が見えてくるでしょう。
6.効果的にPDCAサイクルを回すコツ
初めてPDCAを回す場合、どうやって進めて良いのかわからずに失敗してしまうケースもあるかもしれません。効果的にPDCAを回したい場合は、以下のコツやポイントを守って取り組みましょう。
6-1.目標は数値で定量的に立てる
PDCAのなかでも重要となるPlanのサイクルでは、数値を用いて明確に目標設定をすることが重要です。
- 人時生産性を○円アップする
- 毎日の生産数を○個アップする
- 売り上げを○%上げる
このように、定量的で誰でもわかる目標を設定することで、そのあとにやるべき行動を逆算で考えられるようになります。単に売上をアップさせるといったあいまいな目標では、具体的な計画や実行プランを練ることができません。
6-2.決めた計画に沿って行動する
Planのサイクルで全員が決めた目標は、途中で変更せずに計画的に実行することが大切です。決めた目標からブレずに正しく実行しなければ、良かった点や問題点を洗い出すことができません。
計画がうまくいかなかったときは、Actionのサイクルで改善案を考えることになります。
しかし、Doの時点で計画に沿って行動できていないと、何をどこまで立て直せば良いのかの判断もつきにくくなります。目標に向かう計画を立てたら、計画通りに実行することが大切です。
6-3.無理な計画や目標は立てない
会社やチームの業績をアップさせるために高い目標を掲げることは大切です。ただ、どう頑張っても達成できない非現実的な目標を設定するのは避けましょう。
どうやっても達成できないような目標を立ててしまうと、そのあとのDCAのサイクルを回す意味がなくなってしまいます。
最初のPlanで設定する目標は、改善点を洗い出せばギリギリ達成できる数値からスタートするのが良いでしょう。
高い目標は、Actionで改善点が多く見つかり「これを実行すれば大幅な業務改善が見込める」とわかった時点で設定すると効果的なPDCAになります。
6-4.定期的に進捗状況を確認する
PDCAのどのサイクルでも共通ですが、チームのメンバーや上司に対して、「今はどのサイクルにいるのか」「どのような計画を立てたのか」といった進捗を定期的に報告・確認しましょう。
進捗を確認し合うことによって、現状を整理する時間が持てます。また、目標に対してズレがあるときは上司の指示やアドバイスによって早期の軌道修正も可能になります。
進捗の確認は気が向いたときではなく、決まったタイミングでおこないましょう。「毎週月曜日の朝10時からチームでPDCAを振り返る」といったように、定期的に現状の把握や見直しの時間を設けると、軌道修正もスムーズにできるでしょう。
7.工場・製造業におけるPDCAサイクルの例
ここでは、工場・製造業でどのようにPDCAサイクルが使われているか、その例をご紹介します。
7-1.食品工場の例
食品工場では、食べ物を扱っていることもあり、清潔な空間を維持することが大変重要です。「5S(整理・清掃・清潔・清掃・しつけ)」と呼ばれる職場環境の改善・維持活動において清掃を重点的におこなうためのPDCAの利用例をご紹介します。
- 5Sのうち清掃のチェック項目の評価が低く、清掃を強化する必要があるとわかった
- 特に出荷場の汚れがひどいため、毎朝の始業後に清掃し、次回の評価を4以上にすると目標を立てた(Plan)
- 実際に人員配置と清掃の分担を決めて毎朝決まった時間に実行した(Do)
- 清掃状況を定期的に確認し、清掃前との変化を画像でチェックして比較した(Check)
- 掃除ができていない箇所について改善点を探し、対策を練った(Action)
清掃の質を上げるには、担当者や掃除の進め方などを具体的に示したほうが現場に反映されやすいでしょう。冒頭で紹介した5W2Hを用いて、なるべく具体的に対策を考えましょう。
7-2.自動車製造工場の例
PDCAの考え方は自動車工場でもよく導入されています。とある自動車メーカーでは、海外に進出したときに競合に遅れをとっていた状況を取り戻すためにPDCAを使った実績があります。
- アメリカに進出した直後は競合に競争力で負けている状態であり、競争力を高めるために効率的な生産方式の導入を決めた(Plan)
- 生産現場の無駄を徹底的に削減し、必要なものを必要なときに必要な量だけ生産する体制を構築した。異常が出たときは自動停止する方式を採用し、競争率を高める根本であるコストカットに努めた(Do)
- 現場作業員と管理者が検証をおこない、不良品や問題の発生があればラインを停止して管理者が問題を解消する仕組みを作った(Check)
- 生産工場に携わる作業者と管理者が毎日改善提案をおこない、可能なことはすぐに取り入れた
このように、チーム内の業務改善だけでなく、会社の大きな舵取りをおこなう際にもPDCAは利用できます。
8.PDCA以外のサイクルの紹介
PDCAは製造業でよく使われるフレームワークですが、回しきるのに時間がかかるなどのデメリットもあることから時代遅れといわれるケースも出てきました。最近では、PDCAのデメリットを補てんする新たな考えが浸透し始めています。
ここでは、PDCA以外の新しいサイクルについて、それぞれの概要、各文字の意味、PDCAとの違いなどを解説します。
8-1.OODAループ
OODAは「ウーダ」と読み、以下の4つの言葉で構成されています。
- Observe:観察
- Orient:状況判断
- Decide:意思決定
- Act:行動
OODAループは命を守るために瞬時の判断が求められる戦場で生まれた背景があり、PDCAよりもスピード感のある意思決定モデルです。Planが重要視されるPDCAと異なり、観察と状況判断が重視される特徴があります。
立案した計画に固執せず、相手を観察することで柔軟に計画を見直し、現状を把握することでスムーズな意思決定をするサイクルです。
8-2.STPDサイクル
STPDサイクルとは、計画を立てる前の段階の現状把握を重視する手法です。以下の4つの単語で構成されています。
- See:観察
- Think:考察
- Plan:計画
- Do:実行
See(観察)とThink(考察)がわかれている点に大きな特徴があり、目標と現状の差をしっかり分析することが重視されます。
時間をかけて丁寧にサイクルを回すPDCAと異なり、分析の精度を徹底的に高めることで、現状とのギャップが小さい現実的な目標設定が可能となります。
8-3.PDRサイクル
PDRサイクルとは、PDCAサイクルよりも早く仮説検証ができる手法です。以下の3つの単語から構成されています。
- Prep:準備
- Do:実行
- Review:評価
PDCAサイクルに4つの段階があるのに対し、PDRサイクルは3つのサイクルで構成されています。綿密に計画を立てるPDCAと違い、準備ができたらとにかくやってみることを重視しています。
準備ができたらすぐにサイクルを回すことで、よりスピーディに評価の項目までたどりつくことができます。
また、PDCAでは前例をもとに改善をおこなう傾向が強い反面、PDRサイクルでは担当外の方の意見を取り入れることで大胆なアイデアを出しやすい点も特徴です。
8-4.DCAPサイクル
PDCAのサイクルを入れ替えた手法です。構成されるサイクルはPDCAと同じですが、先に行動するというスピーディさに重点が置かれています。
Doでまず行動を起こして市場や競合の動きをつかみ、Planのサイクルは評価と改善を済ませた最後のステップでおこなうことになります。
9.まとめ
PDCAは仕事の質を向上させるための基本的なフレームワークで、製造業を中心に各業界で採用されています。
一度だけの取り組みではなく、継続的に改善と目標設定をおこなうことで業務の質を上げることが可能です。一方、計画立案を重視するため、実行や評価、改善までたどりつくのに時間がかかるというデメリットもあります。
PDCAのメリットとデメリットを把握しつつ、近年登場したほかのフレームワークも参考にしながら、業務改善を進めていきましょう。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す