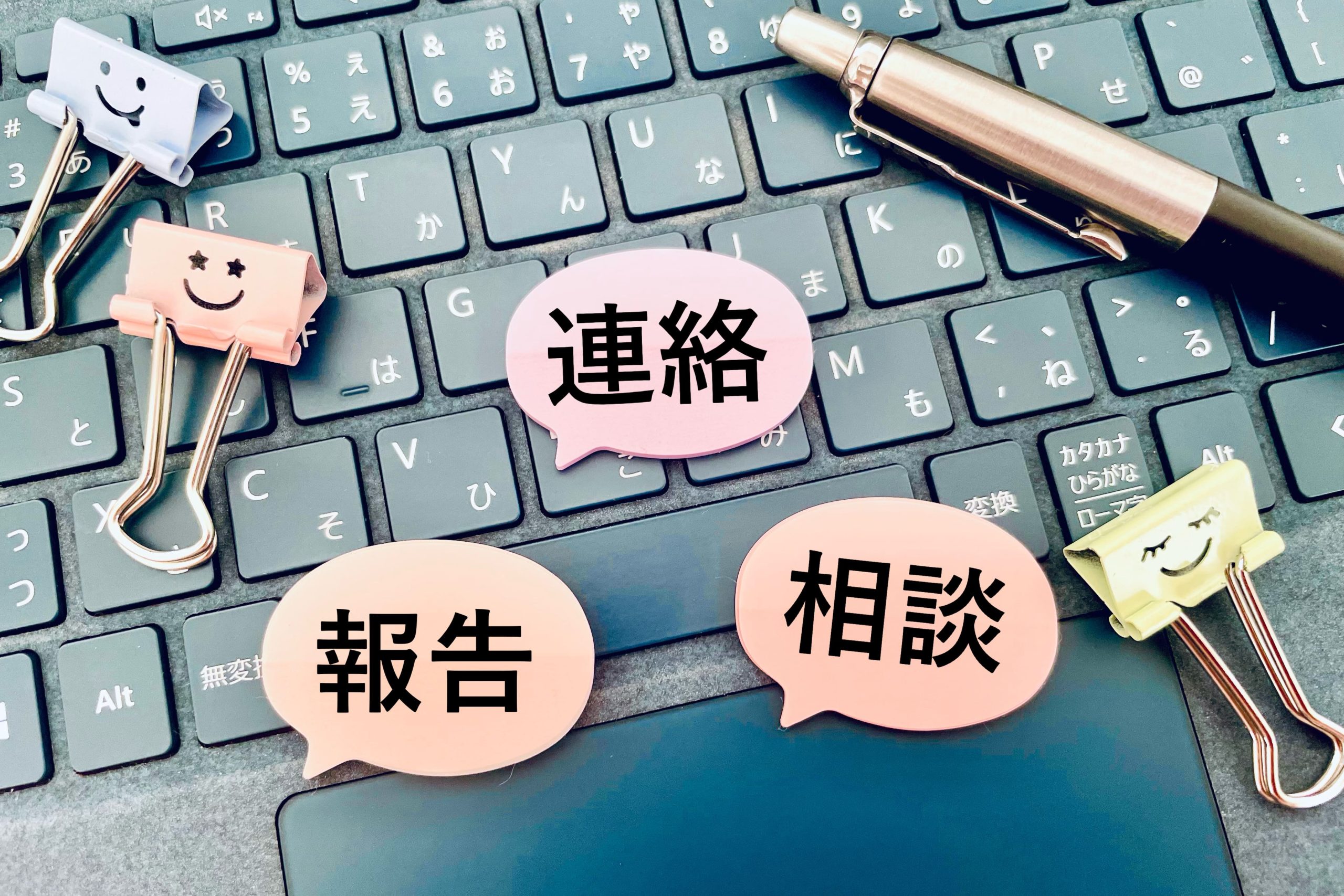教育訓練給付制度とは?支給対象となる人や講座、活用するメリットや注意点

※この記事は6分30秒で読めます。
「教育訓練給付制度って何?」
「教育訓練給付制度の給付が得られる講座や資格が知りたい」
など、教育訓練給付制度に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
教育訓練給付制度は、条件を満たした方が所定の資格を取得したり講座を受講したりすることで、最高で受講費用の70%相当額を受給できる制度です。
今回は、教育訓練給付制度の概要、支給対象者、対象になる講座・資格などを解説します。この記事を読めば教育訓練給付制度のことがよくわかり、キャリア形成に活かせます。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、労働者または離職中の人が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講・修了することで、費用の一部(入学料や授業料など)が支給される給付金です。
教育訓練の受講費用の負担を軽くすることによって、知識・スキルの習得や資格の取得などを支援してくれます。雇用保険の制度であり、在職者が受講した場合でも雇用主ではなく本人に金銭が支給されます。
教育訓練給付制度には、一般教育訓練給付や専門実践教育訓練給付などいくつかの種類があり、それぞれで支給条件や金額・対象講座が異なる点に注意が必要です。
2.教育訓練給付金の支給対象者
教育訓練給付金は以下の4つの制度に分かれています。まずはそれぞれの制度の対象者や支給要件などの違いを見ていきましょう。
2-1.一般教育訓練給付
一般教育訓練給付は、学びたい方のキャリアアップやスキルの向上を目的に、労働者の長期雇用や再就職を促進する制度です。
【支給対象者の要件】
一般教育訓練給付を受けるには、以下のような要件があります。
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は一年以上)であること
- 受講開始日時点において被保険者でない(離職している)場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降で、受講開始日までが一年以内であること
- 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上が経過していること
【支給される金額】
一般教育訓練給付の支給額は、教育訓練受講費用の20%相当額かつ上限が10万円です。その金額が4,000円を超えない場合は支給されません。
2-2.専門実践教育訓練給付
専門実践教育訓練給付は、業務独占資格や名称独占資格などを取得し、特に中長期的キャリア形成を目指して学びたい方のための制度です。
【支給対象者の要件】
専門実践教育訓練給付を受けるには、以下のような要件があります。
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は2年以上)であること
- 受講開始日時点において被保険者でない(離職している)場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降で、受講開始日までが一年以内であること
- 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上が経過していること
【支給される金額】
専門教育訓練給付の支給額は、教育訓練受講費用の50%相当額かつ上限が年間40万円(3年で120万円が上限)です。その金額が4,000円を超えない場合は支給されません。
また、専門実践教育訓練の受講を修了したあとで事前に定められた資格などを取得し、受講修了日の翌日から一年以内に雇用された方や、すでに雇用されている方には、教育訓練経費の20%相当の額が追加で支給されます。
したがって、この場合は50%+20%で計70%の受講費用を受給できます。受講期間が3年なら168万円、4年なら224万円が上限です。
2-3.特定一般教育訓練給付
特定一般教育訓練給付は、平成31年3月の「雇用保険法施行規則」の改正により、従来あった一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金に加わる形で創設された制度です。
介護職やIT関連職などキャリア形成効果が高い講座が対象で、速やかなキャリアアップや再就職を目的にしています。
【支給対象者の要件】
特定一般教育訓練給付を受けるには、以下のような要件があります。
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は2年以上)あること
- 受講開始日時点において被保険者でない(離職している)場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降で、受講開始日までが一年以内であること
- 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
【支給される金額】
特定一般訓練給付の支給額は、教育訓練受講費用の40%相当額かつ上限が20万円です。その金額が4,000円を超えない場合は支給されません。
2-4.教育訓練支援給付
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を初めて受講する人が、「受講時に45歳未満」などの一定の条件を満たして失業状態にある場合に受給できる給付金です。
受給できる金額は、訓練受講中の基本手当の支給を受けられない期間は、基本手当の日額と同様に計算した金額の80%(上限あり)です。2ヵ月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じた額が支給されます。
なお、こちらは令和7年3月31日までの時限措置である点に注意が必要です。
3.教育訓練給付制度の対象となる講座・資格
ここからは、教育訓練給付制度の対象になる講座や資格について解説します。輸送・機械運転や技術・農業などを中心にピックアップしてご紹介するので、教育訓練を探す参考にご利用ください。
3-1.輸送・機械運転関係
輸送・機械運転関係では、普通自動車運転免許では運転できない大型の車両や特殊な車両の運転免許が対象となります。土木関係や運送会社、タクシー業界などへの転職を目指す方におすすめです。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 大型・中型自動車第一種・第二種免許 | 大型は車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、中型は車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員29人以下の車両運転に必要な免許 |
| 大型特殊自動車免許 | 全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下の特殊車両の運転で必要な免許 |
| 準中型自動車第一種免許 | 車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満の車両を運転するための免許 |
| 普通自動車第二種免許 | 旅客を運送する目的で、旅客自動車(タクシーなど)を運転する場合に必要な免許 |
| 玉掛け・フォークリフト運転・高所作業車運転・小型移動式クレーン運転・床上操作式クレーン運転・車両系建設機械運転技能講習・小型移動式クレーン運転・床上操作式クレーン運転・車両系建設機械運転技能講習 | 各フォークリフトやクレーンの操作に必要な技能を習得する講習 |
| 移動式クレーン運転士免許 | つり上げ荷重5トン以上(無制限)の移動式クレーンを運転するための免許 |
| クレーン・デリック運転士免許 | つり上げ荷重が5トン以上の天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、など各種クレーン・デリックを運転するために必要な免許 |
以下の記事ではフォークリフト、クレーン運転士の仕事内容などを詳しく解説しています。併せてご覧ください。
3-2.製造関係
製造関係の資格で教育訓練給付を受けられるのは、製菓衛生士のみです。和菓子・洋菓子などジャンル問わず製菓技術が身についていることの証明になるため、パティシエを目指す際などに活用できます。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 製菓衛生士 | 菓子製造の現場に就業できる名称独占資格 |
3-3.技術・農業関係
技術・農業関係では、土木や管工事、測量士補など現場作業に関する資格が対象となります。電気主任技術者試験も対象であり、ビルメンテナンスや製造業への就職を考えている方にもおすすめです。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 土木施工管理技士 | 土木工事現場の施工管理をするための資格 |
| 管工事施工管理技士 | 管工事現場の施工管理をするための資格 |
| 自動車整備士 | 自動車の定期点検や保守や修理作業などで必要な資格 |
| 電気主任技術者試験 | 電気設備の工事・運用・維持など、保安監督業務を担うための国家資格 |
| 測量士補 | 測量業者に従事して測量をおこなうために必要となる国家資格 |
以下の記事では、計量士や自動車整備士、電気主任技術者の仕事内容などを詳しく解説しています。併せてご覧ください。
3-4.事務関係
事務関係では主に、語学検定、会社の経理・会計に関する資格が対象となります。会社の事務職として転職したい方向けの資格としては以下の2つがあります。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 建設業経理検定 | 建設業特有の専門的な経理処理に関する知識を証明する資格 |
| 簿記能力検定 | 簿記の技術や知識を評価する検定 |
3-5.情報関係
情報関係の資格は、WordやExcelなどパソコンソフトのスキルや、CADやPhotoshop、illustrator、VBAなどのスキルを証明する資格が並びます。
製造業への転職に役立つスキルとしては以下の2つがあります。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| Microsoft Office Specialist2010、2013、2016 | Word、Excel、PowerPointなどのOfficeソフトについての利用スキルを証明する資格 |
| CAD利用技術者試験 | 全世界共通で利用されているオートデスク製品(CAD)の知識や操作技術を評価する試験 |
| 建築CAD検定 | CADを使って建築図面の作図をおこなう実践型の資格試験 |
3-6.医療・社会福祉・保健衛生関係
医療・社会福祉・保健衛生としては、介護関係の資格や研修が数多く対象になっています。
また専門実践教育訓練においては、介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士といった介護や社会福祉に関係する資格だけでなく、美容師や理容師、保育士、栄養士などさまざまな資格を受講できます。
介護業界のなかで特に知名度が高い以下のような資格も対象であり、介護業界への転職を希望する方にとって教育訓練はおすすめの制度です。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 介護職員初任者研修 | 介護の基礎的な知識やスキルを身につけることができる資格 |
| 介護支援専門員実務研修 | ケアプランの作成をはじめ、介護支援専門員としての業務を遂行するうえで基礎となる知識・技能を得るための研修 |
| 介護福祉士 | 介護に関する一定の知識や技能を習得していることを証明する唯一の国家資格 |
3-7.専門的サービス関係
専門サービス関係では、司法書士、行政書士、税理士など、いわゆる「士業」と呼ばれる専門的な資格が多くあります。
資格を勉強して会計事務所やコンサルティング会社で働き、将来的に有資格者として独立開業を狙いたい方におすすめの資格です。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 中小企業診断士 | 中小企業をターゲットに経営診断や助言をおこなう専門家になるための資格 |
| 司書・司書補 | 図書館(公立図書館と私立図書館)の専門的職員の資格 |
| 行政書士 | 官公署に提出する許認可などの申請書類の作成並びに提出手続代理などをおこなうための国家資格 |
| ファイナンシャルプランニング技能検定 | 顧客資産についての貯蓄・投資などのプラン立案・相談に必要なレベルを測るための技能検定。名称独占資格 |
3-8.営業・販売関係
営業・販売の資格としては、小売業、不動産業、飲食業などに関係する資格が対象です。不動産会社や飲食関係への転職におすすめの資格としては以下の2つがあります。
| 免許・資格の種類 | 概要 |
|---|---|
| 宅地建物取引士資格試験 | 不動産に関する重要事項を説明する国家資格 |
| 調理士 | 食の衛生・管理などの知識があることを証明できる国家資格 |
3-9.その他、大学・専門学校など
その他、大学・専門学校などでは、修士・博士、科目等履修や履修証明プログラムなど、大学や専門学校などの認定校に入学して科目を履修することが挙げられます。
例えば、職業実践専門課程は、専門学校のなかでも企業などと密接に連携して最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる学科として、文部科学大臣が認定する専門課程です。
4.教育訓練給付制度のメリット
教育訓練給付制度には以下のようなメリットがあります。
4-1.受講費用が一部支給される
教育訓練を受講することで、受講費用の一部が支給される点が最大のメリットです。
一般・特定一般・専門実践のうち、どの教育訓練を利用するかで支給額は変わりますが、少なくとも受講費用の20%、最大で70%相当の支給を受けられます。
お金に困って資格取得や講座受講を諦めていた方でも、この制度を上手に活用することで、資格の取得やスキルアップが可能となります。
4-2.スキルアップにつながる
教育訓練給付を受けると費用面の心配が抑えられるため、資格取得や講座受講にチャレンジしやすくなります。
資格を取得できればスキルアップや自身の価値の向上につながり、転職活動を有利に進めることも可能になるでしょう。
4-3.就職前に資格を取れる
取得しておくことで、即戦力として評価されることが期待できる資格もあります。
例えば、大型免許やフォークリフト免許などは取得していれば入社早々から幅広い現場で働ける可能性がありますし、企業側には資格取得の補助をしなくて済むメリットがあります。
5.教育訓練給付制度の注意点
受講費用の一部を支給してもらえるという大きなメリットがある教育訓練給付制度ですが、以下のような注意点があることも覚えておきましょう。
5-1.出席率が8割以上ないと支給されない
教育訓練給付金は、「失業していることについての認定を受けた日」に支給される制度です。原則として、失業認定の対象となる支給単位期間(2ヵ月)に教育訓練を受講した日が開講日の80%以上のときに失業認定されます。
出席率の計算方法は以下のとおりです。
出席率(%) = 出席日数÷当該者が出席すべき訓練実施日数×100
出席率が80%未満となった支給単位期間が発生すると、期間全部について不認定となり、教育訓練支援給付金を受け取れないため注意が必要です。
5-2.教育訓練修了後に支給される
教育訓練給付金を受け取れるのは、教育訓練の前ではなく、訓練が終わったあとです。費用は原則先払いであり、一度全額を支払う必要があります。
教育訓練給付金分を差し引いて支払うことはできないことを覚えておきましょう。
5-3.本人がハローワークで申請する
教育訓練給付金を受け取るための申請や手続きは、居住地のハローワークでおこないます。本人がハローワークを訪問してすべての手続きを完了させないと給付は受けられません。
目的の資格を取得できれば自動的に支給されるという制度ではありませんので、注意が必要です。
6.教育訓練給付制度に関するQ&A
最後に、教育訓練給付制度に関してよくある質問と回答をまとめました。
6-1.感染症などで受講できなかった場合はどうしたら良いのでしょうか?
特定の感染症などに罹患したことで受講ができなかった場合、それが本人や親族、同居人であり、医師または担当医療機関関係者が自宅待機が必要と判断したケースでは、出席すべき訓練実施日数から除外する日と定められています。
-
参照:インフルエンザなどの感染症に感染した場合の職業訓練受講給付金の支給申請などの取扱いが変わります
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/var/rev0/0110/8368/201342155042.pdf
したがって、訓練実施日(分母)から感染症などで休んだ日数を除外して出席率を計算することになります。
6-1.大地震など、大規模な災害があった場合はどうしたら良いのでしょうか?
大規模な災害などにより訓練実施施設への通所が困難な場合、訓練実施日から除外して出席率を計算します。
ただし、受講機関まで行けない状態(交通機関の運行が終日ストップ)であることなどが条件です。人身事故や交通事故で一時的に運航がストップするケースは含まれません。
-
参照:教育訓練支援給付金
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207147.pdf
7.まとめ
教育訓練給付金は、必要な条件を満たした場合に、所定の資格取得や受講をして、受講料の20%~最大70%に相当する金額が支給される制度です。
本人がハローワークで手続きすること、出席率が80%以上にする必要があることなどの注意点はありますが、うまく利用すれば金銭の心配抜きにキャリアアップを図れます。
転職活動を成功させたいなら、教育訓練給付金制度を利用してお得に資格やスキルの取得を目指しましょう。
資格やスキルが取得できたら、ぜひJOBPALの求人一覧からご自身に合った仕事を探してみてください。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す