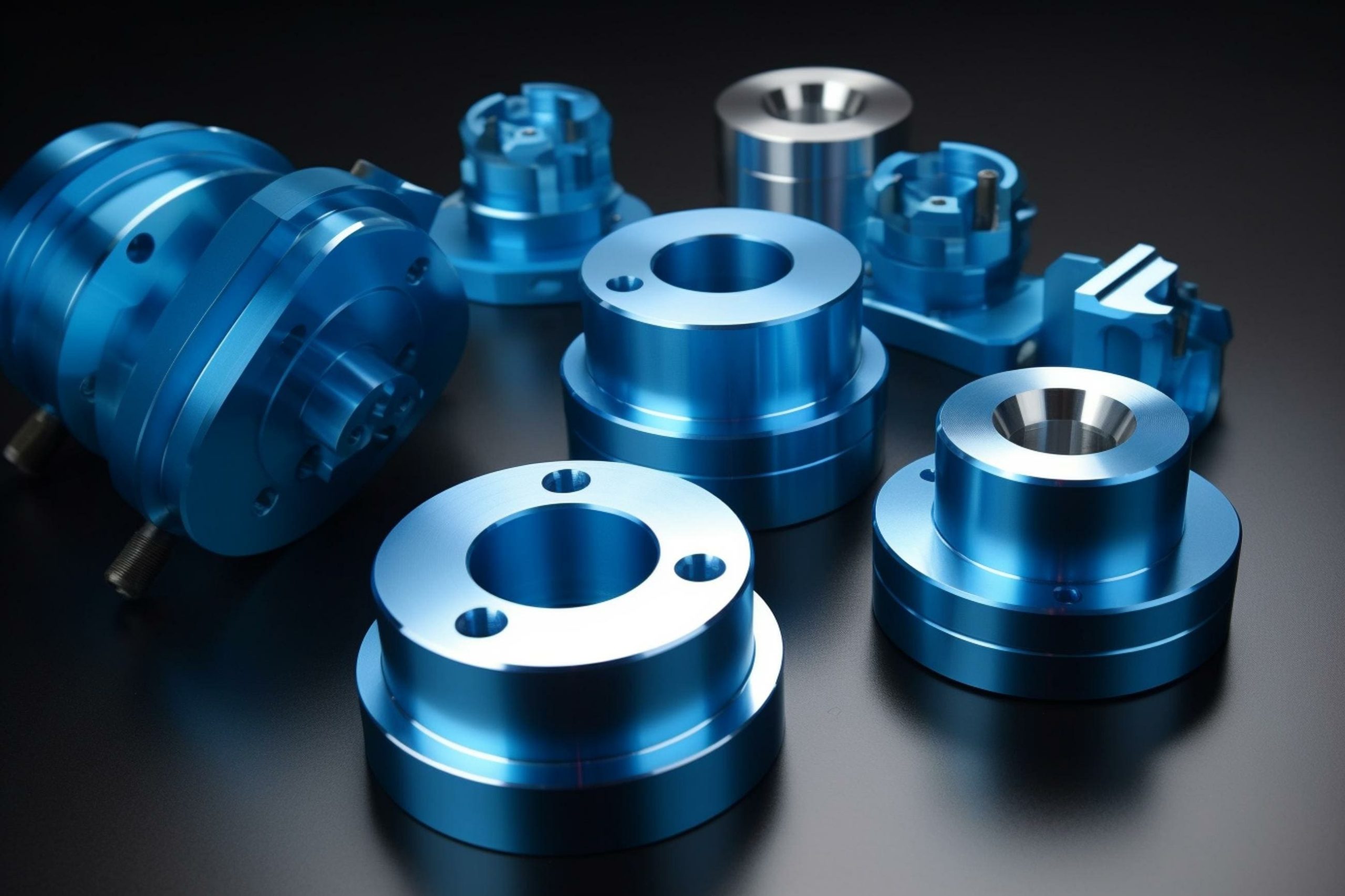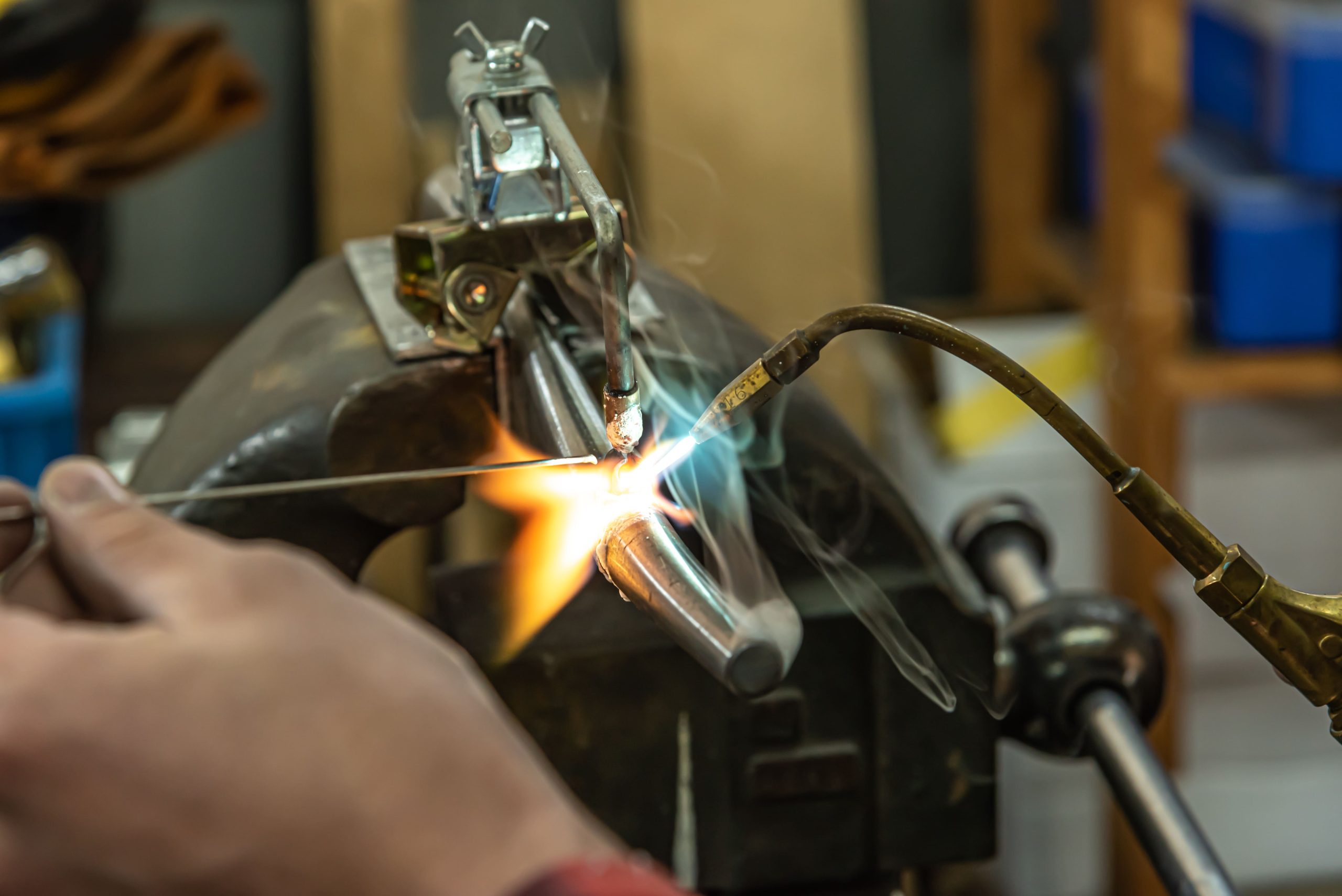電気主任技術者とは?キャリアパスや試験概要を解説

※この記事は5分で読めます。
「電気主任技術者ってどのような資格?」
「電気主任技術者を取得するメリットは?」
など、電気主任技術者に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
電気主任技術者は、電気設備に関する国家試験の一つで、有資格者を保守に配置することが義務付けられています。
今回は、電気主任技術者の概要、資格取得のメリット、試験の内容などを解説します。この記事を読めば、電気主任技術者のことがよくわかり、資格を取れば就職に活かすことができます。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.電気主任技術者とは
電気主任技術者は、ビルや工場などにおける電気設備の工事・運用・維持といった、保安監督業務を担うための国家資格です。
電気関連の資格でよく知られているのは、電気工事士でしょう。電気工事士は電気工事そのものを担当する一方で、電気主任技術者は電気工事現場の立ち合い・監督や、電気設備の保安・点検をおこなう点が大きな違いです。
電気工事士について詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。
2.電気主任技術者の必要性
電気主任技術者の必要性はどこにあるのでしょうか。企業からの視点と、安全管理の視点から説明します。
2-1.企業における電気主任技術者の重要性
事業用電気工作物(600ボルト以上の高圧受電設備)を扱う建物では、保安のため電気主任技術者の資格保持者を配置することが義務付けられています。
電気主任技術者が電気設備を適切に運用し、保守点検作業をおこなうことで、トラブルや事故を未然に防止でき、コスト削減につながるのです。
ずさんな管理などが原因で事故が起きたり、法令違反をしてしまったりすると、企業はコストや信頼性の点で多大な不利益を被ってしまいます。電気主任技術者はこのようなトラブルを未然に防ぎ、企業利益に貢献しています。
2-2.電気主任技術者が担う安全管理
電気主任技術者は電気設備の点検・整備・改善をおこない、電気を安全に使用できる環境を整えます。電気設備に異常が起きた場合はその原因を調査し、対処します。
また、電気主任技術者は現場での保安教育を担う役目でもあります。感電や漏電、火災などの事故を起こさないためにも、電気主任技術者による教育や指導は重要です。
3.電気主任技術者の資格を取得するメリット
電気主任技術者の資格を取得するメリットを、3つ紹介します。
3-1.さまざまな業界で活躍できる
電気設備の点検や管理は、業界を問わず必要です。電気主任技術者の資格取得者は工場やメーカー、通信会社などさまざまな業界や職場で活躍できるでしょう。
3-2.就職や転職に有利に働く
電気主任技術者は、事業用電気設備を適切に運営するうえで欠かせない存在です。しかし、技術者の高齢化や試験の難易度の高さが影響して、将来的な人手不足が懸念されています。
2020年に経済産業省が発表した「電気保安をめぐる現状と今後の課題」によると、2030年には全体の1割となる2,000人の技術者(第三種電気主任技術者)が不足するとされています。このように人手不足が深刻になっていくなかで、電気主任技術者の需要は高まると考えられるでしょう。
-
参照:経済産業省「電気保安をめぐる現状と今後の課題」
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/002_03_00.pdf
3-3.年収が向上する
電気主任技術者の資格を保有していると、資格手当を得られる場合があります。手当の額は企業により異なりますが、5,000円から1万円となることが多いようです。
さらに電気主任技術者は定年後でも働けるケースが多く、年齢を重ねてからでも安定して収入を得やすいといえます。
4.電気主任技術者のキャリアパス
ここでは、電気主任技術者として活躍するにあたってのスキルアップや、資格を活かせる職種などを紹介します。
4-1.電気主任技術者としてのスキルアップ
電気主任技術者としてスキルアップするには、日々の業務範囲だけではなく、電気設備全般に関する知識を身につけることが求められます。そのためには、電気設備に関係したほかの資格の取得もスキルアップに役立ちます。
例えば、電気設備の工事や取り扱いに必要な国家資格である電気工事士や、自家用電気設備の保安業務をおこなう電気管理技術者を目指すと、効率的にスキルアップが可能です。
なお、電気主任技術者を取り巻く環境は絶えず変化しています。日々の学習や研修への参加などにより、知識・技術をアップデートしていくことが重要です。
4-2.電気主任技術者を活かした職種
電気主任技術者は、電気設備の運用・維持・保安管理の担当者として活躍できます。
また、電気主任技術者の資格を持っていると、「電気工事施工管理技術検定」の受検資格を得られます。この資格を取得すれば、設計・施工に関する業務に携わることもできるでしょう。
その他、電気主任技術者のなかには、電力会社や設備メーカーの技術営業職に就く方もいます。
5.電気主任技術者試験
電気主任技術者は、やみくもに勉強して資格取得できるほど簡単な試験ではありません。ここでは、資格取得の効果的な勉強法と、試験の概要や難易度を見ていきましょう。
5-1.電気主任技術者試験の勉強法
試験勉強では参考書をフル活用しましょう。何冊も手を出すのではなく、一冊の参考書を繰り返し読み、知識を着実にインプットする方法がおすすめです。
勉強の順番ですが、まずベースとなる理論を学び、それから電力や機械など実践的な内容に移ります。そして、勉強したことを法規の学習でまとめるイメージで進めていくと良いでしょう。過去問題を繰り返し解いて、身につけた知識をアウトプットする練習も大切です。
すでに実務を経験している方は、実際の現場で問題解決するイメージを持って勉強すると、資格だけでなく仕事に必要な知識や技術も習得できます。
なお、電気主任技術者試験は難易度が高い試験です。独学だけではなく、試験対策講座や研修も積極的に活用し、モチベーションを維持しながら勉強してみてください。
5-2.第一種電気主任技術者試験
電気主任技術者試験は、第一種・第二種・第三種に分かれています。第三種・第二種・第一種の順に業務範囲が広くなることが特徴です。ここでは、第一種電気主任技術者試験の概要と難易度について見ていきましょう。
5-2-1.試験概要
第一種電気主任技術者は、すべての事業用電気工作物を扱える資格です。試験は年1回実施され、一次試験と二次試験に分かれています。2023年の一次試験は8月19日、二次試験は11月12日です。
一次試験は科目ごとに合否が決定され、理論・電力・機械・法規の4科目のうち、一部の科目に合格した場合は「科目合格」となります。そして、翌年と翌々年の試験では合格している科目の試験が免除されます。
なお、二次試験に科目合格の制度はありません。ただし、一次試験に合格した年の二次試験が不合格だった場合は、翌年の一次試験が免除され、二次試験から受験できます。
受験料は以下のとおりです。
- インターネット申し込み:1万3,800円
- 書面申し込み:1万4,200円
5-2-2.試験難易度
2018年~2022年の第一種電気主任技術者の合格率は、低い年で8%、唯一20%を超えた年が、2022年の20.9%でした。平均して20%を切る合格率で、難易度が高い試験であることは確かです。
5-3.第二種電気主任技術者試験の概要
ここでは、第二種電気主任技術者試験の概要と難易度を取り上げます。
5-3-1.試験概要
第二種電気主任技術者は、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物を扱える資格です。試験は第一種電気主任技術者と同様、一次試験と二次試験に分けておこなわれます。試験日程や受験料、一次試験における一部科目の免除や一次試験の免除の仕組みは、第一種電気主任技術者試験と同じです。
5-3-2.試験難易度
2018年~2022年の第二種電気主任技術者の合格率は低い年で14.5%、高い年で27%超です。なお、2022年の合格率は24%でした。5年間の合格率を単純に平均すると21%超ですが、年によって合格率に約2倍の開きが生じています。第一種ほどではないものの、難易度は高い試験と考えられるでしょう。
6.電気主任技術者の資格が活かせる業界
電気主任技術者資格が必要とされる分野は、広範囲にわたります。ここで、電気主任技術者の資格が活かせる業界を紹介します。
6-1.ビルメンテナンス
ビルメンテナンスの業務には大型商業施設やオフィスビル、病院などの電気設備や空調設備の管理・保守・点検が含まれます。電気設備の導入から運用まで担当する場合があり、幅広い知識や経験が身につけられるでしょう。求人企業としては、ビルメンテナンス会社のほか、大手不動産会社などが挙げられます。
6-2.工場ラインの保全管理
生産ラインを含む工場全体を安全に稼働させる保全管理が、工場ラインでの電気主任技術者の仕事です。点検や保守に加え、トラブルシューティングも必要になるため、さまざまな場面に対応できる力もつくでしょう。
6-3.施工管理
工場やビルなどの建設現場では事業用電気工作物が設置され、電気設備に関連した工事の監督は電気主任技術者が担います。おもな仕事内容は、工事の進捗管理や作業員の安全管理などです。どの建設現場でも必要な仕事であるため、電気主任技術者は引く手あまたで、建設会社や大手ゼネコンなどから求人が出されています。
7.まとめ
電気主任技術者は、ビルや工場などにある電気設備の保安監督業務を担います。国家資格である電気主任技術者を取得していると、さまざまな業界で働くことが可能になり、年収アップも期待できます。
電気主任技術者試験は3つの種類に分かれており、難易度の高い試験です。参考書や過去問題などを使って勉強するとともに、試験対策講座や研修を活用すると、合格への早道となるでしょう。
電気主任技術者の仕事に興味がある方は、JOBPALの製造・工場系の設備保守・保全の求人一覧をぜひチェックしてみてください。