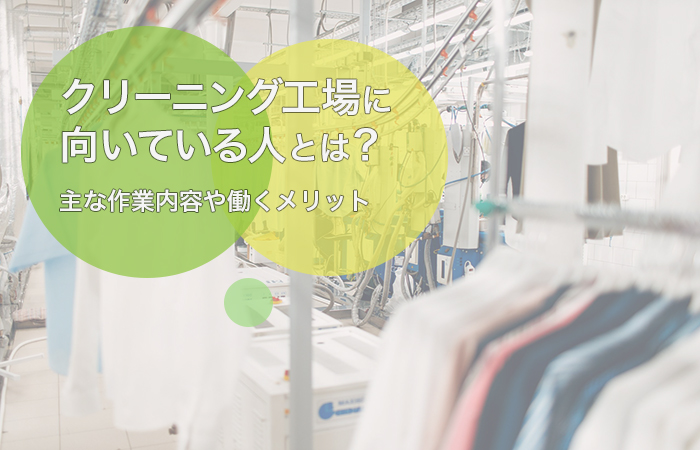電気工事士とは?仕事内容や資格の種類、活躍できる職場を徹底解説

※この記事は6分30秒で読めます。
「電気工事士ってどんな仕事?」
「電気工事士として働くメリットが知りたい」
など、電気工事士に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
電気工事士は電気設備や工事に関する国家資格で、住宅や商業施設、工場などの電気工事をおこなうことができます。
今回は、電気工事士の概要、第一種と第二種の違い、資格を取得する方法、向いている人の特徴などを解説します。この記事を読めば、電気工事士のことがよくわかり、電気工事士として働く自分の未来像をイメージしやすくなります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.電気工事士とは
電気工事士は、電気設備の取り扱いや工事に関する国家資格です。住宅や商業施設、工場などといった建物の電気工事をおこなう際に必須の資格であり、工事を進めるために必要な「電気配線図の作成」など、幅広い工事を担うことができます。
1-1.電気工事士の資格の種類
電気工事士の資格は作業できる範囲によって2つに区分されます。それぞれの資格内容を見ていきましょう。
1-1-1.第二種電気工事士
第二種電気工事士は、「一般住宅」「小規模な施設」の電気工事を担当できる資格です。600V以下で受電する「一般用電気工作物」を担当できます。
建物の電気工事に関連した管理に携わる「現場代理人」になる際にも有効です。現場代理人は有資格者である必要はありませんが、多くの場合は電気工事士の資格を持った人が担当します。
1-1-2.第一種電気工事士
第一種電気工事士は、ビルや工場、大規模施設の電気工事、高圧の送配電線路の電気工事を担当できる資格です。
第二種電気工事士よりも担当できる範囲が広がることで、給与をはじめとした待遇アップが期待できます。
1-1-3.第二種電気工事士と第一種電気工事士の違い
第二種電気工事士と第一種電気工事士の主な違いは「作業できる範囲」です。
第二種電気工事士は「一般用電気工作物」にしか従事できない一方、第一種電気工事士は「600V以上かつ500kW未満の自家用電気工作物」に従事できます。
第一種電気工事士なら、一般住宅や小規模施設だけでなく、ビルや工場、病院などでの大規模な電気工事を担当できます。
1-2.電気工事士の仕事内容
電気工事士の仕事は、大きく以下の2つに分類されます。
- 建設電気工事
- 鉄道電気工事
1-2-1.建設電気工事
建設電気工事は、ビル・工場・病院・住宅などの屋内・屋外電気設備の設計・施工をおこなう仕事です。
コンセントや照明器具の取り付けはもちろん、エアコンの設置工事にも電気工事士の資格が必要になります。
新築住宅では電気配線の設計・施工、配電盤や電気設備の設置など、電気に関する工事をゼロからおこなうほか、リフォームの配線に関する追加工事など、担当できる仕事は大小さまざまです。
1-2-2.鉄道電気工事
鉄道の電気設備の施工や保守をおこなう仕事です。架線、信号、踏切、駅の照明や通信設備、発電所や変電所など、電車を動かすには多くの電気設備が必要です。
電気工事士は、世界トップクラスといわれる日本の鉄道の正確な運航には欠かせない存在といえます。
2.電気工事士の資格を活かせる就職先
令和2年度電気技術者試験受験者実態調査「電気工事士試験受験申込者の勤務先」によると、第一種・第二種電気工事士の勤務先の種類と割合は以下のとおりでした。
| 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 | |
|---|---|---|
| 電気工事会社 | 5% | 7.7% |
| 電力会社 | 37.1% | 19.9% |
| ビル管理・メンテナンス・商業施設保守会社 | 10.1% | 13.9% |
| 電気機器製造会社 | 7.2% | 9.2% |
| 電気機器卸・小売店 | 0.3% | 0.3% |
| 電気通信工事会社 | 0.5% | 1.1% |
| 電気鉄道会社 | 4.4% | 3.7% |
| 建設会社 | 2.7% | 4.8% |
| ガス会社 | 1.5% | 1.2% |
| 食料品製造会社 | 0.7% | 1.6% |
| 石油、化学、紙パ製品製造会社 | 4.7% | 5.7% |
| 官公庁 | 9.1% | 8.1% |
| 団体 | 3.7% | 4.1% |
| その他 | 21.5% | 18.7% |
-
※出典 一般社団法人電気技術者試験センター|令和2年度電気技術者試験受験者実態調査
https://www.shiken.or.jp/pdf/fact_finding_r02.pdf
いずれの資格でも電力会社と答えた人がもっとも多く、次いでビル管理・メンテナンス・商業設備保守会社、電気工事会社、電気機器製造会社などで働いている割合が大きくなっています。
官公庁や団体、ガス会社なども含め、多種多様な就職先があるのが電気工事士の魅力といえるでしょう。
以下の記事では、設備保守について詳しく解説しています。
3.電気工事士の資格を取得する方法
電気工事士は毎年10万人を超える人が受験する人気資格です。ここからは、電気工事士を取得するための方法についてご紹介します。
3-1.電気工事士の受験資格
電気工事士には受験資格の制限がありません。上位の資格を取得するために下位の資格の取得を必要とする国家資格は多いですが、電気工事士に関しては年齢や学歴を問わず誰でも受験することが可能です。
3-2.電気工事士の試験スケジュール
第二種電気工事士の試験は年に2回、第一種電気工事士の試験は年に1回おこなわれます。主なスケジュールは以下のとおりです。
| 試験日程 | |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 学科:9-10月技能:12月 |
| 第二種電気工事士 | ・上期学科:4-5月 技能:7月・下期学科:9-10月 技能:12月 |
技能試験は実施日程が都道府県ごとに異なるため、詳しい日程については各自でご確認ください。
3-3.電気工事士の資格取得までの流れ
電気工事士の資格取得は、「受験の手続き」「試験」「免状の申請」の流れで進んでいきます。
3-3-1.受験の手続きをする
まず、試験の申し込みを書面またはインターネットでおこないます。受験料は以下のとおりです。
| 試験費用 | |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 10,900円(インターネット申し込み) 11,300円(郵便申し込み) |
| 第二種電気工事士 | 9,300円(インターネット申し込み) 9,600円(郵便申し込み) |
3-3-2.試験を受ける
第一種、第二種のどちらも筆記試験と技能試験(実技試験)があります。
「筆記試験」の試験時間は第一種電気工事士で140分、第二種電気工事士で120分です。50問×2点の配点となり、合格基準は約60点に設定されています。
「技能試験」の問題数は1問のみです。試験時間は第一種電気工事士が60分、第二種電気工事士が40分になります。支給される材料と持参した作業用工具を使い、時間内に問題を完成させないといけません。
なお、令和5年度からはCBT方式(コンピュータを利用して実施する試験方式)の試験も導入されることから、「筆記試験」から「学科試験」に名称が変更されます。
3-3-3.免状を申請する
試験の合格通知が届いたら、次に免状申請をおこないます。第二種電気工事士は試験に合格した後に免状を申請することで資格を得ることができ、実務経験は必要ありません。
免状の申請先は都道府県ごとに指定されており、電気工事工業組合など外部に委託している場合もあります。詳細は申請先の都道府県のホームページで確認してください。
免状の申請に必要な書類は以下の3つです。
- 技能試験合格通知書
- 電気工事士免状交付申請書
- 写真2枚(縦4cm、横3cm)
住民票や免状返送用封筒(返送用封筒)が必要な場合もあります。手数料は5,300円です。
第一種電気工事士の場合、免状を申請するには3年の実務経験と以下の書類の提出が必要です。
- 免状交付申請書
- 実務経験証明書
書類はいずれも、都道府県や免状交付業務をおこなう団体の公式サイトでダウンロードできます。
実務経験証明書を作成したら、以下の書類と一緒に提出します。
- 住民票(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm ※裏面に氏名を記入)
- 試験結果通知書のはがき
※すでに電気工事士の資格を保有している場合、資格を証明する書類の写しも必要
第一種電気工事士の免状申請には、6,000円の手数料が必要です。
3-4.電気工事士の合格率
電気工事士の合格率は第一種・第二種でそれぞれ以下のとおりです。
| 筆記試験 | 技能試験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 2019年(令和元年) | 122,266人 | 80,625人 | 65.9% | 100,379人 | 65,520人 | 65.3% |
| 2020年(令和2年) | 104,883人 | 65,114人 | 62.1% | 72,997人 | 52,868人 | 72.4% |
| 2021年(令和4年) | 156,553人 | 92,640人 | 59.2% | 116,276人 | 84,684人 | 72.8% |
-
※出典 一般財団法人電気技術者試験センター|試験実施状況の推移
https://www.shiken.or.jp/situation/index.html
4.電気工事士の資格を取得するメリット4つ
電気工事士は国家資格の一種であり、取得することでさまざまなメリットを得ることができます。
4-1.さまざまな施設で需要がある
電気は生活に欠かせないものであり、電気を扱う仕事は今後も高い需要が見込まれます。
電気工事は有資格者でないと作業できないため、手に職をつければ電気工事の専門家として活躍できるでしょう。将来的にも仕事は途絶えることがなく、資格保有者のニーズは常にあると考えられます。
4-2.電気工事業を開業できる
現場で十分に実務経験を積んだあとに、独立開業する方法もあります。一般家庭向けの電気工事を請け負ったり、事業者の下請けとして電気工事を請け負ったりするなど仕事は幅広く、年齢を重ねても安定した収入を狙えます。
4-3.資格手当がもらえる
電気工事士が必要な企業にとって、資格保有者の雇用は重要です。資格保有者に対し、給与に資格手当をプラスして支給する企業もあります。
4-4.就職・転職で有利になる
電気工事士の需要は多く、求人も安定しています。電気工事やビルメンテナンスの専門業者では、電気工事士の資格保有を必須とする部署も少なくありません。
オール電化住宅や太陽光発電設備など家庭での需要が高まっていることもあり、電気工事士資格を持っていると転職や就職で有利です。
4-5.自宅のDIYやリフォームなどにも使える
自宅を自分でリフォームするなど、プライベートでも電気工事士の資格は役に立ちます自宅の配線や工事を必要とする照明器具の取り付けなど、DIYやリフォームも自分で作業することができます。
5.電気工事士の仕事の魅力
電気工事士の仕事は、「電気」という人にとって必要不可欠なインフラを支える点が魅力です。現代は電力を使って動作するものが圧倒的に多く、電気がなければ生活も仕事も成り立ちません。
人から感謝される瞬間も多く、やりがいを感じることができます。「人々の生活を支えている」という誇りをもって仕事ができるでしょう。
6.電気工事士の関連資格5つ
電気工事士の資格だけでも仕事はできますが、他の資格と組み合わせることでさらに仕事の幅は広がります。ここでは、電気工事士と関連が深い資格の種類や特徴についてご紹介します。
6-1.特種電気工事資格者
電気工事のなかでも「ネオン工事」「非常用予備発電装置工事」については専門的な技術・知識が必要であり、特殊電気工事資格者の資格が求められます。
現役の電気工事士が、業務範囲を広くするために取得することが多い資格です。
6-2.認定電気工事従事者
第二種電気工事士は電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(一般家庭の工事など)しか施工できませんが、認定電気工事従事者を取得するとビル・マンションの照明・コンセント設置などの簡単な工事ができるようになります。
第二種電気工事士および電気主任技術者で3年以上の実務経験があれば取得でき、第一種電気工事士は申請するだけで取得できます。
6-3.電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、工事の管理をするための国家資格です。電気工事の施工計画や施工図の作成、工程管理、品質管理、安全管理など、工事の監督業をおこなうために必要になります。
1級と2級があり、学歴や現場監督などの実務経験によって受験資格は異なります。施工管理上の技術責任者として位置づけられている重要な資格です。
6-4.電気主任技術者
電気主任技術者は、電気事業法に基づいた国家資格です。取り扱いできる事業用電気工作物の電圧により「第一種」「第二種」「第三種」の3つに分類されます。
ビルや工場、発電所、変電所などにおける電気設備の「保安監督業務」が主な仕事です。これらの業務は電気主任技術者しかおこなえません。電気工事士を監督する立場の資格であり、電気工事士は電気主任技術者の指示をもとに作業をおこなうことになります。
6-5.電気通信主任技術者
電気通信ネットワークの工事や維持、運用の監督責任者のための資格です。電気通信事業者は、総務省令で定められた技術基準に適合するよう電気通信主任技術者を選任し、電気通信設備の工事、維持および運用の監督にあたる義務があります。
7.電気工事士の仕事に向いている人
どのような仕事にも、人によって向き・不向きがあり、長く働くには自身に合った仕事を見つけることが重要です。電気工事士の仕事に向いている人の特徴について解説します。
なお、電気工事士を含めた「技術職」の種類や求められるスキルについて知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
7-1.人のために働きたい人
電気工事士は社会に欠かせないインフラを支える存在であるため、自分の仕事が誰かの役に立っていることがダイレクトにわかる業務です。役立てていることに喜びを感じる人には向いています。
7-2.几帳面な人
電気工事は複雑な配線を設計・施工する仕事であり、一つのミスもなく作業することが求められます。雑な作業では大事故につながる恐れもあります。そのため、几帳面で正確な作業ができる人に向いているでしょう。
7-3.コミュニケーション力がある
建物を作るには、電気設備だけではなくさまざまな専門家と力を合わせて作業しなければいけません。ビルメンテナンスの場合でも、管理会社やビルオーナーなど大勢の人とコミュニケーションを密に取ることが求められます。
一人で黙々と作業するイメージがあるかもしれませんが、実際にはコミュニケーション力が必要となります。
8.まとめ
電気工事士は電気に関する工事のエキスパートです。「電気」の重要性は今後も不変であることから安定した需要があり、この先、日本がどのような姿になっても、仕事に困るリスクは少ないといえるでしょう。
そして、さまざまな職場で働くチャンスもあります。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?