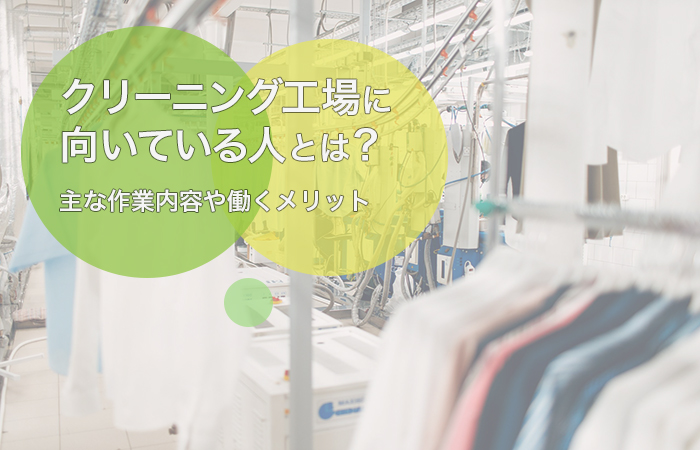高所作業とは?仕事の種類や必要な資格、労働安全衛生法で定められる安全対策を紹介

※この記事は6分30秒で読めます。
「高所作業ってどんな仕事?」
「高所作業の仕事をするのに必要な資格が知りたい」
など、高所作業に関して興味や疑問を持っている方もいるでしょう。
高所作業とは高さ2メートル以上の場所でする作業で、状況に応じてさまざまな機械を使い、足場を組んで作業をおこないます。
今回は、高所作業の概要や種類、高所作業に必要な資格、向いている方・向いていない方の特徴などを解説します。この記事を読めば高所作業のことがよくわかり、自分が働いている姿をイメージできるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.高所作業とは?
高所作業とは、2メートル以上の高さでおこなう作業のことです。この高さは、労働安全衛生法などによって定められています。
万が一落ちてしまうと大事故につながることから、2メートル以上の高所で作業をする際は安全措置を取る必要があります。具体的な安全措置としては「フルハーネス型墜落制止用器具の着用」「作業床や手すり・囲いの設置」などが挙げられます。
簡単な作業ですぐに終わるからと考えず、事故防止のためにルールを守った安全措置を取りながら働くことが重要です。
2.高所作業の種類
ひとくちに高所作業といっても、その種類はさまざまです。大まかな高所作業の種類としては、以下の4つが挙げられます。
2-1.高層ビルの窓清掃
作業用のゴンドラに乗り、高層ビルの窓掃除をおこなう仕事です。オフィス街ではひんぱんに見られる光景で、一般的にイメージしやすい高所作業の一つです。
ゴンドラ以外に、屋上からロープをたらしてブランコを取り付け、作業員がブランコに乗りながら清掃をおこなうケースもあります。
作業員が乗り込むゴンドラの高さはビルの高さによっても異なりますが、15~25メートル以上の高さで作業をおこなうことも珍しくありません。
2-2.解体工事・建設工事
足場を組んだうえでおこなう「解体工事」「建築工事(外壁工事・天井工事)」なども高所作業の一つです。
よく見かける「脚立」や、脚立にキャスターがついている「移動式足場」、より高い場所での作業に対応できる「枠組み足場」など、作業内容によって異なる足場を利用します。2メートルを超えた高さで作業をする場合は、いずれも高所作業の対象です。
高層ビルのようなより高い場所での作業の場合は、高所作業車やクレーンなどを使うこともあります。
2-3.天井内の点検
建築工事における電気工事や空調・給排水設備工事などでは、天井の点検口から天井内に入って作業をすることがあります。その作業で発生する足場作業も高所作業の一つです。
例えば、工場の場合は一般家庭よりも天井が高く、5メートル近い高さの点検口で作業する場合もあります。その場合は脚立ではなく高所作業車を使い、足場をアームで伸ばす形で作業がおこなわれます。
2-4.屋外施設の点検
設備点検の対象が屋外に、かつ高い場所にある場合は、高所作業に該当します。高さによって使う足場はさまざまですが、足場を組んだり高所作業車を用いたりすることもあります。
送電線の建設・点検、橋のメンテナンス、太陽光パネルや風力発電用の風車、電波塔の保守点検など、作業の種類や高さはさまざまです。
送電線の保守・点検の場合は25メートル以上、風力発電用の風車の点検では高さ60メートルの高所で作業をすることもあります。
3.高所作業でよく使う機械類
高所作業では、作業をする高さによってさまざまな機械を使います。代表的な機械は以下の5つです。
3-1.脚立(きゃたつ)
脚立とは、2つのはしごを両側から八の字に合わせ、上に板を載せた形の踏み台のことです。
天板の高さが80cm未満かつ安全に乗れる天板の広さがあり、主に家庭で使用するものを「踏み台」、踏み台以外のものが脚立と呼ばれています。
一戸建ての建築現場など、高所作業のなかでも比較的低い位置で作業をする仕事に利用されるのが一般的です。
ちなみに、労働安全衛生規則という法律では、脚立は以下のように規定されています。
【脚立の規定】
- 丈夫な構造であること
- 材料に著しい損傷や腐敗がないこと
- 脚と水平面との角度を75度以下、かつ、折りたたみ式の製品は、脚と水平面との角度を確実に保つための金具などを備えること
- 踏み面は、作業を安全におこなうため必要な面積があること
-
参照:e-GOV|労働安全衛生規則第528条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032
3-2.手動昇降式移動足場
手動昇降式移動足場は、通常の足場のように1箇所に設置せず、付属するキャスターによって足場全体を動かして利用できる機械です。
バネバランス式という仕組みによって、足場の高さを手動で簡単に変更できるメリットがあります。納期が短い建設現場や、ピンポイントな補修作業で少しだけ足場が必要なシーンで利用されます。
3-3.仮設足場
仮設足場は、ビルやマンション、一般住宅などの新築・修繕の際に立てられる足場です。
新しく建てる建物や修繕する建物を「本設」と呼び、それを建築するために一時的に建てられるため「仮設」と呼ばれます。
3-4.トラック式高所作業車
トラック式高所作業車とは、トラックの荷台に高所作業機能がある機械を乗せた車両のことです。通常のトラックと同様に一般道でも走行でき、移動がスムーズにおこなえるメリットがあります。
また、移送のためのコストがかからないのもメリットの一つです。街路灯、信号機、電柱工事など作業現場が一般道路にある場合や、短時間で工事や点検を終わらせる必要があるケースで使用されます。
3-5.自走式式高所作業車
自走式式高所作業車とは、昇降装置にタイヤなどの自走機能が備わっている車両のことです。
トラック式と違って自動車ではないため公道を走ることができませんが、トラック式よりも小型であるため、小規模の建設現場や屋内高所での作業に使われます。
3-6.ブーム型
高所作業車には、「トラック式」「リフト式」といった分類に加え、作業足場の伸縮方法によっても以下のように分類できます。
- 伸縮ブーム型
- 屈折ブーム型
- 混合ブーム型
伸縮ブーム型はその名のとおりブームが伸縮することで高さを調整する高所作業車で、開けた場所での作業に向いている一方、狭い場所には向かないデメリットがあります。
屈折ブーム型はブームの中間部分が屈折するタイプで、狭い場所に入り込んで作業ができる一方、一般的に作業時の最大高が伸縮ブーム型よりも低い点がデメリットです。
混合ブーム型は、この2つのメリットを混合させた高所作業車となります。
4.高所作業で起こりうる事故の例
高所作業は、転落をはじめとした事故のリスクがある危険な作業です。高所作業で起こりうる事故には以下のようなものがあります。
工場の天井点検で高所作業車のリフトを上げた際、高所作業車の手すりと天井点検口のフレームとの間に首をはさむ
-
参照:職場のあんぜんサイト:労働災害統計
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=1087
高所作業車で大木の枝切作業中、高所作業車が後方に転倒して作業者が地面に激突
-
参照:職場のあんぜんサイト:労働災害統計
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101377
手すり、および落下防止シートを取り外した足場で荷取り作業をおこなっていて転落
いずれも実際に起こった事故であり、高所作業車の運転技術や安全対策が不十分であるなどの理由で発生しています。
高所作業をおこなう際は、このような事故を発生させないためにも、徹底した安全管理・安全対策が必要です。
5.高所作業の安全対策とは?
労働安全法において、高所作業は「2メートル以上の高さでおこなう作業」という定義があり、高所作業をする際は以下の決まりを守る必要があります。
- 高さ2メートル以上の作業場所には作業床を設置すること
- 作業床の設置が困難な場合は昇降できる器具を設置し、ローブを装備すること
- 作業床の端や開口部には囲いや手すりなどを設けて転落を防止すること
- 作業者は安全に昇降できる設置を必ず利用すること
- 作業現場では作業指揮者を設定すること
- 高所作業するときは事前に調査や計画を立てること
高さが2メートル以上の高所で作業をする場合、必ず作業床を設置しないといけません。建設現場に組まれた鉄板などが作業床に該当します。
作業床を設置することが難しい高所では、ゴンドラや高所作業車などの機械を使ったうえで身体にロープなどを装着する必要があります。
加えて、実際に作業をする担当者以外に「指揮者」を選定し、事前に高所作業に関する調査や計画を立てることも定められています。
6.高所作業に関する資格の種類
一部の高所作業では、特定の資格を取得しないと作業ができない場合があります。高所作業に関連する主な資格は以下のとおりです。
6-1.フルハーネス特別教育
フルハーネス特別講習は、フルハーネスを正しく使うための講習です。以下のような「フルハーネス着用と特別教育の義務化」がされている現場では、講習の受講必須です。
- 高さ2メートル以上の箇所において作業床を設けることが困難な場所でおこなう高所作業
- 墜落防止器具のうちフルハーネス型の墜落制止器具を用いておこなう作業
講習は、厚生労働省公表の「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づいておこなわれます。
講習時間は、学科で4.5時間、実技で1.5時間の合計6時間です。講習を受けないまま作業をすると罰則があるため、注意が必要です。
6-2.ロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業とは、高さが2メートル以上かつ作業床を設けられない場所でロープと昇降器具を使ってする作業のことです。
ロープ作業は作業床を設けることができないことから危険度が上がるため、ロープ高所作業特別教育の受講が義務付けられています。
講習時間は、学科で4時間、実技で3時間の合計7時間です。ロープ高所作業やメインロープの知識、関係する法律などを学びます。
6-3.高所作業車運転特別教育
高所作業者運転特別教育と、後述する高所作業車運転技能講習は、高所作業車を運転するのに必須の講習です。
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車を操作する場合は、高所作業車運転特別教育の受講が義務付けられています。
講習時間は、学科で6時間、実技で3時間の計9時間です。高所作業車の運転、作業に関する装置の取り扱いの知識だけでなく、原動機に関する知識や関係する法令なども学びます。
6-4.高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を運転する際に必須となる講習です。高所作業車運転技能講習を修了することで、すべての高所作業車の運転や操作に携わることができます。
講習時間は、学科で11時間、実技で6時間、学科試験で1時間の計18時間です。
7.高所作業の仕事が向いている方
高所作業はその性質上、人によって向き・不向きがあります。高所作業をする仕事に向いているのは、以下のような方です。
7-1.高い場所が好きな方
高所作業をおこなう方にとって重要な資質は、高い場所が得意であることといえます。高所では足がすくんで動けなくなってしまう方がいる一方、高いところがワクワクすると感じる方もいるでしょう。
高所作業は高さ2メートル以上の高所での作業になり、作業が終わるまで長時間にわたって降りずに作業をすることになります。高い場所が好きな方なら、恐怖心を感じることなくスムーズに仕事ができるはずです。
7-2.危機管理ができる方
高所作業は常に危険と隣合わせです。作業床の上で重量物を扱うこともあり、少しのミスや油断が大事故につながる恐れがあります。
事故を防ぐためにはさまざまなところに注意を払う必要があるため、危機管理を徹底しておこなえる方に向いているでしょう。
7-3.慎重な性格の方
高所での作業中は、手足を滑らせて落下したり、工具を落としたりして事故が発生するリスクがあります。
周囲をよく観察してリスクを把握し、一つひとつの作業を慎重かつ丁寧におこなえる方が高所作業に向いています。
7-4.ルールを守れる方
高所作業で過去に起きた事故のなかには、決まりを守っていなかったことで発生したものが少なくありません。
事故を未然に防ぐためのルールを守らずに作業をしていては、事故が発生するのも当然といえるでしょう。したがって、決められたルールを守って作業できる方が高所作業には向いています。
8.高所作業の仕事が向いていない方
以下のような特徴に当てはまる場合、高所作業には向いていない可能性があります。自分の性格が高所作業に向いているかを確認してみましょう。
8-1.高い場所が苦手な方
高い場所への耐性は人によってさまざまで、ワクワクする方もいれば足がすくんでその場から動けなくなってしまう方もいます。
高所作業では、長時間にわたって2メートル以上、現場によっては10メートル以上の高所で長時間作業をすることになります。高所が苦手な方には、高所作業は当然向いているとはいえません。
8-2.マイペースに仕事をしたい方
高所作業では1人で作業をすることはありません。ペアやチームを組んで作業をおこなうことになります。
足場を作るために部材を受け渡す際など、チームワークを発揮して息のあった行動を取ることが求められます。そのため、「マイペースで作業をしたい」「1人で黙々と仕事に打ち込みたい」と考えている方には向いていません。
8-3.屋内で仕事をしたい方
高所作業のなかには工場内の天井の点検など屋内で活動できるものもありますが、ほとんどは屋外での仕事です。
屋内で働く事務や営業と違い、夏は暑さ、冬は寒さのなかで仕事をすることになります。空調が効いた屋内での仕事を希望している方は、高所作業には向いていないでしょう。
9.まとめ
高所作業のなかには未経験から働ける求人もあり、資格を取得することでレベルアップも可能です。しかし、向き・不向きがはっきり分かれる仕事でもあり、誰にでもおすすめできるものではありません。
高所作業の仕事を希望するなら、自分が高所でも作業できるかどうかをよく確認してから応募するようにしましょう。
もし高所作業に興味をお持ちであれば、JOBPALの求人をぜひ一度ご覧ください。