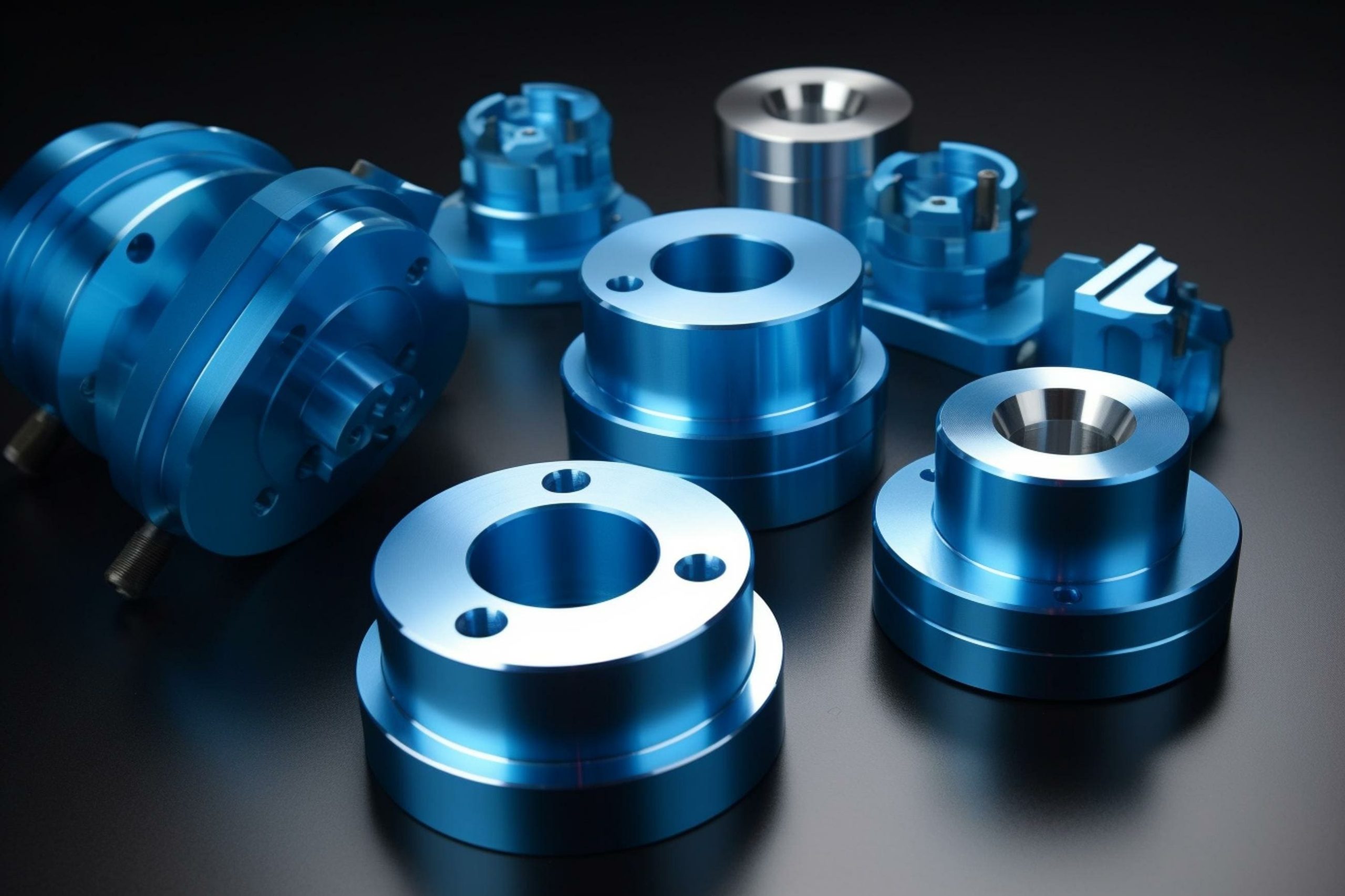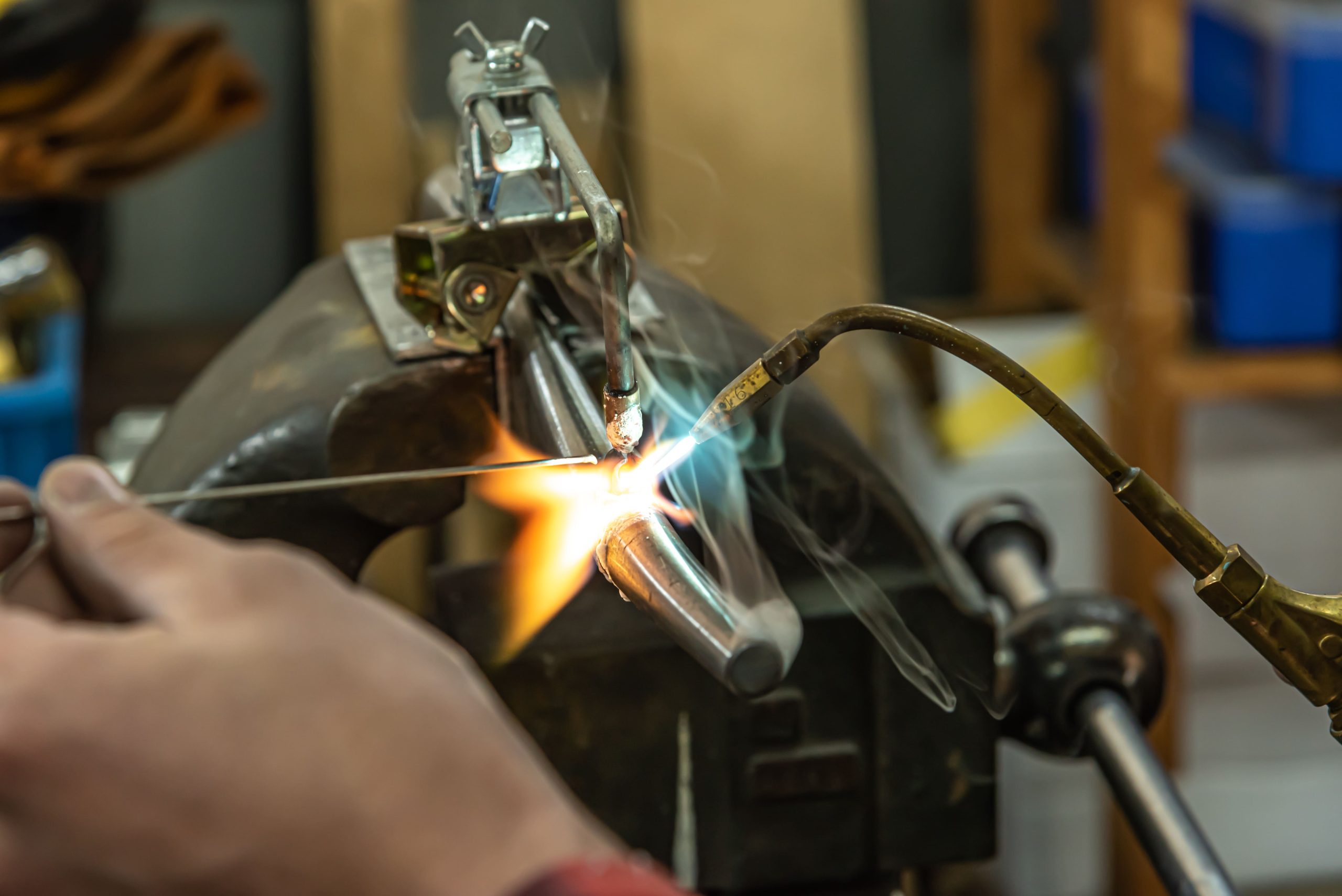倉庫管理主任者とは?仕事内容やメリット、目指し方を解説

※この記事は4分30秒で読めます。
「倉庫管理主任者ってどんな仕事?」
「倉庫管理主任者として働くメリットが知りたい」
など、倉庫管理主任者の仕事に関して興味や疑問を持っている方もいるでしょう。
倉庫管理主任者は、倉庫業を営む企業が倉庫数に応じて配置する必要がある必置資格です。有資格者は高待遇で雇用されることが期待できます。
今回は、倉庫管理主任者の概要、有資格者として働くメリット、資格を取得するための流れなどを解説します。この記事を読めば倉庫管理主任者のことがよくわかり、資格を取得するまでの流れをイメージできるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.倉庫管理主任者とは?
倉庫作業管理主任者とは、倉庫を適切に管理するための知識・能力を持つ認定者のことです。
企業が倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づいた登録を受けるだけでなく、倉庫管理主任者を選任して所定の業務をおこなう必要があります。
倉庫管理主任者となる人物は、一定の業務経験を持っていたり指定の講習を受講したりといった条件を満たす必要があり、そのうえで倉庫の適正管理や火災・労災の防止に努めることになります。
2.倉庫管理主任者の仕事内容
倉庫管理主任者の業務は、「倉庫業法施行規則」第九条の二に定められています。
第九条の二 倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 次に掲げる業務の総括に関すること。 イ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。 ロ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。 ハ 労働災害の防止に関すること。 二 現場従業員の研修に関すること。
- 引用:e-GOV|倉庫業法施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800059
倉庫管理主任者は、倉庫における火災の防止をはじめとした管理をおこなうことが主な仕事です。火災報知器のメンテナンスなどのハード面の管理はもちろん、倉庫における資材の保管や荷役作業(※)といったソフト面での管理も対象に含まれます。
なお、施設管理については倉庫内だけでなく、敷地全体が業務の対象です。加えて労働災害の防止・業務を円滑に進めるための従業員の教育も業務範囲に含まれます。従業員の安全が守られるような作業ルールを定め、従業員教育の場を設けて浸透させていきます。
具体的な業務内容は国土交通省「倉庫管理主任者マニュアル」にも詳しく記載されているので、興味があれば目を通してみてください。
- 参照:国土交通省|倉庫管理主任者マニュアル https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/souko-kanrimanyuaru/manyual.pdf
倉庫管理主任者が働けるのは、倉庫業を営む企業です。基本的に一つの倉庫につき1人の選任が必要であり、複数の倉庫を保有する場合は、倉庫の数に応じた人数の配置が求められます。
ただし、同一の敷地内に存在する複数の倉庫や、道路を挟んで反対側に位置する複数の倉庫などは機能上一体の倉庫としてみなされ、倉庫の数は一つとしてカウントされます。
(※)荷役(にやく)作業……トラックや電車、船、飛行機などに商品を積み込んだり、荷下ろししたりする工程のこと。
3.倉庫管理主任者として働くメリット
倉庫管理主任者は倉庫業を営む企業にとっては絶対に配置が必要な人材であり、有資格者はさまざまな優遇が受けられます。メリットとして考えられるのは、主に以下の2つです。
3-1.資格手当をもらえることがある
倉庫管理主任者は、倉庫業を営むためには配置が必須の人材です。企業は有資格者の給与を高く設定するなど、有資格者が働きやすい環境を整えていることがあります。
企業によって資格手当の金額は異なりますが、月2万円前後の資格手当を受け取ることも可能です。
3-2.転職や就職で有利になる
倉庫業における必置資格である倉庫管理主任者は、倉庫業を営む企業でのニーズが高い資格です。有資格者であれば、書類選考や面接の場で高く評価されるでしょう。
また、倉庫管理主任者の資格を直接利用しない企業でも、資格を取得するために勉強した熱意や努力が認められ、評価アップにつながることもあります。
4.倉庫管理主任者になるには?
倉庫管理主任者は、試験に合格すればすぐに倉庫管理主任者を名乗れる資格ではありません。有資格者として働くためには正しい手順を踏んでいく必要があります。
ここからは、倉庫管理主任者として働くための手順・流れについて解説します。
4-1.倉庫管理主任者に選ばれる必要がある
倉庫管理主任者として働くためには、有資格者の配置義務がある企業に就職することが必要です。
倉庫業者は「実務経験を一定以上有すること」「講習を受けて認定されていること」などの条件を満たした方のなかから選任をおこないます。まずは企業に選任されないと倉庫管理主任者として働くことはできません。
4-1-1.選定要件
倉庫管理主任者として選定されるためには、以下の3つのいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 倉庫管理業務に関して3年以上実務経験がある者
- 倉庫管理業務で指導・監督役として2年以上の実務経験がある者
- 倉庫の管理に関する講習を修了した者
上記のとおり、倉庫管理業務に求められる実務経験は3年以上の実務経験2年以上の指導監督的実務経験のいずれかです。
一方、実務経験がないまたは不足している方でも、講習を受講して修了すれば有資格者として働くことができます。
講習は一般社団法人日本倉庫協会が全国の会場で定期的に開催しており、受講資格は特にありません。受講後の試験もなく、基本的には受講することで資格取得の要件を満たせます。
また、上記の条件の例外として「国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び力を有すると認める者」と認定されれば、有資格者として働くことも可能です。
4-2.講習を受ける
実務経験がない方が倉庫管理主任者に選ばれるためには、講習を修了していることが必要です。
講習は1日で完了しますし、全国各地で実施されるため、受講しやすいといえます。受講料は実施会場ごとに異なりますが、一般の方は1万2千円前後、日本倉庫協会の会員は6,000円前後です。(※2023年6月現在の費用です。)
講習は全4時間45分で、以下のような時間割でおこなわれます。
| 倉庫業法の概要 | 1時間 |
| 倉庫業における労働災害の防止 | 1時間 |
| 倉庫における火災防止 | 1時間 |
| 倉庫管理実務 | 1時間 |
| 自主監査体制の整備 | 45分 |
4-2-1.受講要件
講習の受講について、年齢、学歴、実務経験などの要件は設定されておらず、誰でも受講できます。ただし、以下に該当する方を選任することはできません。
- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録の取り消しを受けてから2年を経過していない者
4-2-2.受講のポイント
倉庫管理主任者の講習には試験がないため、基本的には4時間45分の講習を最後まで受講すれば、その日のうちに修了証を受け取れます。
とはいえ、実務経験に代わる重要な講習です。居眠りをするなどの不真面目な態度で挑まず、最後まで集中して講習に臨むことが大切です。
5.未経験でも倉庫管理主任者を目指せる?
未経験の方でも、倉庫管理主任者を目指すことは可能です。
ただし、大前提として有資格者の選任が必要な職場に就職しなければなりません。倉庫業者として働きながら実務経験の要件を満たしたり、講習を受けたりすることで選定条件を満たせば、企業から選定される可能性があるでしょう。
6.まとめ
倉庫管理主任者は倉庫を持つ企業が法律にしたがって配置する必要がある重要な資格であり、有資格者は転職・就職活動で有利になります。月2万円程度の資格手当を受け取れる企業もあり、無資格のときよりも大幅な年収アップが期待できるでしょう。
資格の難易度は高くなく、実務経験や講習受講の要件を満たせば誰でも有資格者として働けるチャンスがあります。
ぜひ一度、JOBPALの求人一覧から倉庫業の求人を探してみてはいかがでしょうか。