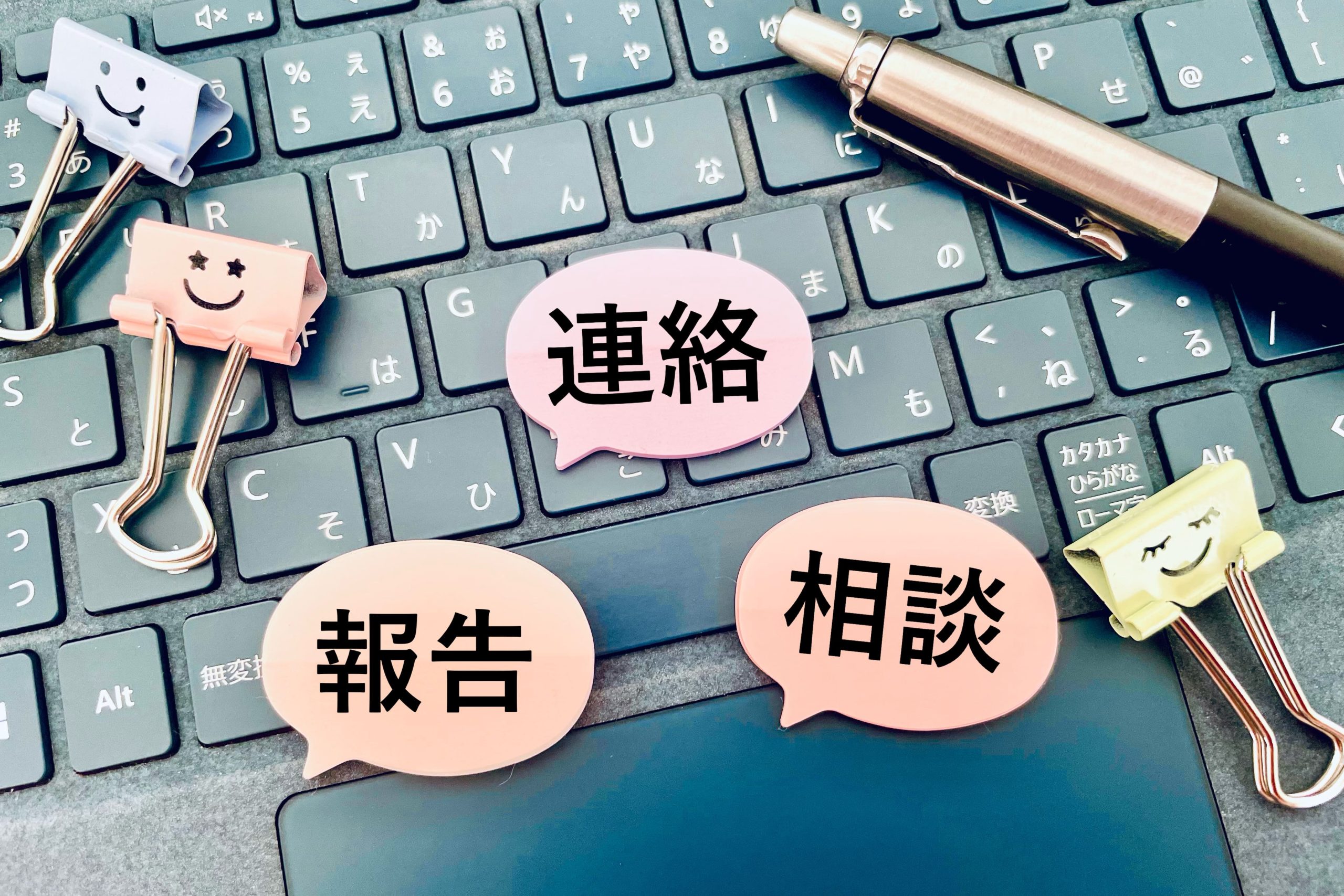仕事に役立つ!メモの取り方の基礎・応用のポイントを解説

※この記事は6分30秒で読めます。
「メモを取ることにはどのようなメリットがあるの?」
「あとから見やすいメモの取り方を知りたい」
など、メモの取り方に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
正しいメモの取り方は、ただ聞いたことを書き写すだけではありません。重要な情報に絞って、あとから見やすいような工夫をしながら書くことが大切です。
今回は、メモを取る目的、メリット、メモの取り方のポイントなどを解説します。この記事を読めば、メモの取り方のことがよくわかり、あとから見返しても見やすいメモを取れるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.仕事に役立つ!メモを取る目的
仕事でメモを取るのは、教わった内容や指示された内容を忘れないようにすることが目的です。
特に新しい仕事に就いた当初は覚えることが山のようにあり、すべてを暗記で覚えることは困難です。しかし、メモを残してあれば、わからないことや忘れてしまったことがあってもメモを見ながらある程度のレベルで仕事をこなすことができます。
また、仕事を覚えたあともメモを取ることは重要です。日々、数多くのタスクを忘れずに同時並行で進めるためには、しっかりとメモを取っておくことが大切です。
メモを取ることは、重要な情報を忘れずに覚えておくための、社会人の基本スキルといえます。
2.メモを取るべきビジネスシーンの例
以下のようなシーンでメモを取ることで、情報を忘れることなく記録しておけます。
- 新しい取引先・顧客の名前を覚えたいとき
- 複雑な情報を整理するとき
- 上司から仕事の指示を受けたとき
- 新しい仕事の作業工程を覚えるとき
- 会議で決まったことを残したいとき
- 顧客の話を聞いているとき
- 注文ごとに納期と製造する順番を整理したいとき
- 研修やセミナーの情報をまとめるとき
- 新しい企画・アイデアを思いついたとき
- 会議の議事録を作成するとき など
これらを自分の頭のなかだけで整理することは難しいでしょう。やるべきことを整理しタスク化するためにも、覚えるべきと感じた情報はすかさずメモを取る習慣を身につけましょう。
また、メモを取ることは単なる作業ではありません。適切なメモを書き残すことでさまざまなメリットが得られます。
3.メモを取ることの4つのメリット
メモを取ることにはどのようなメリットがあるのか、4つのポイントをご紹介します。
3-1.情報を忘れないように記録できる
仕事では、上司からの指示や顧客からの注文・見積依頼など、さまざまな情報が入ってきます。聞くだけで覚えようとすると忘れる可能性があり、忘れると思い出すことができないかもしれません。
しかし、メモを取ることで重要な情報を記録でき、忘れたときもメモを見返すことで思い出せます。重要な指示や依頼をこなすとき、アイデアや学習内容をまとめたいとき、ただ聞いておわりにせずメモを取る癖を身につければ、忘れてしまってミスにつながるような事態を防げるでしょう。
また、メモを取るときは、耳で聞くこと、書いて記録することに加え、読み上げて復唱するといったプロセスを踏むことができ、耳で聞くだけよりも頭のなかに残りやすくなります。
3-2.重要な要点を整理する力が身につく
相手の発言についてメモを取る際、すべての内容をメモするとかえって要点がわかりにくくなります。読み返したときに「どこを読めば良いのか」と迷ってしまうかもしれません。
また、相手の発言よりメモを取るスピードはどうしても遅くなるので、すべて書き残そうとすると後半の発言内容をメモできない可能性もあります。
メモをあとから見返しやすいように、また、相手の発言についていけるようにするためには、要点のみを記録していく必要があります。
そうして繰り返しメモを取ることが、重要なポイントや鍵を握るキーワードに絞って記録する練習になり、効率的に要点をまとめられるようになっていきます。
3-3.問題点や課題点を見つけられる
ただ耳で聞くだけより、言葉に出したり目で追ったりすることで、相手の話の本質がわかりやすくなります。
頭のなかで曖昧に考えていただけではわからなかった問題点や課題について、メモを取っているうちに気付くこともあるでしょう。
メモを取り続ければ、気になることを可視化する癖が身につき、問題を発見する力や解決する力の向上が期待できます。
3-4.相手に安心感を与えられる
上司や同僚、取引先から仕事の指示や依頼があったとき、耳で聞いているだけだと、相手が「本当に聞いているのか」と不安に感じる可能性があります。
しかし、メモを取っている姿を見せることで、相手に「ちゃんと聞いてくれているから忘れずに実行してくれるだろう」という安心感を与えられます。それによって信頼関係の構築もできるでしょう。
4.【基礎編】メモの取り方のポイント
メモを取るといっても、ただ聞いた内容をひたすら書けば良いというわけではありません。情報が多すぎると、メモに書いた内容を読み返しても何が重要かわかりにくくなります。
ここでは、見返すときを想定したメモの取り方の基本をご紹介します。
4-1.タイトル・日付を書く
メモを取るときにやってしまいがちなのが、いきなり本題から書き始めることです。
仕事をしていると1日に何回もメモを取ることになり、日付やタイトルを残していないと、メモを見返してもいつのメモかわからなくなる可能性があります。メモを取り始める際には、冒頭に以下の情報を必ず記録しましょう。
- 何についてのメモなのかがわかるタイトル
- メモをとった日付
この2つの情報を残すことで、いつの指示・会話をメモしたものか、何についてのメモなのかがすぐにわかります。
また、指示や依頼をくれた相手の名前や話を聞いた場所の情報、会議に参加した人の名前などもメモしておけば、見返すときによりスムーズです。
4-2.話しの要点だけを書く
相手が話すスピードに対して、すべての内容を手書きで追いかけるのは非常に困難です。
一言一句メモしても要点がわかりにくいため、話の要点のみをメモにまとめましょう。要点さえ書いてあれば、あとから見返したときに読みやすく、大事な部分がすぐにわかる価値のあるメモになります。
ただし、重要な情報まで削らないように注意が必要です。慣れないうちは要点の前後まで多めに記録しておき、あとから要点のみを書き直すと、ミスなく要点のみに絞ったメモになるでしょう。
4-3.余白を設ける
メモを取る行為は、情報を記録することはもちろん、あとから見返して重要な情報を思い出すことが主な目的です。メモを取るときは、あとから見返したときにわかりやすい取り方を意識しましょう。
例えば、余白がなく文字だけで埋まったメモ帳は、何が書かれているかを読み取るのも非常に大変です。
一文ごとに改行したり段落ごとに隙間を設けたりすることでメモに余白が生まれ、書いてある内容が見やすくなります。あとから新しいアイデアを追記できたり、間違いを二重線で消して書き直せたりもできるでしょう。
4-4.色分けをする
メモを取るときは手持ちのボールペンやシャープペンを使うことになり、基本は黒一色になります。
ただ、黒一色だけだと、どこが要点なのかがわかりにくいかもしれません。余裕があれば、メモの内容に応じて色分けをすると読みやすいでしょう。
例えば以下のように、情報ごとに色分けしておくと、あとから見返したときに要点をすぐ把握できるようになります。
- 黒:通常のメモ
- 赤:特に重要なこと
- 青:自分の意見やアイデア
黒一色のボールペンの他、黒・赤・青の三色のボールペンを常に持ち歩いておくと良いでしょう。黒一色で書いた場合は、あとから蛍光ペンなどでマーカーを引いておくと見やすくなります。
4-5.メモは一冊にまとめる
メモを複数持っていると、同じ議題を違うメモ帳に分けて記録してしまう場合があります。あとから見返したときに重要な情報が別のメモ帳に残っていることに気付かず、大きなミスにつながる可能性もあります。
また、たくさんメモ帳があることで、書いたメモがどのメモ帳にあるか見つけるのに時間がかかる可能性があります。
仕事で持つメモ帳は一冊にしておき、ページ順に情報をまとめるようにすると、重要な情報を別のメモ帳に記録する心配はありません。
メモ帳のすべてのページを使い切ったあとは、表紙に「2024年1月~5月まで」といったようにメモした期間を記録しておき、作業机などに保管しておきましょう。次のメモ帳の表紙には「2024年5月~」と書いておけば、複数のメモ帳があっても時系列で迷うことがなくなります。
5.【応用編】メモの取り方のポイント
基本的なメモの取り方を覚えたあとは、見やすく、かつ要点がわかりやすい書き方を追求していきましょう。ここでは応用編として、より見やすく漏れのないメモの取り方をご紹介します。
5-1.5W1Hを押さえておく
メモの本文を書く際、情報が不足していると、誰の発言なのかわからない、いつまでに対処すれば良いのかわからないといったように、かえって困る可能性もあります。
見返したときに不明点が出ないようにするには、「5W1H」がすべて埋まる書き方になるように工夫しましょう。5W1Hを押さえてメモを取ることで、仕事の指示や依頼を受けた際に必要な情報を漏らさずに記録できます。
5W1Hとは以下のような情報を指します。
- What(何):仕事や依頼の内容は何か
- Why(なぜ):なぜその仕事や依頼を実行する必要があるのか
- Who(誰が):自分が担当するのか、他の社員との連携が必要なのか
- When(いつ):提出期限や出荷納期はいつか
- Where(どこで):仕事をする場所はどこか
- How(どのように):どのように仕事を進めるのが良いのか
5-2.PREP法を活用する
メモを取るときは、5W1Hに加えてPREP法を意識した書き方をすることも重要です。PREP法とは、結論から先に書き、理由と具体例で情報を補完し最後にもう一度結論(まとめ)を書く手法のことです。
PREP法に5W1Hを加えたメモの書き方の例は以下のようになります。
- P=Point(結論):顧客から依頼された新規の製品製造プロジェクトが始まる(What)。製造責任者は製造部長のA。営業担当は二課主任の自分(Who)。
- R=Reason(理由):既存製品は新しい規格に対応しておらず、時勢に合う商品にリニューアルをおこなうため(Why)
- E=Example(具体例):新製品の製造開始時は営業と顧客が立会いのもと、弊社工場でおこなう(Where、How)。新製品は順次取引先に出荷される。初回の出荷納期は3月31日まで(When)
- P=Point(まとめ):既存製品との総入れ替えであり、利益獲得のチャンスになる。顧客からの新規プロジェクトを優先的に進めるように製造部長と連携する
6.要注意!良くないメモの取り方
メモの取り方の基本と応用をご紹介しましたが、メモはただ書けば良いわけではありません。書き方やまとめ方が悪いと、かえって読み返す際に苦労することになります。
メモを取る際には、これからご紹介する「良くないメモの取り方」に該当しないように気をつけましょう。
6-1.字が汚くて読めない
メモはその場でただ書けば良いわけではなく、あとからスムーズに読み返せることも必要です。自分だけが読むメモなら多少字が雑でも読めるかもしれませんが、同僚や後輩に見せる可能性があるなら特にきれいな字で書く必要があります。
字が汚すぎて読めないというのはメモの本来の機能を果たしていません。最低限読める字でメモを取りましょう。字が汚くなってしまったときは、忘れないうちに書き直しておくと、あとから読み返しやすくなります。
6-2.どれが重要なことかわからない
淡々と文字ばかりを書いていると、どこが要点なのかわかりにくくなります。重要な点がわからずに読み取りに時間がかかると、かえって仕事の効率を悪くします。
そのため、メモを取るときは5W1HやPREP法を意識しつつ色分けをするなどして、どこが重要なのか判断しやすい状態にしておきましょう。
色をつける以外に、重要な情報に★や■などのマークをつけるのも有効です。
6-3.メモに必死で話を聞いていない
メモを取るのは、あくまで話の重要な部分を忘れないことが目的です。メモを取る事ばかりに必死になっていると会話のスピードについていけず、重要なことを聞き逃す可能性があります。
話を聞いて重要な用件を漏らさず覚えることが大前提であり、その情報を忘れないための手段がメモであることを覚えておきましょう。
メモを取る際には、重要な情報だけを抜粋して記録する癖をつけたり、必要なら少し会話をストップしてもらったりすることで、重要な情報を聞き漏らしにくくなるでしょう。
7.使いやすいメモ帳やノート選びのコツ
あとから読み返しやすいメモを残すためには、メモを書き留めるノート選びも重要です。ここではメモ取りに使いやすいノートの特徴をご紹介します。
7-1.自分に合うサイズのものを選ぶ
メモを取るノートの大きさは、仕事の仕方や内容で変えると良いでしょう。
例えば、事務など1日の大半を座って過ごす方の場合、大きなノートにメモをとっても問題ありません。大きなノートなら大量の情報を書き込めるため、会議の議事録用にも役立ちます。
一方、製造や営業など外出や立ち仕事がメインの仕事の場合、制服やスーツの胸ポケットにしまえるサイズの小型ノートが望ましいでしょう。
7-2.罫線かあるかどうかで選ぶ
工場で働くオペレーターや営業がメモを取る際は、白紙よりも罫線がついたノートを選ぶことをおすすめします。
罫線がない紙にメモをすると、文章をまっすぐに書くのが難しく、見にくくなってしまう可能性があるためです。罫線があれば横一線で読みやすいメモになり、余白を取る際の目安にも利用できます。
一方、メモのなかに何らかのイラストを描くことが必要な企画職やデザイン職の場合は、イラストが描きやすい罫線なしのノートのほうが向いているでしょう。
7-3.開く向きによって選ぶ
ノートが開く向きは縦開きか横開きかで異なります。立ったまま片手でメモを取る可能性が高い方は、縦開きの小型ノートがページをめくりやすくて便利です。
一方、横開きのノートは片手でメモをしにくいデメリットがある反面、左右のページを同時に見返せることで情報を整理しやすい点がメリットです。
8.パソコンでメモを取る場合
パソコンを持って会議や打ち合わせに参加している際は、パソコンのメモ帳ソフトやWordなどを利用してメモを取ることも可能です。
パソコンで作成すれば字の汚さを気にすることなく、スキャンせずにそのままメールやチャットツールで共有もできます。自分が教える立場になったときや、チームリーダーとしてメンバーに会議の情報を共有したいときなどに役立つでしょう。
ただし、データで保管しているメモは、うっかりミスや手違いで消してしまったり、データがどこにあるかわからなくなってしまったりするリスクもあります。保存場所を明確に決め、時系列や会議の種類ごとに保管場所を明確にしておきましょう。
9.まとめ
仕事では、「上司からの指示と顧客からの依頼と後輩からの問い合わせが同時に来た」というようなマルチタスクが発生する状況も数多くあります。重要な用件を忘れず、優先順位を間違えないためにも、あとから見やすい形でメモを取るように意識しましょう。
メモを取る能力が高ければ効率的に仕事を進められ、新しい職場での活躍の可能性も高まります。転職を検討している方は、ぜひ以下から求人を検索してみてください。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す