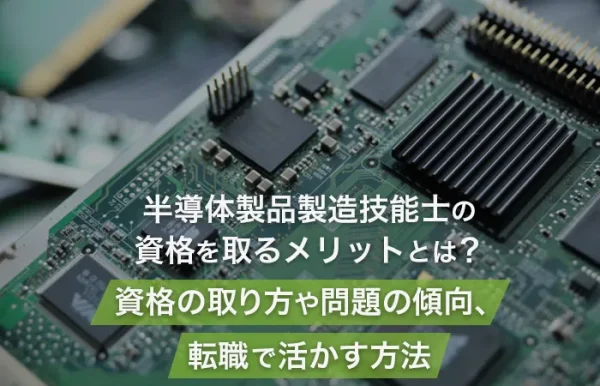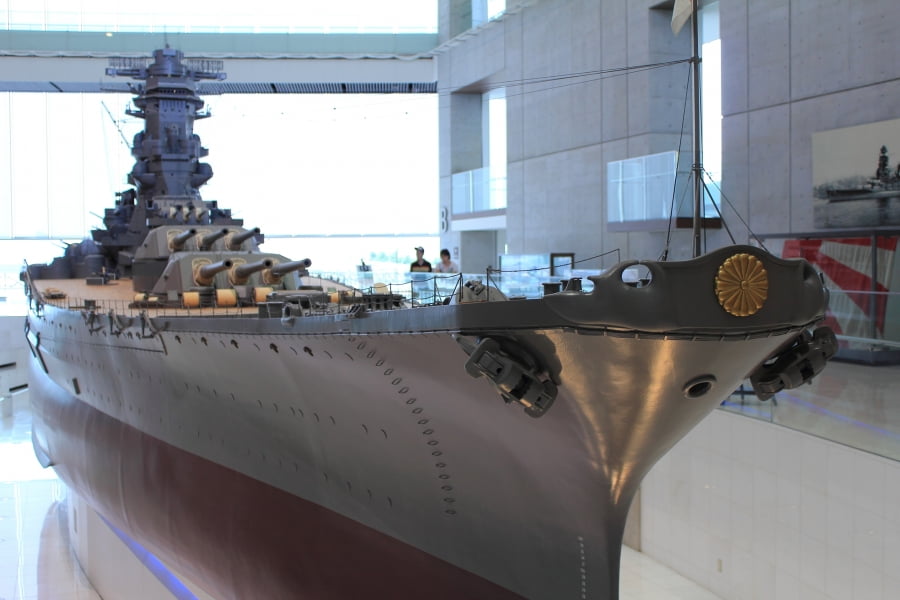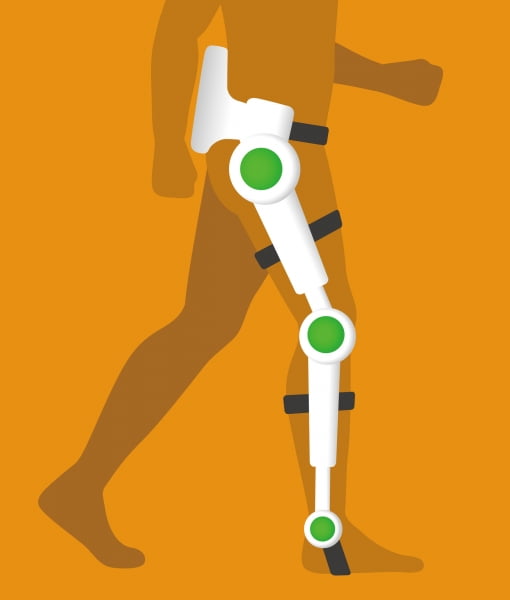品質管理検定(QC検定)とは?難易度や勉強方法を解説

※この記事は6分で読めます。
「品質管理検定ってどのような資格?」
「品質管理検定の難易度が知りたい」
など、品質管理検定に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
品質管理検定は、品質管理に関する知識を体系的に学ぶことができ、実務や就職・転職活動に活かせる資格です。
今回は、品質管理検定の概要、メリットや難易度、勉強方法などを解説します。この記事を読めば品質管理検定のことがよくわかり、取得までに必要なポイントを整理できるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.そもそも品質管理とは?
そもそも品質管理とは、メーカーが作る製品や提供されるサービスの質を一定に保つためにおこなう取り組みのことです。
例えば自動車の部品を作る工場ならば、製品の加工・組立や検査・測定の精度のばらつきを抑え、不良品の発生を防いでいきます。
集団で生産をおこなう製造現場においては、個々の作業内容や意識の差により品質が一定に保てないケースも出てきます。そこで求められるのが、組織的な品質管理のリーダー役を担う“品質管理部”です。
品質管理部では主に、製造時に生じる不良品を減らすための施策を検討・実施します。具体的には、現場で働く作業員の意識や能力を向上させるための取り組みをおこなったり、不良の発生原因を究明して改善策を講じたりしていきます。
以下の記事では、工場の仕事の種類や内容を詳しく解説しています。
2.品質管理検定(QC検定)とは?
品質管理検定とは、品質管理に関する知識をどの程度身に付けているかを測るために役立てられる検定資格です。
QC(クオリティ・コントロール)検定とも呼ばれており、レベルに応じて1〜4級のグレードが用意されています。試験は3月と9月、年2回の実施です。
ものづくりやサービスに関わる職種では、品質管理部での勤務や管理職への昇格条件として、品質管理検定の取得が求められる場合も珍しくありません。そのため、製造現場で給料やキャリアアップを目指している場合はぜひチャレンジしたい検定制度です。
-
参照:品質管理検定(QC検定)とは│日本規格協会 JSA Group Webdesk
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/qc_qc1/
3.品質管理検定(QC検定)を取得するメリット
品質管理検定を取得するメリットは大きく2つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1.年収や転職に良い影響がある
会社が品質管理検定取得に関する資格手当を設けている場合は、年収が上がるメリットが第一に挙げられます。
特に製造業では、品質管理検定の取得を社内教育の一環として取り入れているところも珍しくありません。所属部署や職種によっては、品質管理検定の取得が評価や昇進に良い影響を与えることもあるでしょう。
また転職活動時には、品質管理に関する知識をどれくらい持っているのかを客観的に示す指標としてアピールすることも可能です。
3-2.品質管理の知識が深まる
資格取得を目指して学習を進めることにより、品質管理についての実用的な知識を深められる点も、品質管理検定を受けるメリットの1つです。
品質管理検定は難易度ごとに1級〜4級が用意されており、理解度に合わせて体系的に学習できます。
学んだ品質管理の知識は、サービス業や企画開発など、さまざまな業種でも活用できます。仕事の質や効率をアップさせたい方にもおすすめの資格です。
4.品質管理検定(QC検定)の難易度
品質管理検定は難易度ごとに4つの級が設けられており、入口は広く開かれています。検定を通して品質管理の知識を深めるためには、自身の知識量に合ったグレードを選ぶことが大切です。
4-1.品質管理検定(QC検定)4級
品質管理検定の入口となる4級では、不良品についてどう考えるべきかといった品質管理の基本的な知識や考え方を身に付けられます。
対象はこれから製造現場で働く方や学生が中心となっており、個人で申し込む場合の受験料は3,960円(税込)です。
4級用テキストは主催団体のホームページで無料公開もされているため、気軽に受験しやすいグレードとなっています。
-
参照: 4級テキスト│日本規格協会 JSA Group Webdesk
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/qc_level4/
4-2.品質管理検定(QC検定)3級
3級では、グラフやチェックシートなどの、いわゆるQC7つ道具を用いた品質管理について学びます。
品質管理の基礎知識や実務経験がある方は、3級からの受験を目指しても良いでしょう。
人為的に起きてしまったミスの原因を特定するなど、QC的問題解決ができるようになるため、業種や業態を問わず取得を推奨している企業もあります。
4-3.品質管理検定(QC検定)2級
2級では、品質に関する問題解決においてリーダー的立場となって対処する人材に必要な知識の有無を測ります。また、QC7つ道具や新QC7つ道具を活用した統計的な手法の会得も必要です。
合格率は回によりバラツキがありますが、2013年度以降の実施では20%~40%程度を推移しています。およそ半数が合格できる3級よりも難易度が上がるため、本腰を入れた学習が必要です。
-
参照:品質管理検定センター資料
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/qc/md_4742.pdf
4-4.品質管理検定(QC検定)1級
1級では、解決困難なトラブルが生じた際にどのような手法で解決を目指すのか、具体的な計画の立案と実践ができるスキルを求められます。
品質管理部のリーダーや指導者に就く方の受験が多いといわれています。難易度は非常に高く、受験者数は各回1,000人程度で、合格率は10%を切ることも珍しくありません。
試験内容は1級のみマークシート試験と論述試験に分かれており、マークシート試験で基準以上の点数を獲得したものの論述試験で合格基準に達しなかった場合は準1級合格、両方の合格基準に達すれば1級合格者となります。
-
参照:「準1級」設置に伴う、制度・運営方法の変更の概要│日本規格協会 JSA Group Webdesk
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/qc/md_4759.pdf
-
参照:品質管理検定センター資料
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/qc/md_4742.pdf
5.品質管理検定(QC検定)勉強の方法
ここでは、品質管理検定(QC)検定の勉強方法について解説していきます。
まず手始めに購入したテキストを読みながら問題を解いていく順序で進めます。テキストを最後まで勉強したら過去問にチャレンジして、出題される問題の傾向をつかみましょう。
5-1.品質管理検定(QC)検定4級
4級の試験対策では、品質管理の実践・手法と合わせて、企業活動の基本についても学びます。QC7つ道具や品質管理がどのようなものかを問う内容の出題が中心です。
品質管理検定の公式テキストは、4級に限り検定を主催している日本規格協会がWebで無料公開しています。
また、4級の試験内容はこのテキストから出題されることが明言されています。勉強時間としてはおおよそ50時間程度あれば十分といわれており、1日2時間ずつ勉強すれば約1ヵ月で完了する目安です。
-
参照:合格基準│日本規格協会 JSA Group Webdesk
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/qc_level2/#level4
5-2.品質管理検定(QC)検定3級
級では、QC的なものの見方や考え方、品質の概念を知識として学びます。加えて、データの取り方やまとめ方、QC7つ道具を用いて統計を読み取るスキルも必要です。
まずはテキストを繰り返し読み、専門用語を正しく理解できるようにしましょう。また、公式を暗記して使用する計算問題も出題されるため、過去問に繰り返し取り組むことも大切です。
ちなみに、3級の出題範囲には4級のテキスト内容もふくまれています。3級から受験する方は、4級の内容を学習しておくことも忘れないようにしてください。
5-3.品質管理検定(QC)検定2級
2級では、品質に関するより詳しい知識と、統計を用いた品質管理の手法を学びます。
試験では3級、4級の範囲も含めて出題されるので、取りこぼしのないようにしっかり学習することが大切です。
繰り返し過去問を解くことが主な試験対策となりますが、必要に応じて通信講座を受講する方もいます。苦手分野の特定が困難な方や、独学では理解を深められない方は、受講も積極的に検討してみましょう。
5-4.品質管理検定(QC)検定1級
1級の試験では、2級までの内容をより深く、かつ実践的に理解したうえで、マネジメントやマーケティングに関する知識も求められます。
また、1級の試験では論述もおこなわれます。実例を挙げる際には普段の業務で経験したことが活かせるので、日頃から品質管理の知識や手法を意識しながら働きましょう。
1級は合格率が低めの試験になるので、目標値を高めに設定して学習に取り組むことをおすすめします。
6.品質管理(QC)の資格で就職や転職に活かす方法
製造の現場では、商品の質がそのまま会社の評判につながることも珍しくありません。そのため品質管理の基準は年々厳しくなっており、品質管理のスキルを持つ人材は重宝されています。
品質管理検定の資格を持っていると、品質管理に関する知識をどの程度持っているかを客観的に示すことが可能です。
希望職種や取得級数によっては、就職や転職の際にアピールポイントの1つとして活用できます。品質管理に関する実務経験がある場合は、具体的な事例を挙げて紹介すると良いでしょう。
【アピール時の例文】
私は、社会人になってから身に付けたさまざまな知識を体系的に学び直したいと考え、前職在職中に品質管理検定3級を取得しました。
品質管理の知識を得たことでデータの取得や扱いが以前よりスムーズにできるようになり、効率的かつ効果的な問題解決力が備わったと実感しております。
今後はデータを統計的な手法でも扱えるようになりたいと考えており、品質管理検定2級の取得に向けて勉強中です。
7.まとめ
品質管理検定に関する記載を求人広告や求人サイトで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。品質管理検定を持っていると転職活動時に有利になるだけでなく、即戦力として活躍できるでしょう。
注意力や管理力に自信がある方や、体系的な知識を身に付けたい方は、製造業やサービス業などの現場で役立てられる品質管理検定の取得で仕事の幅を広げてみましょう。
JOBPALでは、品質管理検定の資格を活かせる仕事など、多くの求人情報を掲載しています。ぜひ就職・転職活動にご活用ください。