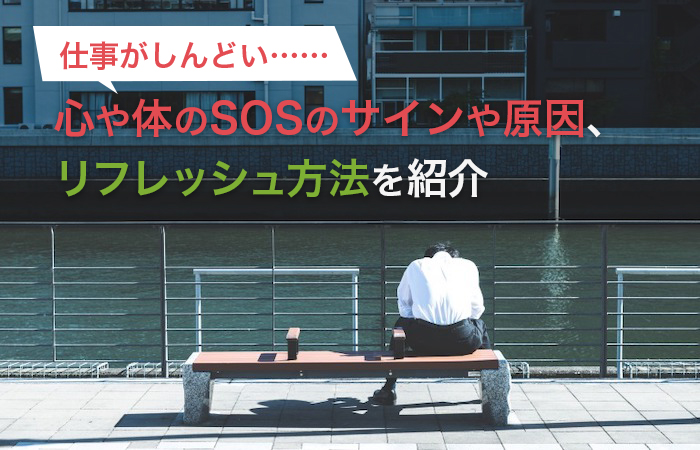早期退職とは?知っておきたいリスクや注意点、よくあるトラブル

※この記事は6分30秒で読めます。
「早期退職ってどんな制度?」
「早期退職するメリットが知りたい」
など、早期退職に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
早期退職は企業が用意した福利厚生の一つで、早期に退職することで割増しの退職金が受け取れたり、就職支援を受けられたりするメリットがあります。
今回は、早期退職の概要、早期退職を決める前に考えておきたいこと、メリット・デメリットなどを解説します。この記事を読めば早期退職のことがよくわかり、納得して早期退職できるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.早期退職制度とは?
早期退職制度は、定年になるよりも前に従業員が会社・組織を退職できる制度です。応募者には退職金の割り増しや再就職支援などの優遇措置があります。何歳から対象になるかなどの明確な決まりはありませんが、40~50代などが対象になるのが一般的です。
なお、整理解雇(いわゆるリストラ)は会社側から解雇されることを指すため、早期退職とは意味合いが異なります。
1-1.早期退職の種類
早期退職には大きく分けて「希望退職制度」「早期退職優遇制度」の2つがあります。
1-1-1.希望退職制度
希望退職は、会社が経営のリスクに備えて早期退職希望者の募集をかける制度のことです。主に、会社の業績が悪いことを理由に人件費を減らすような目的で実施されます。一方的な解雇ではなく従業員の意思が尊重されるのが特徴で、自己都合ではなく会社都合での退職が成立します。
応じた従業員には「退職金の割り増し」「再就職支援」をはじめとした優遇措置が適用されます。
1-1-2.早期退職優遇制度
会社により福利厚生の一環として設けられている制度です。業績の良し悪しに関係なく、一定の年齢に達したときに従業員が自分の判断でキャリアを選択できるようにするなどポジティブな目的で利用されます。
1-2.選択定年制とは?
将来の経営リスクに備えて、企業が早期退職希望者を募る制度のことです。定年退職の前に労働者側の意思で定年のタイミングを決めることができます。
従業員の平均年齢が上がっていくなかで若返りを図るなどの目的があり、該当する年齢に達した段階で退職を選ぶと、退職金額について優遇措置が受けられるのが一般的です。なお、選択定年制による退職は自己都合の退職になる点に注意が必要です。
2.会社で早期退職制度がはじまったら考えるべきこと
会社で早期退職制度が始まったとしても、「仕事は辛いし、割増しで退職金をもらえるなら辞めてしまおう」と短絡的に考えるのはリスクが大きいのでおすすめしません。もし早期退職を申し込むなら、以下のようなことを考えておきましょう。
- 退職金を含めて貯金が十分にあるかを確認する
- 退職したらどうするかを頭に入れて動く
- 自分の市場価値を知っておく
- 家族やパートナーにも話しておく
早期退職をすると退職金は多めにもらえるかもしれませんが、月給を得ることはできなくなり、再就職するまで固定収入がなくなります。日々の生活に支障が出ないよう、自身の貯金額はしっかりと確認しておきましょう。
退職したら「いつまでに再就職を目指すのか」「どんな業界で働きたいか」「年収はどれくらいになりそうか」といった内容を考えましょう。貯金で生活できているうちに内定を受け取れるようなスケジュールを考えておかないと、無職のうちに貯金が底を突くということも考えられます。
また、早期退職後に自分に合う求人を見つけるためには、自身の市場価値を知っておくことも大切です。市場価値を知るには、転職サイトやエージェントに登録して案件を紹介してもらい、どのような案件が紹介されるかで確かめる方法があります。
自分にマッチした求人が紹介されるなら、早期退職しても比較的早くに再就職できる可能性があるかもしれません。逆に、希望する案件がまったく紹介されない場合は市場から注目されていないことを意味しており、早期退職は慎重に考えるべきです。
また、早期退職について家族の同意を得ておくことも重要となります。相談もなく早期退職すると、一時的には家族が退職金という利益を得ることになりますが、「なぜ一言も相談がなかったのか」などと問い詰められたり、信頼関係にひびが入ったりすることも考えられます。固定収入がない間は家族に迷惑をかけることも考え、必ず事前に相談しましょう。
JOBPALでは気軽に転職相談ができますので、ぜひご活用ください。
3.早期退職のメリット
早期退職にはメリット・デメリットの両方があります。ここでは早期退職をすることのメリットをご紹介します。
3-1.再就職支援制度を活用できる
企業によっては、早期退職をした場合に福利厚生の一環として再就職支援制度を活用できる場合があります。
再就職支援制度は、次のキャリアをスムーズに始められるように再就職のあっせんをしてくれる制度のことです。大企業ではグループ系列の別企業を紹介してくれることもあります。
3-2.会社都合の退職になる
希望退職制度の場合は自己都合退職にならず、会社都合での退職という扱いになります。失業給付の給付制限期間がなく、退職してすぐに失業給付を受け取ることが可能です。
所定給付日数は年齢と被保険者期間(社員であった期間)によって異なり、具体的には以下のとおりとなります。
| 被保険者の期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
| 区分 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 130日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
-
参照:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
なお、選択定年制度を選ぶと「自己都合退職」になり、3ヵ月の待期期間が発生します。給付日数が短くなる場合があることも注意が必要です。詳しくは下記でご覧いただけます。
3-3.退職金が割増になる場合もある
早期退職を導入している企業のなかには、割増退職金を支給する企業もあります。増額金額の計算方法は企業によって異なりますが、代表的な考え方は以下のとおりです。
- 全員が一律、同額で設定
- 年齢や勤続年数に合わせて増額
- 定年まで勤務した場合の金額が支給される
3-4.時間に余裕ができる
早期退職に応じると固定の収入はなくなりますが、時間に余裕ができるメリットがあります。次の仕事のための資格取得や勉強、ゆっくり羽を伸ばすなど、忙しくてできなかったことができるでしょう。
また、セカンドキャリアに向かう場合、時間を使って準備をしっかりおこなえるのもメリットです。例えば、フリーランスとして独立したい場合は綿密な計画と準備が欠かせませんが、早期退職すれば会社との両立が必要なくなり、独立に向けて時間をフル活用して準備を進めることができるでしょう。
3-5.人間関係の悩みが減る
どこの会社に行っても、人間関係で悩むことは多かれ少なかれあります。しかし、早期退職してリタイア生活をすることになった場合、職場の人間関係のストレスや悩みが減ることは確実です。そうした悩みを抱えているなら、早期退職して一息ついてから次の身の振り方を考えてみるのも有効な方法です。
4.早期退職のリスク
早期退職には前述のようなメリットがある一方、デメリットやリスクがあることも覚えておきましょう。
4-1.思ったよりも退職金がもらえないこともある
「退職金が割増しになるからお得」と短絡的に判断しないほうが賢明です。割増されたものの、想定よりも割増率が少なかったというケースも考えられます。
このリスクを回避するには、まず自分がいくらの退職金を受け取れるのか明確になるように計算することが重要です。金額に納得してから早期退職に申し込めば、あとから「退職金が少なかった…」と悩むこともなくなるでしょう。
計算してみて退職金が思ったより少ないことが判明しても早期退職の気持ちが揺るがないなら、生活資金の準備を進めましょう。退職金以外の収入源を見つけるなど、早期退職を見越して早めのうちから貯金をしておくことも重要です。
4-2.転職先が決まりにくい場合がある
「いよいよセカンドキャリアにチャレンジ…」と思っていたのに、なかなか転職先が決まらないケースもあります。
特に40代~50代以上になると、20代~30代のときと比較して転職難易度が上がってしまう傾向にあります。40代以降は新しい環境に染まりにくいうえ、管理職として即戦力が求められることから、企業としても採用に慎重になるのが一般的です。
結果的に条件を譲歩して再就職先を探すことになり、求めていたキャリアで働けない可能性もあります。
4-3.社宅が住まいの場合は引き払う必要がある
社宅に住んでいた場合は、退職と同時に引き払う必要があります。家賃補助を受けていた人も同様で、早期退職後は当然ながら家賃補助を受けることができません。
社宅を利用していた人は、早期退職する日が決まった段階で次の住まいを探しておきましょう。今まで家賃補助を受けていた人は、家賃補助なしでどれくらい生活できる貯金があるのかを計算してから早期退職に応募するのが鉄則です。
4-4.年金が減ってしまう可能性がある
定年前に退職することで、将来的に受け取れる年金額が減ってしまう可能性があります。会社に勤めている人は厚生年金に加入しており、将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることになりますが、厚生年金は加入している期間や給与額によって将来の支給額が変わる仕組みです。
早期退職のあと、再就職までに時間がかかると加入期間が短くなり、将来の年金額に影響します。転職できても前職より給料が下がれば同様です。退職金の割り増し分も年金の減額で帳消し、あるいは損になってしまうことも考えられます。
4-5.クレジットカードやローンの審査に通りにくくなる
ローンやクレジットカードに申し込む予定がある場合、早期退職してしまうと不利になります。カードローンやクレジットカードの申し込み条件には「安定した収入」があることが定められており、無職の人は審査を通過することができません。
また、審査される項目には「年収」「勤続年数」などもあります。再就職したとしても、前職より年収が下がったり勤続年数が短くなったりすることで審査結果に影響が出るため注意が必要です。
5.早期退職でよくあるトラブル
早期退職をすると決めたあと、すんなりと会社に認められれば良いのですが、そうとは限らない場合もあるようです。ここでは早期退職でよくあるトラブルの例を3つご紹介します。
5-1.早期退職の不認定
早期退職を希望しているのに認めてもらえないケースがあります。これは違法にはならないため、会社から承認されるまで何度も希望を出し続けなければいけません。
5-2.早期退職の強要
会社や上司から早期退職を強要されるケースもあるようです。しかし、単に退職を促されただけでは退職する必要はなく、納得できない場合は応なくても問題ありません。
5-3.割増退職金の不払い
早期退職優遇制度がある会社なのに、割増退職金が支払われないケースもあります。この場合は速やかに「なぜ割増退職金が受け取れないのか」の理由を確認しましょう。規定があるのに支払われない場合は違法であり、弁護士に相談すべきです。
6.早期退職を希望するときの注意点
「割増退職金が出る」という理由だけで、深く考えずに早期退職に応じる人もいるかもしれません。しかし、割増退職金はあくまで一時的なお金に過ぎないため、今後の人生を考えて新たな収入源を考えておく必要があります。
早期退職によって得られるのは「退職金」「割り増し分の退職金」ですが、前述のとおり、早期退職によって「将来の年金額」が減額されたり「社宅や家賃補助」などがなくなったりすることも考えられます。そうすると固定収入がなくなるため、無職の期間が長いと割増しで受け取れる分も簡単に使い切ってしまうでしょう。
早期退職でもらえるお金ともらえなくなるお金を天秤にかけつつ、他のメリット・デメリットも併せて考えながら、本当に早期退職が必要かどうかを判断しましょう。
7.まとめ
早期退職をすると、割り増しの退職金を受け取れたり、再就職先を斡旋してもらえたり、人によっては人間関係から解放されて羽を伸ばすこともできます。
ただし、「再就職がうまくいかないかもしれない」「年金額が減少する可能性がある」などのデメリットもあるため、早期退職に応じるかどうかは慎重に判断しましょう。
早期退職すると決めたら、新しい就職先を決めるのが当面の目標となります。JOBPALではさまざまな新着求人を掲載していますので、ぜひ再就職先を探す際の参考にしてください。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す