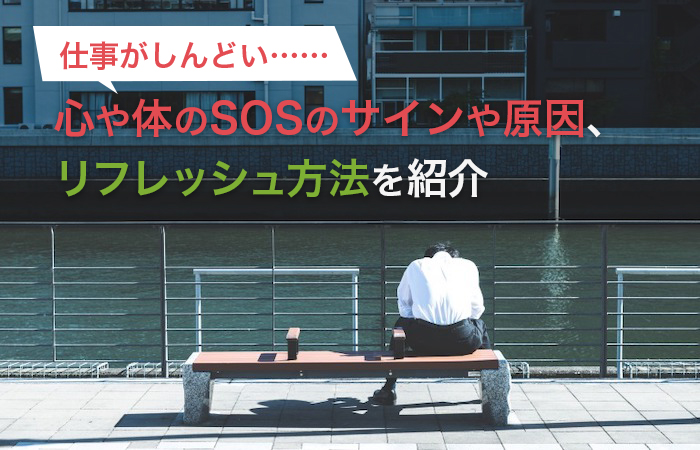仕事が多すぎる!キャパオーバーになってしまう原因と対処法

※この記事は5分30秒で読めます。
「仕事が多すぎて身体がもたない」
「仕事をやってもやっても終わらない」
など、仕事が多すぎることに悩んでいる方もいるでしょう。
仕事で最大限のパフォーマンスを発揮するためには、ある程度の余裕も必要です。キャパオーバーの量の仕事をしていると、どんどんストレスも溜まってくるでしょう。
今回は、仕事が多すぎると悩む主な原因や対処法、無理し続けることの悪影響などを解説します。この記事を読むことで、仕事が多すぎるといった悩みから抜け出す一つのきっかけを見つけられるかもしれません。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.仕事が多すぎると悩んでいる方は多い
今、日本では長時間労働が社会問題になっています。そんななかでキャパオーバーに陥っているのは、仕事を始めたばかりの若い世代だけではありません。
キャパオーバーで苦しんでいる方は管理職など、ベテランと言えるような年代にも多くいます。残業や休日出勤が日常化している、帰宅後に自宅で仕事をするといった現状が、事実としてあるのです。
残業が日常化し、キャパオーバーになってしまう原因について、この記事で確認していきましょう。
2.仕事が多すぎてキャパオーバーになる原因
仕事が多すぎてキャパオーバーになる原因には、主に以下のものが関係しています。
- できるからこそ多くの仕事を任される
- ミスを引きずって自信を失ったり慎重になる
- 睡眠・休息不足に陥っている
- 上司のパワハラが影響している
- そもそも自分に仕事内容が合っていない
- 心身的に余裕がない状態になっている
- 仕事を頼まれたら断れない
それぞれの原因についてお伝えします。
2-1.できるからこそ多くの仕事を任される
会社としては、仕事ができる有能な社員に多くの仕事を任せたいと考えることは想像できると思います。
周りの方と仕事量を比較してみてください。多くの仕事を抱えているわけではなく、余裕がありそうな方もいるのではないでしょうか。
あなただけ仕事が多いということは、それだけ信頼されていると考えられます。
信頼されていることは決して悪い気分ではありませんが、それでキャパオーバーになってしまうようなら仕事を減らしてもらったほうが良いかもしれません。
2-2.ミスを引きずって自信を失ったり慎重になる
仕事量が多いと一つひとつの作業が雑になったり、集中力が維持できなかったりしてミスをしがちです。
そしてミスをしたとき、怒られたことをきっかけに自信を無くし、仕事に影響を与えてしまうこともあるでしょう。
例えば、同じミスをしないよう慎重になりすぎて、スピードが落ちてしまうなどのケースがあります。ミスをしないように慎重になるのはよいことですが、時間がかかり過ぎるのは仕事の効率が悪くなります。
そもそも仕事量が多いことでミスが発生したのなら、仕事量を減らしてもらい、ミスが起こらないような状況を作るべきです。
2-3.睡眠・休息不足に陥っている
残業や休日出勤が続くと、自宅で過ごす時間が減り、日常生活に支障を及ぼします。
なかでも多いのは、睡眠不足に陥る方です。帰宅が遅くなるとそれだけ食事や入浴も後ろ倒しになり、睡眠時間が削られてしまうでしょう。
睡眠不足は、やる気や思考力の低下に影響し、仕事のパフォーマンスを悪化させるため注意が必要です。
2-4.上司のパワハラが影響している
キャパオーバーになる原因には、上司のパワハラが関係しているケースもあります。
具体的には、明確な理由がなく自分だけに異常な量の仕事や、絶対に期限が間に合わないタスクなどを振られたら、パワハラの可能性も考えられるでしょう。
心当たりがある場合は、心身が疲弊する前に人事や相談窓口などに相談してみてください。改善が望めないようであれば、会社を辞めることも一つの選択肢になるかもしれません。
2-5.そもそも自分に仕事内容が合っていない
今の仕事が自分自身の適正に合っていないと、作業効率が悪くなり、仕事が溜まっていく一方です。
人には得意・不得意があるので、自分の適職を考え、必要に応じて職種の変更や部署移動、転職を検討しましょう。
2-6.心身的に余裕がない状態になっている
転職後や新卒の方に多いのは、覚えることが多く、体力的にも精神的にも余裕がなくなっているケースです。
余裕がない状態になってしまうと、効率よく仕事をこなしていくことができないため、仕事がどんどん溜まり、結果的にキャパオーバーになってしまいます。
無理をし続けると、体調を崩してしまう可能性もあるでしょう。
2-7.仕事を頼まれたら断れない
仕事を頼まれると断れないタイプの方は、現状のタスクで精一杯なのにも関わらず頼まれた仕事を引き受けてしまい、キャパオーバーになりやすいです。
また、そのような方に対しては周りの方も気軽に仕事をお願いしてしまい、なかなかキャパオーバーの状態が改善されません。
一人で抱えられるタスクには限界があります。限界を超えた量のタスクを引き受けると、作業効率の悪化や重大なミスなどにつながる可能性も考えられるため、ときには断る勇気も必要です。
3.仕事が多すぎてキャパオーバーになった際の対処法
仕事が多すぎてキャパオーバーになってしまったときは、以下の対処法をお試しください。
- 同僚や部下に仕事を割り振る
- 上司に相談して調整してもらう
- 業務の効率化を図る
- 一つのタスクにかける時間を調整する
- 仕事を断る勇気を持つ
- 自分の適職を探す
自分に合う対処法を探してみましょう。
3-1.同僚や部下に仕事を割り振る
余裕のある同僚や部下がいる場合は、タスクを割り振り自分の仕事量を調整しましょう。人に任せても問題ないタスクがないか、チェックしてみてください。
しかし、会社によっては常に人材不足で、代わりにタスクを任せられる相手がいない場合も考えられます。その場合は、他の対処法を試してみましょう。
3-2.上司に相談して調整してもらう
上司に自分の仕事量が多く余裕がないこと、今の自分がおこなっている仕事の進め方などを相談してみましょう。
まずは、効率化による改善ができないかの助言をもらい、それでも解決が難しい場合は仕事量を調整をしてもらうことで、キャパオーバーになることを未然に防ぎます。
3-3.業務の効率化を図る
メールの返信やExcel作業など、単純作業に時間がかかっているようであれば、自動化ツールを導入するなどして業務の効率化を図りましょう。
そのほかにも時間がかかっている業務は、すべて見直しをして、効率化できる部分を見つけることで、キャパオーバーになることを防げる可能性があります。
自分で効率化の方法を見つけられないときは、上司や先輩から資料やノウハウを共有してもらい、参考にすると良いでしょう。
3-4.一つのタスクにかける時間を調整する
仕事を終えるのが早いことから多くの業務を振られてしまう方は、一つのタスクに費やす時間を多めにとって、振られる仕事量を調整しましょう。
各タスクの質を高めるためにも、本当に必要な時間をかけて取り組むことは大切です。
仕事を終えるのが遅いことから仕事が溜まってしまう方は、100%の完成度を目指すのではなく、スピード重視で作業をしてみましょう。
一つのタスクにかけられる時間を計算し、あらかじめ予定を組んでおくと、どのようなタスクでつまづいているのかが明確になります。
3-5.仕事を断る勇気を持つ
仕事が多くキャパオーバーしそうな場合は、他の仕事を頼まれても勇気を持って断ることが大切です。
現時点で抱えている仕事で精いっぱいであることをきちんと伝えれば、相手も理解してくれるはずです。
無理に引き受けると、「期限に間に合わない」「ミスがある」など、かえって迷惑をかける可能性があります。
3-6.自分の適職を探す
人には向き・不向きがあり、今の仕事が向いていないことから、キャパオーバーを引き起こしているケースも考えられます。
今の仕事が適職ではないと感じて、「やめたい」「つらい」と悩んでいるなら、転職することも検討しましょう。
前向きな気持ちでいられない状況で働きつづけると、身体的にも精神的にもつらい状況が続いてしまいます。無理しすぎるのは良くないため、より自分に合った仕事を一度探してみてください。
4.仕事が多すぎる状態が続いたときの悪影響
仕事が多すぎる状態が続くと、以下のような悪影響が及ぶのでご注意ください。
- ストレスを溜めてしまう
- 自分の時間を確保できない
- 仕事のモチベーションが下がる
- 自己管理ができないと思われる
各悪影響について知っておきましょう。
4-1.ストレスを溜めてしまう
仕事が多すぎると、残業で十分な睡眠時間が確保できない、食事はいつもコンビニ弁当で済ませてしまう、長時間座りっぱなしで運動不足になるなど、日常生活にさまざまな支障が出ます。
こうした生活の乱れは、ストレスにつながります。乱れた生活が長期間続くと、やがて心が限界を迎え、精神的な病気にかかってしまう危険性があります。また、肩こりや腰痛などを身体の不調が出てくる方も多いでしょう。
4-2.自分の時間を確保できない
キャパオーバーになっている方の多くは、帰宅後や休日にも仕事をしています。
ノートパソコンやタブレットなどが普及した現代では、いつでもどこでも仕事ができるようになっています。言い換えれば、休みなく仕事ができるようになってしまったということです。
会社にいる時間で仕事が終わるよう仕事量を調節するのではなく、日々自宅に帰ってからも仕事をするようになってしまっている方もいるでしょう。
自宅に仕事を持ち帰ってしまうと、自分の時間をなかなか確保しにくくなります。
それだけではなく、友人や家族と過ごす時間も仕事のことを考えてしまったり、日曜日の夜になると翌日の仕事のことを考えて憂鬱になったりと、プライベートを楽しめないこともあります。
4-3.仕事のモチベーションが下がる
休日まで仕事をしている、あるいは仕事のことを考えていると、休みの日と仕事の日のメリハリがつかなくなります。
そのような生活を続けることで心身に疲労が溜まり、仕事に対するモチベーションが低下するケースも少なくありません。
休日には、仕事で溜まった疲労を回復させる時間としての役割があります。「休むことも仕事の一つ」とも言うように、休みの日には仕事のことを忘れ、心身の疲労回復に努めることが大切です。
4-4.自己管理ができないと思われる
昔と違い、今は「仕事ができない・遅いから残業している」と考えられるようになっています。
仕事を多く抱えて残業が日常化することで、会社から「仕事の管理ができない社員」と思われてしまう可能性があります。
このようなマイナスな印象は、昇給や昇進を妨げてしまうケースがあるため、仕事量を調整して、できる限り避けたいところです。
5.仕事が多すぎて自分の限界を迎える前に
仕事が多すぎると、上記でお伝えしたように心身の健康をはじめ、仕事や日常生活にさまざまな悪影響が出る可能性が高いです。
そのため、仕事が多すぎてキャパオーバーを迎えそうだと感じたら、早めに対処することが大切になります。
通常であれば上司や先輩に相談したり、同僚や部下に仕事を手伝ってもらったりすることで解決できますが、社内の人材不足によるしわ寄せが生じていれば難しいかもしれません。
今の会社で対処することが難しい場合、転職するのも選択肢の一つです。
そもそも今の仕事が自分に合っていないことから、キャパオーバーを迎えている可能性も考えられるため、本当に自分に合う仕事を探してみてください。
自分に合う仕事が見つかれば、今よりも余裕を持って仕事に取り組むことができ、プライベートも楽しめることでしょう。
転職先を探すならぜひJOBPALの求人情報をご覧ください。キャリアパートナーとの面談も受け付けているので、ご相談いただくとあなたにぴったりの求人情報をご紹介します。
6.まとめ
仕事が多すぎてキャパオーバーになる原因はさまざまです。
頼まれたら断れないといった性格が災いしているケースや、優秀だからこそ仕事を任されてしまうケース、今の仕事が合わないことから効率が悪くなっているケースなどがあります。
キャパオーバーの仕事を無理にこなすことは、心身の不調や重大なミスなどにつながり、結果的に会社に迷惑をかける可能性さえ考えられます。
仕事が多すぎることに悩んでいるなら、早めの対処を心がけましょう。
「今の仕事が合わない」「つらい」などの理由で転職を検討している方は、まずはJOBPALまでご相談ください。豊富な条件・求人情報から、あなたの希望にマッチするものをご案内します。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す