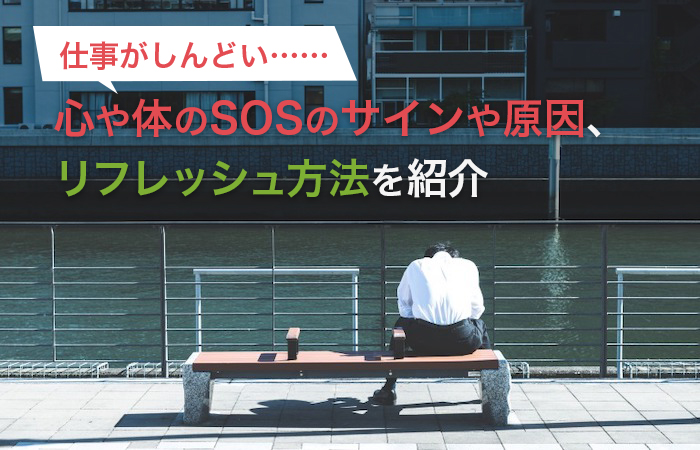電話応対の苦手意識を克服したい!方法や基本的な電話応対の流れを解説

※この記事は6分30秒で読めます。
「電話応対が苦手だけど克服できる?」
「電話応対が苦手な人の特徴や対処法が知りたい」
など、電話応対の苦手さを克服する方法に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
電話応対は声のみでコミュニケーションを取る必要があることから苦手意識を持つ方も多いですが、何度も電話を取ることで徐々に慣れていけます。
今回は、電話応対が苦手な方が増えていることや苦手な理由、克服する方法などを解説します。この記事を読めば、苦手な電話応対を克服する方法がよくわかり、慣れるきっかけをつかめます。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.電話応対が苦手な人が増えている
現代のビジネスのやりとりにはEメールやチャットツールが欠かせませんが、電話もなくてはならないツールです。
特に営業や事務職などの座り仕事では、取引先とのやり取りで電話を使用するケースが多々あります。しかし、電話応対に対して苦手意識をもつ方は少なくないのではないでしょうか。
株式会社ソフツーが公表した「電話業務に関する実態調査」では、全体の約6割、20代~30代に限っては7割以上が電話に苦手意識を感じていることがわかっています。
-
参照:若者世代は7割以上が「電話恐怖症」に!?ソフツー「電話業務に関する実態調査」を発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000028096.html
若い方ほど電話応対に苦手意識があるのは、電話以外の連絡手段としてLINEなどのコミュニケーションツールやSNSが発達しており、音声通話の機会が減っているからと考えられます。
電話が苦手な方は「自分だけが苦手なのだろうか」と思ってしまうかもしれませんが、上記の数字が示すとおり、多くの方が電話に苦手意識を持っています。過剰に不安になる必要はありません。前向きに対策を考えていきましょう。
2.電話応対が苦手な理由とは?
電話応対が苦手な理由は人によってさまざまですが、主な理由として考えられるのは以下の5つです。
2-1.緊張して言葉が出なくなる
電話応対を苦手に感じる大きな原因として、緊張が挙げられます。
実際に会って話をする相手は親しい間柄の方やすでに会ったことがある方が多いですが、電話の場合はまったく知らない方と話す可能性も大いにあります。重要な取引先の役員などからの電話を受ける可能性もあり、「失礼な対応はできない」と緊張してしまいがちです。
また、特に入社したばかりの頃は、取引先の担当者の名前がわからない、聞き取れないなどの理由で余計に緊張してしまうこともあります。
2-2.相手の表情が見えないから怖い
電話は実際に会って話すのと違い、音声から相手の感情や態度などを連想する必要があります。
そのため、相手の声色から「不機嫌なのではないか」と考えてしまい、うまく話せないという方もいるようです。
2-3.話したことを忘れてしまう
自分が担当していない顧客や取引先以外からの電話で担当者が席を外していた場合、相手の用件をメモにまとめておくことも必要になります。
このとき、うまく聞き取れなかったり聞き取り漏らして、何を話したか思い出せなくなってしまったりすることがあります。このような失敗をひきずってしまい、電話に苦手意識を感じてしまう方もいるでしょう。
2-4.電話中の周りの視線が怖い
ビジネスの電話では、上司や同僚と一緒に仕事をしている空間で通話することになります。
その際、「失言をしているのではないか」「言葉遣いがおかしかったのではないか」などと周囲の視線が気になり、苦手意識が生まれる原因になることもあるでしょう。
2-5.質問されたら答えられる自信がない
電話はメールとは違い、緊急性の高い質問をされるケースもよくあります。
メールならしっかり下調べや確認をしたうえで回答できますが、電話では先方の問い合わせについてその場で回答したり、詳しい担当者に迅速につないだりする必要があります。
また、すぐに答えが伝えられないような質問でも、何らかのリアクションをして顧客の要望に応えることが必要になります。しかし、電話や仕事に慣れていないと臨機応変な受け答えができず、電話自体が苦手になってしまうことも考えられます。
3.電話応対の苦手意識は克服できる?
今は電話応対を苦手意識に感じている方でも、努力や頑張り次第で克服することは十分に可能です。
電話応対に苦手意識を持つ方の特徴として、電話に慣れていないことや、過去の失敗体験を引きずっていることが関係しているケースがよくあります。
しかし、不慣れなことでも何となく苦手に感じているくらいであれば、数をこなすうちに自然と慣れて苦手意識をなくせる可能性があります。何度も電話応対を続けていくうちに成功体験が増え、過去の失敗のトラウマを克服することもできるでしょう。
ただし、自身の性格や適性によっては、どうしても電話応対がストレスになってしまうことも考えられます。どうしても苦手に感じる気持ちが克服できない場合は、電話応対が必要ない部署への配置転換や転職といった形で電話から離れることも検討したほうが良いでしょう。
例えば、工場の機械オペレーターの場合は社外の方と電話で話す機会はほとんどなく、黙々と作業に集中しやすい仕事です。
4.電話応対の苦手意識を克服する方法
ここからは、電話応対に苦手意識を持っている方が苦手意識を克服するために実践したい5つの方法をご紹介します。
4-1.基本的な電話応対の流れを覚える
まずは、電話をかけたときと受けたときのそれぞれの基本的な流れを知っておくことをおすすめします。
電話をかけたときの基本的な流れは以下のとおりです。
- 会社名と自分の名前を名乗る
- 「いつもお世話になっております」とあいさつをする
- 先方の担当者の名前を伝え、電話を代わってもらう
- 用件を結論から簡潔に話す
- 担当者が不在で伝言を頼むときも簡潔に話す
- 静かに受話器を置く
自分から電話をかける際は、すでに見知った担当者との話になることも多く、電話を受ける際と比べてさほど緊張することはないでしょう。用件は簡潔にし、結論から話すようにすると相手に伝わりやすくなります。
また、相手方の担当者が不在で伝言を依頼する際、内容が複雑な場合は「メモをご用意ください」などの気遣いもあると良いでしょう。
続いて、電話を受けたときの基本的な流れは以下のとおりです。
- 電話が鳴ったら3コール以内に電話に出る
- 会社名と自分の名前を名乗る
- 相手の名前と内容を復唱してメモを取る
- 電話を保留して担当者につなぐ
- 不在の場合は、その旨と折り返すことを伝える
- 電話を切ってから受話器を置く
電話を受ける際は、3コール以内に出ることが一般的なマナーです。それよりも時間が経過してから受話器を取った場合は「大変お待たせしました」などとつけ加えると良いでしょう。
ただし、会社によっては「1コール目から出る」とルール化している場合もあります。
電話を受けた際は、相手の名前と会社名に間違いがないように、メモを取りましょう。保留して担当者につなげれば電話応対は終了ですが、担当者が不在の場合はその旨を先方に伝えて担当者から折り返させる旨を伝えます。
先方が電話をかけた目的やかかってきた時間などはメモに残し、担当者の机に置いておきましょう。
なお、電話を切る際はかけたほうから切るのがマナーです。電話を受けた場合は、相手が受話器を置いたことを確認してから電話を切りましょう。
こうした基本的な応対の流れが理解できていれば、焦ったり悩んだりせずにスムーズに応対できるはずです。
以下の記事では、電話応対のマナーをより詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
4-2.マニュアルがあれば読み込んで覚える
会社によっては社内用の電話応対マニュアルがまとまっている場合があります。
電話応対のマニュアルが用意されている場合は、内容をしっかり読んでおきましょう。マニュアルに沿った対応がしっかりできていれば周囲の視線も気にならず、落ち着いて応対できるはずです。
また、自分用に電話応対のマニュアルを作ることも対策としておすすめです。各取引先の重要人物の応対の仕方、正しい言葉遣い、シーンごとに必要な電話の操作方法などを記録しておけば、不安なときに頼りになり、気持ちの面でも楽になるでしょう。
加えて、以下のような細かい工夫をしておくことも有効です。
- 電話をかけた瞬間に言葉に詰まってしまう場合は、事前にメモを用意しておき、確認しながら話す
- 声が小さい癖がある場合、マニュアルや電話の回りなどに「声を大きく」などの注意喚起を書いておく
- 口頭で説明するのが難しいことが事前にわかっている場合は、先にメールで詳細を送っておく
4-3.仕事の時間以外でも電話の練習をする
電話応対の不安を解消するには、苦手を克服できるまで何度も練習するのが近道です。休日は家族やパートナーに協力してもらって電話応対の練習をすると良いでしょう。
親しい間柄の方との電話練習なら、緊張せずにスムーズに応対できるはずです。そうして成功体験を重ねたうえで実際の電話応対に臨めば、練習と同じように緊張せずに対応しやすくなります。
また、自分の会話を録音することで、声のトーンや話し方に問題がないかをチェックできます。自分のペースで練習したい方はこちらの方法がおすすめです。録音→改善を繰り返すことで、自信をもって電話応対ができるようになるでしょう。
4-4.とにかく電話を取って数をこなす
電話応対に不慣れで苦手意識を感じている方は、とにかく数をこなすことが苦手を克服する近道です。仕事の日はできるだけ他の方より早く電話を取って実戦で練習しましょう。
最初のうちは言葉遣いやマナーで失敗することもあるかもしれませんが、数をこなしていくうちに上手に応対ができるようになるはずです。
多少の失敗を恐れず、もし失敗しても「次回は気をつけよう!」とポジティブに考え、どんどん電話を取って慣れていきましょう。
4-5.周りの目線は気にしなくて良い
電話で話しているときにふと上司と目が合ってしまうようなこともあるかもしれません。そのようなときは緊張してしまうかもしれませんが、ほとんどの場合、電話中に周囲から見られていることはありません。
上司はもちろん、他の方も自分の仕事で手一杯という時間がほとんどです。電話の内容に聞き耳を立てることはあっても、じっと見つめてくることはほとんどありません。周囲の視線を感じたとしても気にせず、落ち着いて電話応対すれば大丈夫です。
5.電話応対に関するQ&A
最後に、電話応対に関してよくある質問と回答をQ&A形式でまとめました。
5-1.電話になると敬語とフランクな言葉遣いが混じってしまいます。直し方はありますか?
日本語には「丁寧語」「謙譲語」「尊敬語」があり、場面によって使い分けが必要です。慣れていないと尊敬語を使う場面で謙譲語が出たり、丁寧語が出ずにフランクな言葉が出てしまったりします。
普段から言葉遣いに気をつけ、相手によって尊敬語や謙譲語を使い分けるクセを身につけることが大切です。
5-2.電話がかかってきたらすぐに出たほうが良いですか?すぐに出ようとするとメモの準備ができず焦ってしまいます。
電話が鳴ってからメモの用意をすると電話応対が遅れて、先方に迷惑をかけてしまうことがあります。電話応対をしていないときから常にメモと筆記用具を用意しておくことをおすすめします。
また、聞き手とは逆の手で受話器を取ることも意識しましょう。利き手で筆記用具を持てば、電話の内容次第ですぐにメモを取り始められます。
もしメモの準備ができていない場合は、先方が用件を話し出す前に「メモの用意をしますのでお待ちください」と断りを入れることも覚えておきましょう。
5-3.電話が聞こえにくいときはどうしたら良いでしょうか?
電話が聞こえにくい状態のまま話を進めると、重要な伝言を聞き逃してしまうことが考えられます。
「申し訳ございませんが、お電話が少し遠いようです」など、相手に電話が聞こえにくいことを伝え、あらためて内容を話してもらいましょう。
電話が聞こえにくい場合の伝え方の例は以下のとおりです。
- 大変申し訳ございません。お電話が遠いようなのですが、もう一度お願いできますでしょうか。
- 電波状況が悪いようです。恐れ入りますが、再度お聞かせいただけますか?
なお、「お声が遠いようです」は相手の声の小ささを責めるような印象があるのでNGとされています。
また、声が聞こえなくなったからといって適当に切ってしまうと失礼にあたります。電話を切る際は、丁寧に一言断ってから切るのがマナーです。必要ならこちらから折り返し、「お電話が遠いようでしたので、一度切らせていただきました」と伝えましょう。
6.まとめ
電話応対では相手の顔が見えず、音声だけでコミュニケーションを取る必要があります。相手によって声のトーンや話すスピードがまったく異なるため、不慣れなうちは緊張して失敗することもあるでしょう。
ただ、ベテラン社員も最初は失敗しながら電話応対のスキルを磨いたはずです。最初は多少の失敗は気にせず、慣れるためにもどんどん電話に出ることを意識しましょう。
どうしても電話応対の苦手意識がなくならない場合は、電話応対がない職種に転職することも選択肢の1つです。
JOBPALでは、電話応対の業務がない、または少ない製造・工場系の求人をご用意しています。電話が苦手な方はぜひ以下の求人一覧をチェックしてみてください。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す