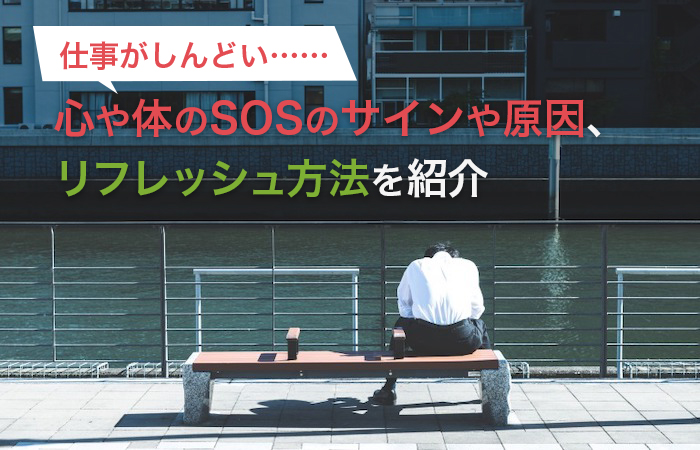休職したら給与はもらえるの?休職の種類や利用できる制度まとめ

※この記事は6分で読めます。
「休職中に給与は受け取れるの?」
「休職中に給与を受け取れないときはどうすれば良い?」
など、休職中の給与に関して疑問や不安を持っている方もいるでしょう。
休職中に給与が受け取れるかどうかは会社によって異なりますが、公的な制度をうまく活用すれば毎日の生活は不安なく送れます。
今回は、休職の概要、休職に多い理由、休職の種類、休職中に利用できる公的制度などを解説します。この記事を読めば、休職中の給与のことがよくわかり、会社に対して休職の相談を切り出しやすくなります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.休職とは?
休職(きゅうしょく)とは、会社に籍を置いたまま、従業員の自己都合などで労働義務が一時的に免除された状態のことです。労働基準法で定められた制度ではないため、休職期間や休職に当てはまる条件は会社ごとに異なります。
多くの会社は、「病気休職」「事故欠勤休職」など、休職の原因によっていくつかの休職制度を設けています。会社を退職すると給与収入がゼロになり、同じような仕事に就職できるかどうかもわかりません。休職制度は労働者にとって心強い制度といえるでしょう。
1-1.休業との違い
休業は、会社の都合で仕事が休みとなる制度です。会社の業績不振や設備の不具合、災害によって働くことができずに休みになった場合は、休職ではなく休業に該当します。平均賃金の6割以上の額の手当が支給されます。
会社によって制度内容に違いがある休職と違い、休業は法律に基づいた休みです。育児休業や介護休業は法律に基づいた制度で休みを取ることから「休業」と名前がついています。
2.休職に多い理由
休職する理由として考えられるのは、主に以下の2つです。
- 傷病による休職
- 自己都合による休職
傷病による休職には主に2つの種類があります。一つは会社と関係ない病気やケガによるケースです。風邪から肺炎を発症して入院が必要になったり、休暇中に骨折して出勤できなくなったりしたケースが該当します。
もう一つは仕事に関連するもので、通勤や業務による病気やケガのほか、うつ病や適応障害といった精神疾患も休職の理由になる場合があります。
自己都合による休職には「出産・育児」のための休職がもっとも多く、「休暇のため」「介護・看護のため」が続きます。短期留学のために休職する「留学休職」が用意されている企業もあります。
-
参照:総務省統計局|労働力調査 追加参考表
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/pdf/2021_1sankou.pdf
3.休職の種類
休職は法律で定められた制度ではないため、会社によって利用できる休職制度が異なります。ここでは、代表的な休職制度の種類をご紹介します。
3-1.傷病休職
文字通り、病気やケガを原因とする休職のことです。業務以外で発生したケガや病気が原因の私傷病(ししょうびょう)休暇と、業務が原因で発生したケガや病気の公傷病休暇があります。
私傷病の場合は、ケガや病気の状態次第で健康保険の傷病手当の受給対象になります。業務中のケガや通勤途中の事故であれば、業務上の災害として労災保険の補償が受けられます。
傷病休職を取得する際は、医療機関から発行された診断書の提出を求められることが一般的です。
3-2.事故欠勤休職
勤務外の事故が原因の長期休職のことです。この場合の事故とは交通事故のような意味ではなく「アクシデント」という意味で使われます。
例えば、従業員が事件を起こして逮捕・拘留されているなど、他の休職に当てはまらない場合に適用されます。
3-3.自己都合休職
個人的な理由で休職する制度です。ボランティアへの参加や海外留学(留学休職)を理由に会社を休職する場合は、自己都合休職に該当します。
近年は、ボランティアや海外留学で得た知識や経験を仕事に活かしてもらうべく自己都合休職の制度を設ける企業もあるようです。休職中の給与を補償されているケースであれば、自分のスキルアップに利用できるでしょう。
3-4.起訴休職
従業員が刑事事件の被告人になった場合に利用される休職制度です。判決が確定するまでのあいだは自宅で待機しなければならないため、起訴休職制度があれば活用しながら休むことができます。
会社としては、従業員が起訴されただけでは懲戒処分とするのは難しいのが実情です。しかし、出勤することで業務に支障が出る可能性もあることから、会社から休職が命じられる場合があります。
3-5.出向休職
労働者が会社との雇用契約を維持したままグループ企業や関連企業に出向した場合に、元々いた企業では休職扱いになる制度のことです。
元々の企業に籍を残す「在籍出向」と、籍ごと移転する「転籍出向」があり、在籍出向の場合には出向休職が適用されます。出向期間が満了して復帰するまで出向休職が続くことになります。
3-6.組合専従休職
労働組合の役員に選出された方が、労働組合の仕事に従事するために取る休職のことです。この休職が認められると、労働組合の仕事をすることになるため、使用者は会社から労働組合に変わります。
休職期間中は会社から従業員に給料が支払われることはなく、休職が終了して通常業務に戻った場合に給与の支払いが再開されます。
4.休職中の給与は支払われる?
自己都合で休職した従業員に対して、会社は給料を支払う義務はありません。労働基準法第24条にも「ノーワーク・ノーペイの原則」が定められており、基本的に休職中は無給となります。
ただし、休職は法律で決まった制度ではないため、会社によって給与の規定も異なる場合があります。就業規則によっては休職中でも一定の給与を受け取ることも可能です。なお、会社都合で休職になった場合には、一定の給与を受け取ることができます。
転職活動中に休職中の補償について気になるときは、面接の際に直接聞くこともできますが、応募前に転職アドバイザーに確認してみることをおすすめします。
JOBPALでは、お仕事に関する疑問や不明点をキャリアパートナーに確認できます。企業ごとの休職制度について聞きたい方はぜひご活用ください。
5.休職中に利用できる制度
自己都合による休職で会社から給与が支払われることは基本的にありませんが、公的に利用できる制度からお金を受け取ることはできます。ここでは、休職中に利用できる公的制度の種類について解説します。
5-1.傷病手当
傷病手当金は健康保険の制度から支給される手当で、協会けんぽや健保組合の被保険者が対象です。
支給開始日以前の継続した2ヵ月間の各月の「標準月額の平均÷30×2/3」を1日分として、支給開始日から通算して1年6ヵ月まで受け取れます。
なお、傷病手当金を受け取るためには、以下の受給要件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
5-2.障害年金
病気やケガによって生活・仕事が制限されるような場合に受け取れる年金のことです。
国民年金の加入者は障害基礎年金、厚生年金に加入している場合は障害厚生年金を受給できますが、以下の受給要件を満たす必要があります。
- 初診日を証明できること
- 障害状態にあること
- 一定期間の年金保険料の支払いがあること
障害の状態については、障害基礎年金では障害等級1級または2級のいずれかに該当すること、障害厚生年金は1級・2級・3級のいずれかに該当していることが条件です。
また、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることも必要な要件です。
5-3.生活保護
生活保護は、資産や能力などをすべて活用しても生活が困窮する場合に、困窮の程度に応じて必要な保護をおこなう制度のことです。
世帯の全収入が最低生活費を下回ることが受給要件ですが、まず家族や親族から援助を可能な限り受けることが前提です。それでも最低生活費を下回る収入しか得られない場合、不足分が支給されます。
よって、申請自体は可能でも、支援してくれる親族がいる場合には生活保護を受給できない可能性があります。
5-4.生活福祉資金貸付制度
低所得者、高齢者、障害者の生活を経済的に支え、在宅福祉や社会参加を図ることを目的にした貸付制度です。以下の3つの世帯が貸付対象とされています。
- 低所得者世帯:必要な資金を他から借りることが難しい世帯(住民税非課税世帯)
- 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳などの交付を受けた者が属する世帯
- 高齢者世帯:65歳以上の高齢者が属する世帯
生活福祉支援金貸付制度は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類に分かれます。現役世代が休職中に利用できる制度は、主に不動産担保型生活資金以外の3つです。
例えば総合支援資金では、生活支援費として生活再建までに必要な費用を借り入れることができ、借りられる金額は2人以上世帯で月20万円以内、単身世帯は月15万円以内です。
6.休職の給与に関するQ&A
最後に、休職中の給与に関してよくある質問と回答をまとめました。
6-1.休職したいときはどのように上司に話せば良いでしょうか?
休職の種類によって必要な書類や理由は異なりますが、診断書が必要な場合は医療機関から発行された診断書を持って直属の上司に相談しましょう。
休職したい旨を話すときは、体調が許す限り自分で直接上司に伝えるのがマナーです。就業規則に定められているなら正当な権利であるため、嘘をついたり怖がったりする必要はありません。休職したい理由は正直に伝えましょう。
6-2.休職はどのくらいの期間までできますか?
休職の期間については法律での定めがないため、会社の就業規則などの規定によって大きく変わります。
ただ、病気で休職している原因が仕事にある場合は、原則として療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇が法律で禁止されています。
6-3.休職したらクビになりますか?
休職したからといってすぐにクビにはなりません。ただ、会社の規定で定められた期間、または3年経っても回復せず復職しない場合には、会社は打切り保障(労働基準法81条)を実行でき、解雇ができます。
規定は会社ごとに異なるため、気になる場合は就業規則を確認しましょう。
7.まとめ
会社の就業規則に定めがあれば休職は労働者の権利であり、たとえ自己都合でも会社や上司に相談することに問題はありません。
一般的には休職中に給与は支給されませんが、企業によっては休職の種類に応じて一定額が支給される場合もあります。まずは会社の就業規則を確認してみましょう。
転職活動中の方が応募企業の休職制度について知りたい場合は、転職アドバイザーに聞いてみるのがおすすめです。JOBPALではキャリアパートナーによる面談を実施しており、応募企業についてわからないことを相談できます。
企業ごとの休職制度に興味があれば、ぜひJOBPALの面談に応募してみてください。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す