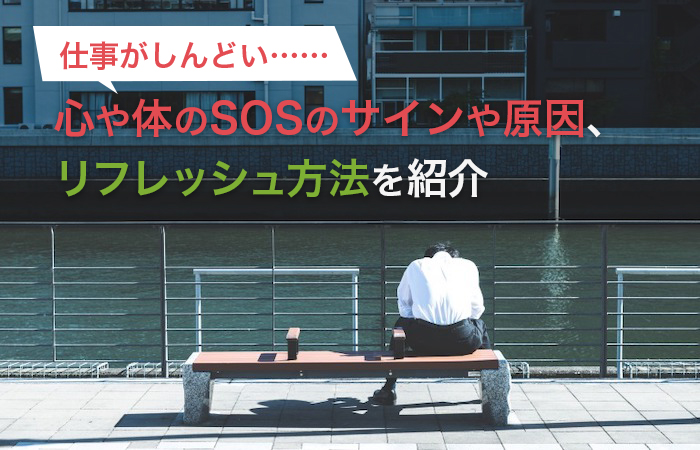仕事が続かない人の特徴や原因とは?知っておくべきリスクや対処法・天職の見つけ方
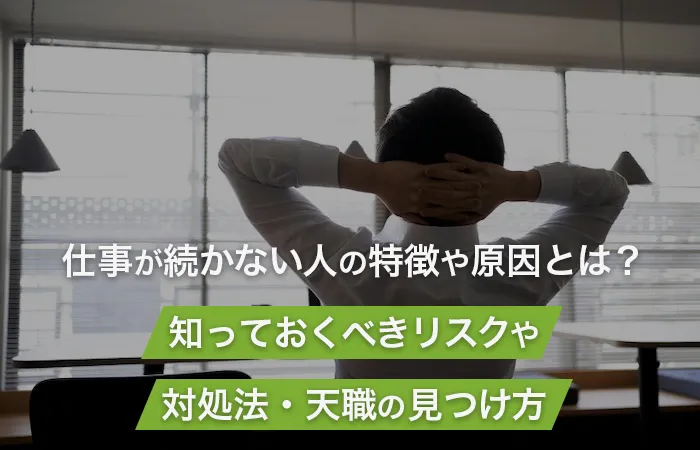
※この記事は6分30秒で読めます。
「なかなか仕事が続かない」
「自分に合った仕事はどうやって探せば良いの?」
など、仕事が長く続かないことに関して、疑問を持っている方もいるでしょう。
仕事が続かない人でも、原因を把握して適切な対策に取り組むことで、長く続けられる仕事に出会うことが可能です。
今回は、仕事が続かない人の特徴、仕事が続かない状況の改善方法、長続きしやすい仕事の例などを解説します。この記事を読めば、今まで仕事が続かなかった原因を再認識でき、長く続けられる方法やコツ・天職がわかるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.一つの仕事が長く続かない人の9つの特徴や原因
まずは、一つの仕事が長く続かない人に見られる9つの特徴をご紹介します。
- 仕事に対する目的を持っていない
- 経済的に余裕があり逃げ場がある
- うまく人間関係を構築できていない
- 理想を高く持ちすぎている
- 些細なミスを気にし過ぎている
- 自分に合う仕事が見つかっていない
- 自己評価が低すぎる
- 仕事にやりがいを求め過ぎる
- 何ごとに対しても飽きっぽい
それぞれの特徴について確認していきましょう。
1-1.仕事に対する目的を持っていない
仕事に対する目的を明確に持っていない人は、仕事が長く続かないでしょう。目的意識を持てなければ、何かを成し遂げたいという思いが芽生えず、次第に「何でここにいるんだろう」と思うようになり、仕事を辞めたい気持ちが強くなります。
一方、「家族を養わなければならない」「車が欲しい」「貯金を増やしたい」など、働いて得たお金でやらなければならないこと、やりたいことがある人は、目的に向かって努力でき、仕事を長く続けられるでしょう。
1-2.経済的に余裕があり逃げ場がある
経済的に余裕があり、働かなくても生活に困らない人も、仕事が長く続かない人の特徴です。
例えば、実家暮らしの場合、自分が仕事を辞めたとしても、住む場所や食べるものに困窮する可能性は低いでしょう。
何かあったときの逃げ場がある人は「石にかじりついても仕事に行かないと」という必死な状況とは無縁のため、仕事で嫌なことがあったりうまくいかなかったりするとすぐに「辞めよう」と思ってしまうことがあります。
対して、親やパートナーを頼れない状況だったり、一人暮らしをしていたりすると、自分が仕事をして収入を得なければ暮らしていけないため、少々のことでは仕事をやめるという決断はできなくなります。
1-3.うまく人間関係を構築できていない
コミュニケーションスキルに問題があったり、緊張でうまく話せなかったりして上司や同僚との関係がうまく構築できず、職場の居心地の悪さに耐えかねて仕事を辞めてしまう人もいます。
仕事に関する質問でさえ躊躇してしまう、休憩中も周囲に気を遣うという状況では、徐々に精神が疲弊し、仕事に行くのがつらくなってしまいます。
1-4.理想を高く持ちすぎている
会社や業務に対して、現実よりも高い理想を描いている人も、仕事が続かない人の典型的な例です。
ある程度の理想はモチベーションになりますが、あまりに壮大な理想を持ってしまうと、現実とのギャップを目のあたりにしたときに落胆し、耐えきれずに仕事を辞めたくなります。
例えば、華やかな仕事だと思っていたのに、実際は人目につかない地味な作業ばかりだと、自分の居場所は別にあると感じ長く続かないでしょう。
1-5.些細なミスを気にし過ぎている
些細なミスを引きずってしまうのは、真面目な人ゆえの思考の癖ですが、マイナス思考に苛まれて、仕事が続かないというケースが見受けられます。「○○でなければならない」と自分なりの信念を持ち、自分を許すことができない完璧主義者が陥りがちです。
上司にひどく怒られた、同僚から反感を買ったといった場合はもちろん、ネガティブな反応がなかったとしても、ふとしたことから自分で自分を責めてしまい、自信を失って仕事から逃げ出したくなってしまいます。
1-6.自分に合う仕事が見つかっていない
自分に合う仕事が見つからず、何となく今の会社に入社したという場合は、仕事が長く続かなくても致し方ありません。自分に合わない仕事に対して、モチベーションを高く保つことは簡単ではないでしょう。
合わないポイントは仕事内容のみならず、企業風土や職場環境、待遇面など、さまざまな要因が考えられます。上司や同僚が楽しそうに生き生きと働いていればいるほど、自分とのギャップを感じ、辞めたいと強く思ってしまうかもしれません。
1-7.自己評価が低すぎる
自己評価が極端に低いことが、仕事が続かない原因になっている可能性もあります。仕事のミスは誰にでもあるものですが、自己評価が低いと「この仕事は自分には荷が重すぎる」「次にミスしたらもう会社にいられない」などと過剰なマイナス思考になってしまいます。
マイナス思考が影響し、結果的に与えられた仕事をこなせなかったり、集中して取り組めなかったりして、周囲からの評価にも影響することが考えられます。
1-8.仕事にやりがいを求め過ぎる
仕事に「やりがい」を求めすぎることも、長続きしない原因の一つです。理想が高いあまり現実とのギャップが大きくなり、「もっとクリエイティブな仕事がしたかった」「自分のレベルならもっと高度な仕事ができるのに」と不満に感じることが増えると考えられます。
与えられた職務のなかで「やりがい」を見つけることを覚えない限り、短期間で退職を繰り返すことになるかもしれません。
1-9.何ごとに対しても飽きっぽい
さまざまなことにチャレンジする気持ちがある人は、新しい仕事にも怖がらず挑戦できます。一方、「目移りしてしまう」「飽きっぽい」というマイナスな側面があることには注意が必要です。
友人と話したり他の会社を調べたりしているうちに、何となく他の会社のほうが良い仕事ができると感じて転職をしてしまうことが考えられます。
2.仕事が続かない状況を改善しないリスク
仕事が続かない状況は誰にでも起こりうることです。しかし、状況の改善を試みないと以下のようなリスクを抱えることになります。
- 経験やスキルを得られない
- 収入が上がりづらい
- すぐに辞める癖がつく
- 転職先が見つからなくなる
- 社会的信用度が低くなる
あとになって「あのときああしておけばよかった……」と後悔することがないよう、今できる改善をしておくことが大切です。
仕事が続けられない状態を改善しない場合のリスクについて、詳しくみていきましょう。
2-1.経験やスキルを得られない
仕事が続かない人は、短期間で転職することになるため、経験やスキルがなかなか身につきません。経験やスキルは、一定以上仕事を続けるなかで少しずつ得られるものです。
短期間で職を転々とすると、知識やスキルの学びが中途半端な状態で止まってしまいます。
まったくの素人ではないものの、自分のものにして活かせる状態ではないため、応用を利かせたり、転職に活かせたりするほどの自己成長は難しいでしょう。
2-2.収入が上がりづらい
就業期間が短いために収入が上がらず、生活が苦しくなるリスクもあります。収入アップの一つの要素は勤続年数です。成果主義の企業もありますが、多くの企業では昔からの年功序列の名残があり、より長い勤続年数の人を評価する風潮があります。
また、年一回など会社が定める昇給のチャンスも逸してしまう可能性があります。結果、低収入のまま転職を繰り返すことになってしまいます。
2-3.すぐに辞める癖がつく
どうしても耐えられない仕事なら、心身に異変が出る前に辞めることも必要になる場合もあります。ただ、何かあるたびに感情的になり、辞めることを繰り返していくと、「辞め癖」がついてしまう場合があります。
辞め癖がついてしまうと、少しのトラブルでも「辞めれば良い」と考えてしまい、自分が成長する機会が失われます。
通常は、上司に辞めることを相談するのはハードルが高いものですが、辞め癖がついていると心理的ハードルが下がって簡単に辞めるようになってしまいます。
2-4.転職先が見つからなくなる
仕事が続かないと、そのたびに転職活動をすることになりますが、回数を重ね過ぎると面接時に良い評価を得るのが難しくなる可能性があります。
1~2回程度なら問題ありませんが、それ以上になると、応募先企業の採用担当者に「何か事情や問題がある人なのではないか」「飽きたらすぐに辞めそう」と思われてしまいます。
書類選考を突破し面接に進めても、企業が抱く懸念を打ち消すポジティブな要素がなければ、内定獲得は難しいでしょう。
2-5.社会的信用度が低くなる
すぐに辞めて転職を繰り返すと「スキルが身につかない」→「スキルも勤続年数もないから給料が上がらない」→「スキルがないから転職先が見つからない」といった悪循環に陥ってしまいます。
この状態を繰り返すと、転職活動の際に履歴書等を見た採用担当者から「この人はどのような仕事であっても長く続かないのでは?」ととらえられてしまう可能性があります。そうすると、ますます採用から遠のいてしまうでしょう。
定職に就けなくなってしまうと社会的な信用を大いに失い、収入面以外にも悪影響があります。ローンを組むときなど、正社員として安定した収入を得ていないと審査においてマイナスに働くことが考えられます。
3.仕事が続かない状況を改善する8つの対処法
これまで仕事がなかなか続かなかった人は、前述したリスクを回避するために、少しでも早く改善するように努力しましょう。工夫次第で状況を改善できるはずです。ここでは、すぐに取り組める8つの方法をご紹介します。
- 心に余裕を持って仕事に取り組む
- すぐに決断せず我慢してみる
- 他人と自分を比較するのをやめる
- 仕事とプライベートのメリハリをつける
- 自分に合わない仕事は引き受けない
- 心を許せる人に悩みを相談する
- 生活のための仕事だと割り切る
- 自分に合ったストレス解消法を探しておく
できることから実践してみましょう。
3-1.心に余裕を持って仕事に取り組む
常に緊張し張り詰めた状態だと、自分が意識している以上に体力を消耗し、疲労を感じてしまうでしょう。すべてを完璧にやらなければと思わず、少し心を緩めたほうがうまくいくこともあります。
完璧主義は本人の性質の部分が大きいため、自分の中の「完璧」の基準を調整してみましょう。例えば、「ミスは発生するもの」という前提のもと、ミスをした自分を責め続けるのではなく、「ミスを含めて得たものを次の仕事に活かそう」と考えることで、心に余裕をもって仕事ができます。
3-2.すぐに決断せず我慢してみる
仕事が続かない人は、我慢をせずにすぐに退職という決断に至りがちです。転職してから数ヵ月~1年程度は覚えることが多く、段取りもわからないため、我慢の連続になります。
自分が一通りの仕事をこなせるようになるまでは辞めずに我慢してみましょう。年月が経ち、人間関係も深まれば、辞めたい感情がなくなってくるかもしれません。
仕事を一人前にこなせるようになっても、なお「辞めたい」という気持ちが消えないときは、そのときにあらためて考えてみましょう。
3-3.他人と自分を比較するのをやめる
他人と自分を比較する癖がある人は、意識して比較しないように努力してみましょう。
他人と比べて、自分の経験やスキルが劣っていると感じると、「頑張っても追いつけない」と諦めを感じたり、「無理に決まっている」と投げやりになったりして、仕事自体が嫌になる場合があります。
しかし、生まれや育ち、性格、経験など、人はそれぞれが違う個性を持つものです。他人は他人、自分は自分、得意不得意はそれぞれ違って当然、などと割り切るようにしましょう。
3-4.仕事とプライベートのメリハリをつける
仕事とプライベートをしっかりと分け、メリハリのある暮らしを目指しましょう。何をしていても仕事が頭から離れないという状況では、ストレスがかかるのも無理はありません。
プライベートの時間には、好きなことをして心をリフレッシュさせることがおすすめです。仕事以外の時間が充実すれば、自然と生活にメリハリが出てくるでしょう。
3-5.自分に合わない仕事は引き受けない
真面目な人は、上司や先輩から任された仕事を何でもすべて引き受けてしまうこともあるでしょう。そうするとタスク量が膨大になってしまい、一つひとつの仕事のクオリティが下がってしまうことがあります。
仕事にはそれぞれ向き・不向きがあるため、何でも引き受けることが最適解とは限りません。キャパオーバーになることはもちろんですが、自分がやることでかえって時間がかかったり、自分の能力では対処できなかったりする場合は、勇気を持って断ることも大切です。
会社や部署、上司によっても断れるかどうかが変わりますが、できる範囲で「得意な仕事」「自分なら効率的に進められる仕事」「楽しい仕事」に集中することで、ストレスなく仕事が進められます。適材適所で仕事の効率が上がれば、結果的に会社にも貢献できるでしょう。
ただし、単に断るだけではなく、チーム内で仕事の割り振りを見直す配慮も必要です。
3-6.心を許せる人に悩みを相談する
尊敬する先輩や学生時代の友人、パートナー、家族など、心を許せる相手に悩みを聞いてもらうこともおすすめです。
「仕事が続かない」「辞めたい」という悩みを人に相談することで、ストレスが軽減されるだけでなく、自分の気持ちを再確認できます。
3-7.生活のための仕事だと割り切る
仕事にやりがいを求めすぎず、時には「生活のため」と割り切ることも大切です。仕事をするのは「お金のため」「プライベートのため」と割り切って、給料は我慢料だと思うほうがうまくいくこともあります。
まずは目の前の仕事に集中し、継続的に収入を得ることや、早く帰ってプライベートを充実させることを第一に考えてみましょう。
また、転職活動には、「将来の退職金が減る」「ボーナスをもらえない可能性がある」「転職活動の交通費などがかかる」などのマイナス要素もあることを覚えておきましょう。
3-8.自分に合ったストレス解消法を探しておく
毎日の仕事で過度なストレスを抱えてしまうと、休日を楽しく過ごすことができません。仕事の疲れやストレスが抜けないまま、次の週の仕事を始めることになってしまいます。
平日は職場と自宅の往復、休日は体力を回復させるために寝る、といった生活を続けている方は、プライベートを充実させる楽しみを見つけてみましょう。
打ち込めるスポーツやゲーム、旅行など、趣味や娯楽を見つけることでストレスが解消でき、仕事のモチベーションアップにつながります。
4.長く続けられる!自分に合う天職を見つけるコツ
「今度こそ仕事を続けたい!」と決意するあなたへ、自分に本当に合った仕事探しの方法をご紹介します。
- 仕事が長く続かない原因を書き出してみる
- 自分に合う仕事は何か徹底的に考える
- 第三者の意見を聞いてみる
- 適職診断を受ける
- 転職エージェントに相談する
「これだ」と思える天職に出会えれば、仕事が続かない自分からきっと卒業できるはずです。
4-1.仕事が長く続かない原因を書き出してみる
仕事が長く続かない原因がどこにあるのか、思いつくことを書き出してみましょう。今まで不安や不満に感じたこと、退職の決め手、影響していると思われる自分の性格など、原因と考えられる要素を深掘りすることが大切です。
原因によっては、上司に相談することで解決に至る可能性もあり、仕事を辞める必要がなくなるでしょう。
4-2.自分に合う仕事は何か徹底的に考える
適職を見つけるためには、自分と向き合い、「自分に合う仕事が何なのか」を見つけることが大切です。
自分の強みや弱み、好きなことや苦手なこと、今まで評価された要素など、過去のエピソードをもとに自分を振り返ってみましょう。自分の性格や特徴によっても「長続きしやすい仕事」は変わってきます。
ここでは、長続きしやすい仕事の例を、性格や特徴ごとにご紹介します。
4-2-1.人間関係で悩みやすい人向けの仕事
人間関係が原因で仕事が続かない人には、一人で黙々と続けられる仕事がおすすめです。
代表的な仕事としては、「工場勤務」「配送ドライバー」「新聞配達・ポスティング」などがあります。
工場勤務では、同僚や上司と連携して動く梱包や検品といった部署もありますが、製造ラインであれば黙々と製造に集中できます。
ドライバーや新聞配達も、公道に出てしまえば一人で黙々と運転する時間が大半であり、人間関係のストレスを感じずに仕事ができる傾向があります。
4-2-2.飽きっぽい人向けの仕事
自分の性格を「飽きっぽい」と自覚している人は、単調作業にならない仕事が向いています。具体例としては「営業」「介護」などです。
営業は、会社の売上を上げるために客先に出向いてプレゼンをし、契約を獲得する仕事です。訪問先は日々変わるため、常に新しい気持ちで顧客と向き合うことができます。
介護は、利用者の食事や入浴、排泄、着替えなどを手伝う仕事です。業務内容は多岐にわたるため、臨機応変さが求められます。
4-2-3.体を動かしていたい人向けの仕事
体を動かして仕事をしたい人は、事務や経理ではなく現場で働ける職種を選びましょう。具体的には「工場勤務」「引越し業者」「清掃業者」などがあります。
工場の場合、工程(生産する順番など)を考える部門や営業事務、品質管理は座って仕事をするケースが多いですが、現場の製造ラインや検品・梱包、出荷などの部門で働く人は立ち仕事が基本となります。
引越し業者はトラックで移動し、依頼先に荷物を運ぶことが仕事のため、身体を動かしたい方にはおすすめです。
清掃業者も1日中体を動かす仕事ですが、引越しや製造ラインほど重いものや危険なものは扱いません。家事のスキルがそのまま仕事に活かせるため、家事が得意な人に向いています。
4-3.第三者の意見を聞いてみる
今まで自分だけで就職・転職活動をしてきた方は、第三者にアドバイスを求めることも考えましょう。家族や友人に悩みを聞いてもらい、転職に関するアドバイスをもらってみると、今まで自分では気付けなかったポイントを指摘してくれるかもしれません。
また、自分では「自分は○○な性格だ」と思っていても、周囲からはまったく違う性格に見えていることもあります。第三者に聞くことで、あらためて自分自身の性格や特徴を知るきっかけになるでしょう。
以下の記事では、転職を考える際に相談すべき相手やその方法について解説しています。
4-4.適職診断を受ける
自分に合う仕事がどうしてもわからない場合、適職診断を受けることも検討しましょう。インターネット上には数多くの適職診断ツールがあります。ツールを利用することで、自分の性格や強み・弱みを把握でき、転職活動の仕事探しに活かすことができます。
ただ、それはあくまでも自分の中のほんの一部だけを切り取って診断したに過ぎず、自己分析の結果と一致しないこともあるかもしれません。
適職診断の結果は参考程度にとどめ、自分でも自己分析や業界研究を進めることが大切です。
以下の記事では、自分に合った仕事の探し方について解説しています。
4-5.転職サポートに相談する
仕事が続かない自分から卒業したいと強い決意を持っている場合は、転職サポートへの相談がおすすめです。経験豊富なアドバイザーがサポートしてくれるので、過去の経験や人柄からあなたの適職を見抜き、仕事を紹介してくれます。
UTグループでも、就職や転職に関する相談を受け付けています。経験豊富な担当者が求人探しをサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
5.どうしても仕事を辞めたいときに考えるべきこと
いろいろ努力はしたものの「どうしても今の仕事を辞めたい」と思ってしまう人もいるでしょう。そんな自分に嫌気がさし、将来に不安を覚えている人もいるかもしれません。
しかし、大前提として理解しておきたいのは、仕事を辞めることは決して悪いことではないということです。
短期間のうちに転職を繰り返すことにリスクであることは間違いありません。とはいえ無理なく働き続けられる仕事を探すほうが、長い目で見て良い選択となることもあります。
また、「仕事はあくまでも人生の一部」という考え方もぜひ持っておきましょう。時間も心も仕事に支配されると、リラックスしたりプライベートを楽しんだりする余裕がなくなってしまいます。
自分の人生を豊かにするためにも、仕事とプライベートのバランスをうまく図ることが大切です。
6.まとめ
仕事が続かない人には、必ず何らかの理由があります。まずは今までの退職理由を振り返ってみましょう。
過去は変えられなくても、未来はあなたの心がけ次第で変えることができます。今回の内容を参考に、自分に本当に合う仕事を探してみましょう。また、性格によって天職は変わってくるため、まずは自己分析を進めることもおすすめです。
JOBPALでは、さまざまな業種業界の求人情報を掲載しています。気になる求人があれば、お気軽にお問い合わせください。あなたが今感じている悩みを少しでも解消できるようにサポートさせていただきます。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す