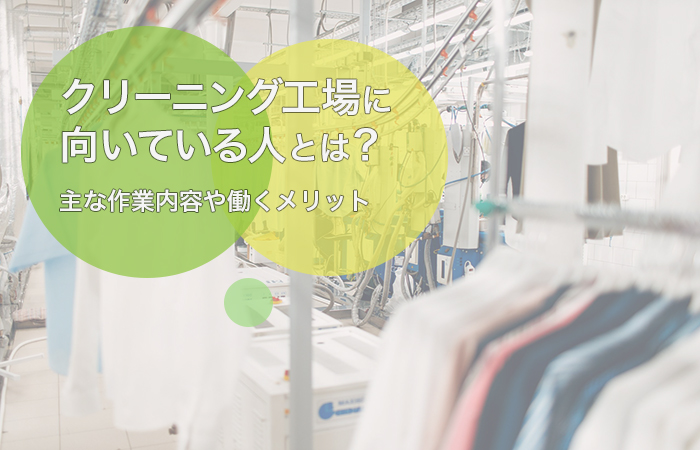消防設備士とは?仕事内容や資格概要、合格率、活躍できる職場を徹底解説
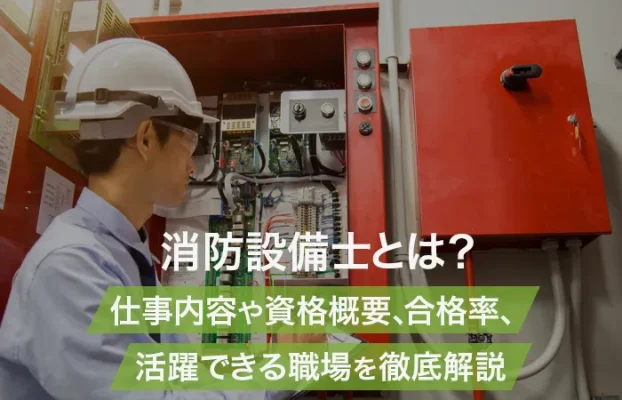
※この記事は6分30秒で読めます。
「消防設備士ってどんな仕事?」
「消防設備士として働くメリットが知りたい」
など、消防設備士に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
消防設備士は、公共施設や工場などの消防設備の点検・整備ができる国家資格であり、手に職をつけたい人や需要のある業界で働きたい人に向いています。
今回は、消防設備士の概要、資格取得までの流れ、向いている人の特徴などを解説します。この記事を読めば消防設備士のことがよくわかり、消防設備士として働く自分の未来をイメージできるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.消防設備士とは
消防設備士は、施設に設置されている消防設備の点検・整備ができる国家資格です。1965年の消防法改正により制定された資格で、大きく「甲種」と「乙種」に分かれています。乙種は消防設備の点検・整備、甲種は乙種の範囲に加えて消防設備の設置・交換作業まで従事することが可能です。
消火器や火災報知器、スプリンクラーなど、建物内に設置された消防設備を点検したり整備したりといった仕事は、消防設備士を持った方のみ従事することができます。いわゆる「業務独占資格」であり、有資格者の活躍の場が多い仕事です。
1-1.消防設備士の資格の種類
消防設備士は「甲種1~5類」「乙種1~7類」の計13種類があり、取得した資格区分によって業務範囲が以下のように異なります。
| 免状の種類 | 類別 | 消防用設備等 |
|---|---|---|
| 甲種 | 特類 | 特殊消防用設備等 (従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等) |
| 甲種又は乙種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 | |
| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 | |
| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |
| 乙種 | 第6類 | 消火器 |
| 第7類 | 漏電火災警報器 |
-
参照:消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター
https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/
1-1-1.点検と整備のみ可能な「乙種」
乙種は、消防用設備等の整備・点検業務のみ従事できる資格です。第1類~第7類まであります。
1-1-2.点検と工事、整備が可能な「甲種」
甲種は乙種の上位資格であり、点検と整備に加えて設置工事まで携わることができます。
1-1-3.最上位の資格「甲種特類」
甲種には「甲種特類」と呼ばれる区分があり、乙種・甲種の資格分類では扱っていない「特殊消防設備」の点検や工事をすることができます。
1-2.消防設備士の仕事内容
扱える消防用設備は、保有している消防設備士の資格ごとに異なります。いずれも、有資格者のみ対応できる消防設備の工事・点検・整備ができます。
一定以上の規模の商業施設やホテル、劇場などといった施設の消防用設備や警備設備の点検整備・設置工事などがその一例です。公共施設やビルなどでは定期的に消防設備を点検することが法律で定められていることから、全国どこでも仕事を見つけるチャンスがあります。
1-1-2.扱える消防用設備は資格ごとに異なる
前述の通り消防設備士の資格は3つに分かれており、乙種はさらに1~7類、甲種は1~5類に細分化されます。1類はスプリンクラー設備、5類は金属製避難はしごといった具合に、それぞれ扱える消防設備が異なります。
| 特類 | 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等に関する点検・整備・工事 |
| 第1類 | 消火栓やスプリンクラーといった水系の消防設備 |
| 第2類 | 泡を使った消火設備 |
| 第3類 | 二酸化炭素・窒素ガス、粉末を使う消防設備 |
| 第4類 | 火災報知器の点検・設置・工事 |
| 第5類 | 火災の際の避難に使用する避難器具の点検・整備・工事 |
| 第6類 | 消火器の点検・整備 |
| 第7類 | 漏電火災警報器の点検・整備 |
2.消防設備士の資格を活かせる就職先
消防設備士の資格保有者が必要とされている職場としては、以下のような企業や施設が挙げられます。
- 工場・倉庫
- 消防設備の専門会社
- 防災設備の会社
- ビルメンテナンス業務や電気設備業務を請け負う会社
- 不動産会社のビルメンテナンス業務を請け負う会社
- 電気設備業務を請け負う会社 など
消防設備士は業務独占資格であり、需要の高さから有資格者が優遇されることは珍しくありません。
以下の記事では、関連する業務である設備保守の仕事について解説しています。
3.消防設備士の資格を取得する方法
消防設備士の資格を取得するには、受験資格を満たしたうえで試験を突破する必要があります。ここからは、消防設備士の資格を取得するための方法を見ていきましょう。
3-1.消防設備士の受験資格
同じ消防設備士でも、「乙種」と「甲種」で受験資格は異なります。また、甲類は資格を満たさないと資格試験を受けることはできません。
3-1-1.乙種消防設備士
乙種の場合、特別な受験資格は特にありません。第1~7類まで誰でも受験することができます。
3-1-2.甲種消防設備士
甲種の試験を受けるには、一定の受験資格を満たしている必要があります。国家資格の取得や現場での実務経験、一定の学科(機械や電気、工業化学、土木または建築に関する学科)や課程の修了といった制限があるため、自身が受験資格を満たしていることを確認してから申し込むようにしましょう。
3-1-3.特類
甲種特類は「甲種の4類と5類の資格保有、甲種1類から3類のいずれか一つ、合計3種類以上の甲種の資格保有をしていること」が受験資格として定められています。
3-2.試験は筆記試験と技能試験の2つ
消防設備士の試験は「筆記試験」と「技能試験」の2つがあります。筆記試験は四肢択一式のマークシート方式です。技能試験は機器の識別などをする「鑑別等」と「製図」があり、資格の難易度によってそれぞれの出題範囲や難易度が異なります。
3-2-1.乙種の場合
乙種の試験範囲は甲種と似ているものの、工事に関わらないことから工事に関する問題は出題されません。消防関連法令、基礎知識、構造や設備から出題されます。
3-2-2.甲種の場合
甲種1~5類の筆記試験の出題範囲は「消防関係法令、基礎的知識、構造・機能、及び工事・整備」です。実技試験では「鑑別等」と「製図」が出題されます。
3-2-3.特類の場合
法令のほか、工事設備対象設備等の構造や機能、火災及び防火の3つの科目が出題範囲です。なお、特類には実技試験はありません。
3-3.消防設備士までの流れ
消防設備士になるまでには、「受験の手続きをする」「試験を受ける」というプロセスが必要であり、さらに免許取得後も定期的に講習の受講が必要です。それぞれの手続きの流れについて解説します。
3-3-1.受験の手続きをする
消防設備士の試験回数は年2回〜4回で、都道府県ごとによって違いがあります。全国のどの試験センターでも受験できるため、都合の良い日程で開催されている試験会場を選択しましょう。
受験費用は以下のとおりです。
- 甲種 5,700円
- 乙種 3,800円
申し込み方法は、書面申請(願書による申請)と電子申請(インターネットによる申請)の2通りがあります。
書面申請の場合、各都道府県の消防設備試験研究センター各支部の窓口で配布されている願書を入手しましょう。持参または郵送(受付締切日の消印有効)の方法で申し込むことができます。
オンラインにつながる環境であれば、パソコン・スマートフォンによる電子申請が可能です。ただし、以下の場合には電子申請ができないため、書面による申請をおこないましょう。
- 受験資格を証明する書類が必要な場合(電気工事士・電気主任技術者、実務経験、工事補助(設備士)、卒業証書等証明書など)
- 消防設備士試験で科目免除を希望し、資格証明の書類が必要な場合(電気工事士・電気主任技術者・火薬類免状保有者など)
- 同一試験日に複数の受験を申請する場合
3-3-2.試験を受ける
各都道府県にある消防試験研究センターの指定場所が試験会場になります。場所は受験票に記載されているので、必ず確認しておきましょう。
3-3-3.免許取得後も定期講習を受講する
乙種、甲種に関係なく、消防設備士の資格を持っている人は「消防設備士講習」の受講が必要です。人命に関わる業務であることに加え、社会情勢、消防法や消防設備の時代に合わせた変化などに対応していくため、資格取得後も定期講習の受講が義務付けられています。
受講の申請方法は郵送(簡易書留が推奨)で、申し込みには以下の書類の提出が必要となります。
- 受講申請書 (県の収入証紙7,000円分および消防設備士免状コピー(表と裏)貼付) ※申請書は講習区分毎に1枚ずつ必要です。
- 63円切手
講習の日程や会場は都道府県ごとに異なるため、各都道府県の消防試験研究センター支部で確認してください。
-
参照:電子申請トップ : 一般財団法人消防試験研究センター
https://shinsei.shoubo-shiken.or.jp/shoubou_ia/iajs0101.do
3-4.消防設備士の合格率
消防設備士の合格率は、甲種でおおむね30%、乙種で40%弱となっています。
令和4年度の受験者数と合格率は以下のとおりです。
【甲種・令和4年度】
| 年度 | 区分 | 甲種 | ||||||
| 特類 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 甲種計 | ||
| 令和4年 | 受験者 | 654 | 6,337 | 2,018 | 2.120 | 10,337 | 2,116 | 23,582 |
| 合格者 | 195 | 1,375 | 617 | 668 | 3,557 | 746 | 7,158 | |
| 合格率 | 29.8 | 21.7 | 30.6 | 31.5 | 34.4 | 35.3 | 30.4 | |
【乙種・令和4年度】
| 年度 | 区分 | 乙種 | ||||||||
| 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 | 乙種計 | |||
| 令和4年 | 受験者 | 1,140 | 383 | 594 | 4,406 | 569 | 13,478 | 3,158 | 23,728 | |
| 合格者 | 341 | 125 | 187 | 1,550 | 228 | 5,140 | 1,849 | 9,420 | ||
| 合格率 | 29.9 | 32.6 | 31.5 | 35.2 | 40.1 | 38.1 | 58.5 | 39.7 | ||
-
参照:試験実施状況|一般財団法人消防試験研究センター
https://www.shoubo-shiken.or.jp/result/
4.消防設備士の資格を取得するメリット4つ
消防設備士を取得することで、さまざまなメリットを享受できるようになります。以下では消防設備士を取得することの代表的な4つのメリットをご紹介します。
以下の記事では、消防設備士以外にも転職に役立つ資格をご紹介しています。
4-1.さまざまな施設で必要とされる
消防設備士は消防の設備を点検・整備・工事する際の必須資格であり、業務独占資格です。
消防法により、一般の居住用住宅以外のほとんどの建物で消防設備の定期的な点検とメンテナンスが義務付けられていることから、さまざまな施設で必要とされています。ビル、商業施設、病院など、さまざまな職場が見つかるでしょう。
4-2.一生の仕事として続けられる
消火器の点検・整備が可能な「乙種第6類」、火災報知設備の点検・整備ができる「乙種第4類」をはじめとする消防設備士資格は、今後も高い需要が見込めます。
業務独占資格という強みもあり、取得すれば就職先に困ることは少ないでしょう。手に職をつければ、定年後に再雇用を目指すことも可能です。
4-3.給与が上がる可能性がある
有資格者の確保が必要な会社では、資格を持つ人に「資格手当」を支払うことも少なくありません。資格取得によって収入のアップが期待できます。
4-4.就職や転職でアピールできる
消防設備士の資格保持者は多種多様な現場で必要とされており、仕事の性質上、AIに置き換わることも考えにくい資格です。法律によって定められた業務については資格を有していなければ携わることができず、需要は常に存在します。
5.消防設備士の仕事の魅力
消防設備士は、火災が生じた際に素早く対応するための消防用設備の設置や点検、整備が仕事です。正しく動く消防設備がなければ、多くの命が失われることになります。
医師や看護師のように直接人の命を守るわけではありませんが、間接的に大勢の人命を守ることにもつながる、とてもやりがいのある仕事です。社会の役に立つ仕事を探しているのであれば、消防設備士は有力な候補といえるでしょう。
6.消防設備士の仕事に向いている人
どんな仕事でも向き不向きはありますので、自身の希望や特性と合った仕事を見つけることが転職活動では重要です。では、消防設備士にはどんな人が向いているのでしょうか?
なお、以下の記事では自分に合った仕事の探し方を解説しています。
6-1.人のために働きたい人
消防設備士は多くの人が集まる場所の防火管理を担う仕事であり、業務は人命を守ることにつながります。「自分の仕事が人を救うこともある」という使命感に燃えた人や、人の幸せのために働きたい人に向いている仕事です。
6-2.学習意欲がある人
近年は防災に対する人々の意識が高まっており、それに合わせて今後の法改正も予想されます。実際の事故や災害をもとに運用マニュアルもブラッシュアップされることが多いため、常に最新の法律や情報を勉強し、現場の業務へ落とし込むことが求められます。
また、有資格者であっても定期的な講習への参加は必須であり、「取得して終わり」という資格ではありません。学習意欲が高く、継続的な勉強が苦にならない人に向いているでしょう。
7.まとめ
消防設備士は、消防設備の点検・整備・工事に携わることができる国家資格で、防災への関心が高まっていることから高い需要が期待できる資格です。消防施設が設置された企業や施設であればどこでも職場になる可能性があります。また、プライベートでも資格の知識は役に立つでしょう。
甲種特類までの取得には長い時間を要しますが、興味があればチャレンジしてみてはいかがでしょうか?