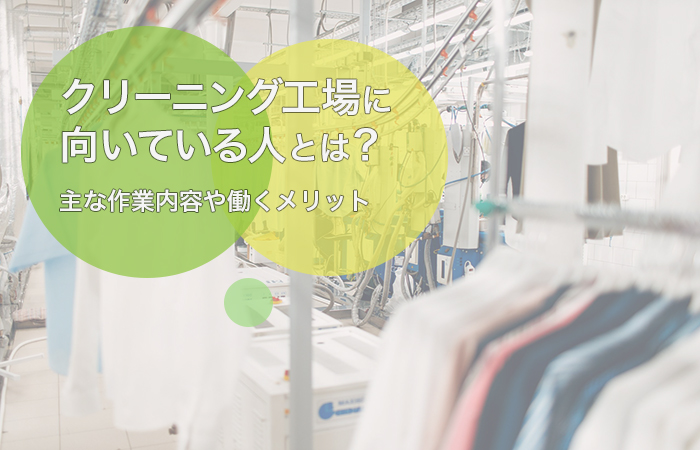工場の検査作業とは?仕事内容や資格、働くメリットを解説

※この記事は6分で読めます。
「検査作業ってどんな仕事?」
「検査作業にはどんな種類がある?」
など、検査作業に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
検査作業は工場から出荷する前に不良品を発見するための工程であり、クレームの発生を未然に防ぐ重要な仕事です。
今回は、検査作業の概要と必要性、検査作業の種類、向いている人の特徴などを解説します。この記事を読めば検査作業のことがよくわかり、実際に働く姿をイメージできるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.検査作業とは
「検査作業」とは、製品の品質を担保するため、工場で作られた製品の品質検査をする作業です。
工場で作られた製品に対しては必ず検査作業が実施され、その方法は「目視」「顕微鏡」「機械選別」など多岐にわたります。
2.検査作業でチェックする内容
検査作業でチェックされる内容は製品によってさまざまですが、主な検査項目は以下の5つです。
2-1.形状不良
設計書と異なる形や歪みの有無などをチェックする項目です。
それぞれの製品は図面で寸法公差(許容範囲)が決まっており、その範囲を逸脱すると形状不良として不良品になります。そのほか、凹み、加工時に生じる出っ張りやトゲなどを意味する「バリ」などがあった場合も不良品扱いとなります。
目視検査の場合は製品に照明を当てて傷が見えにくい位置にある傷を確認し、正常な製品や部品にはない傷を検出することもあります。
2-2.動作不良
自動車の部品や家電など複雑な機械の場合、製造された製品が仕様通りに動作するかのチェックをおこないます。
2-3.色
製品の色味や色むら(色の濃淡や色合い)をチェックし、仕様書と異なる部分がないかを確認することも検査作業の仕事です。
金属製品を塗装した際の色味だけでなく、金属を酸化させ色合いを変化させた際の色味が見本通りになっているかをチェックする場合もあります。色味や色ムラのチェックは定量化や自動化が難しい分野とされており、基本的には検査員が目視によるチェックをおこないます。
2-4.異物
正常な製品にはない固形物などが付着していないかチェックをする作業です。異物はホコリや髪の毛、ゴミなどさまざまであり、付着箇所も異なります。
色味と同様に定量化が難しい検査項目であり、機械による自動判定が難しいことから目視によるチェックがおこなわれます。
2-5.印字ミス
製品に印字をする場合、その文字に誤字や脱字、スペルミスなどがないかをチェックします。
3.検査作業が必要な理由
工場で製造された製品は、必ず検査作業をクリアしてから出荷されます。この工程を経なければ不良品が混ざっていることを検出できず、重大なクレームにつながる可能性があります。
検査作業は不良品を市場に流通させないための最後の砦というべき仕事です。品質が業績に直結することもあり、製造業では絶対になくてはならない重要な工程となります。
以下の記事では、向上における検査や評価の仕事について、より詳しく解説しています。
4.検査作業の方法7つ
ひと口に「検査作業」といっても多くの方法があります。対象の製品によって検査の方法は異なりますが、工場でおこなわれる検査作業については大きく以下の7つの検査方法に分けられます。
4-1.目視検査
検査作業の基本的な方法で、文字通り担当者の目で不良品を判別します。ベルトコンベアで流れてくる完成した製品を目視で確認し、基準を満たさないものや不良品を見つける方法です。
目視は一人ですべてをおこなうわけではなく、大量に流れてくる製品に対して複数人で作業にあたることが一般的です。二交代や三交代の工場ではローテーションを組んで業務にあたります。
製品によっては顕微鏡で検査をおこない、検査後に検査内容をパソコンにデータを記録することもあります。
4-2.外観検査
目視と同じく、製品に傷や汚れ、変色などがないかを確認する作業です。大きく「インライン検査」「オフライン検査」に分かれます。
- インライン検査…生産ライン上に外観検査が組み込まれている
- オフライン検査…生産ラインから外れたところで外観検査を実施する
機械でチェックする工場も少なくありませんが、機械で判別できない外観の違いについては人の目でチェックをおこないます。
4-3.機能検査
生産した部品や完成品が設計通りに動くかを確認する作業です。自動車の走行テストなどがこれにあたり、各種機能検査をしてすべての項目が仕様通りに動くかチェックします。
4-4.分析補助
主に医療品や化粧品の研究開発が必要となる工場でおこなわれる検査です。成分の分析をおこなって得たデータをPCにまとめることで開発者をサポートします。
4-5.モニター検査
モニター画面を使って作業状況や機械の動作状況を確認し、不良品を見つけ出す検査です。モニターチェックで不具合を発見した時点で原因となる工程が明らかになるため、製造ラインの改善も速やかに進みます。
4-6.測定器検査
設計通りに製品ができているかを確認するために測定器を使って検査する方法です。「ノギス」や「マイクロメーター」など寸法を測定する道具を使用して検査をおこないます。
寸法公差内に収まっているかをチェックするほか、製品によっては振動や圧力、張力などの項目に沿ってチェックしていきます。
4-7.官能検査
主に化粧品工場や食品工場でおこなわれる検査で、人間の五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)を使って製品のエラーを検査する作業です。工業部品では「視覚」「触覚」を用いて外観や形状の検査をおこなうことが一般的です。
5.検査作業の仕事におすすめの資格
検査作業は、基本的には資格を持っていない人でも従事できます。ただ、資格を保有することで検査作業者としての力量を客観的に証明することになり、キャリアアップにも有効です。
ここでは、検査作業でおすすめの資格についてご紹介します。
5-1.品質管理検定
品質管理検定は「QC検定」とも呼ばれており、品質管理に関する知識をどの程度持っているかを証明できる資格です。
担当する仕事において品質管理・改善を実施するレベルはどれくらいか、その管理・改善をするためにどれくらいの知識が必要であるかによって、1級~4級のなかから取得すべき資格を選択します。
5-1-1.資格の取得方法
品質管理検定は、1級~4級のいずれも必要な受験資格はありません。試験内容は、1級がマークシートと論述、2~4級はマークシートです。
| 1級 | 13:30~15:40 マークシート(90分)・論述(30分) ※ 15:00~15:10のマークシート回収時間を含む |
| 1級(一次試験免除) | 15:10~15:40 論述(30分) |
| 2級 | 10:30~12:00 マークシート(90分) |
| 3級 | 13:30~15:00 マークシート(90分) |
| 4級 | 10:30~12:00 マークシート(90分) |
1級試験のうち、手法分野と実践分野からなる一次試験(マークシート試験)の結果が以下を満たしている場合は準1級に合格となります。
- 総合得点が概ね70%以上であること
- 手法分野と実践分野の得点がそれぞれ50%以上であること
準1級に合格した人は、合格した回の直後に実施される検定試験に限って申込の際の申告により、1級試験の一次試験を免除されます。
なお、受験料は以下のとおりです(個人申込の場合)。
| 1級 | 11,000円 |
| 1級(一次試験免除) | 88,000円 |
| 2級 | 6,380円 |
| 3級 | 5,170円 |
| 4級 | 3,960円 |
5-2.官能評価士
官能評価士は、人間の五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)を活用して食品や香料、工業製品などの品質を測定する「官能評価」に関する知識、技術を認定する試験です。
上級官能評価士、専門官能評価士という上位資格もあり、試験は年に一回実施されます。
5-2-1.資格の取得方法
官能評価士は、3つの資格ごとに受験資格や試験内容が異なります。
| 受験資格 | |
| 専門官能評価士 | ・上級官能評価士の資格保有者 ・5年以上の官能評価の実務経験 |
| 上級官能評価士 | ・官能評価士の資格保有者 ・日本官能評価学会の「中級講座」を修了している、もしくは日本官能評価学会での大会発表を第一著者として一回以上 |
| 官能評価士 | 制限なし |
受験料はいずれも1万円、また資格認定料として1万円~3万円が必要となります(※2023年3月現在)。
6.検査作業の仕事をするメリット
検査の作業者として働くメリットはさまざまですが、ここでは代表的なメリットを3つご紹介します。
6-1.未経験でも働きやすい
検査内容がマニュアル化されていることが多く、未経験の人でも働けるのが検査作業のメリットです。最初は難易度の低い作業から任されて一つの製品検査をひたすら繰り返すため、未経験でも比較的早く仕事を覚えることができるでしょう。
作業を覚えて精度を上げていくことができれば、仕事の幅を徐々に広げていくことが可能です。
6-2.女性が活躍できる
工場は金属の重い製品や機械を扱うイメージがあるかもしれませんが、検査作業は力仕事が比較的少ないため、女性でも活躍できます。体力を使わずに働くことで、帰宅後の時間や休日を有意義に使うことができるでしょう。
プライベートを充実させたい人や仕事と子育てを両立したいと考える人でも活躍できる仕事です。
以下の記事では、女性の工場勤務についてより詳しく解説しています。
6-3.作業環境が良い傾向にある
異物混入などを防ぐ目的から、検査をおこなう場所はきれいな環境が整えられていることが多く、作業環境は良好です。工場や扱う製品にもよりますが、座りながら作業ができる場合もあります。
また、顕微鏡などの精密機械は熱に弱いため、空調が効いた部屋で作業することも可能です。
7.検査作業に向いている人
検査作業に興味が持てたら、自分の性格が検査作業に向いているのかもチェックしてみましょう。検査作業に向いているのは下記に挙げるようなタイプの人です。
7-1.単純作業が苦にならない人
検査作業は、目視でも外観検査でも測定器検査でも、流れる商品をいかに手早く、正確に、かつ大量にチェックできるかが問われます。小さな製品を一日に何百・何千とチェックし続けるため、同じ作業を続けることに抵抗がない人に向いています。
以下の記事では、ライン作業について詳しく解説しています。
7-2.細かい作業が好きな人
検査作業で見つかるのは、明らかに不良と分かる製品ばかりではありません。目視では見つけにくい小さなキズや汚れ、色味の違いなど、小さな異常を見つける仕事であるため、細かい作業が好きな人に向いています。
集中していないと見逃してしまうような小さな異常を大量の製品の中から探し出すことになるため、集中力が長く持続することも必要です。
7-3.責任感がある人
検査は不良品を出荷・流通させないための大切な仕事です。適当な仕事をして不良品を発見できずに世の中に出てしまうと、クレームや回収騒ぎになって会社に大きな損失を与えることになります。
「不良品の流通は私が絶対に止める」という強い使命感や責任感を持って取り組める人に向いているでしょう。
8.まとめ
検査作業には、「目視検査」「モニター検査」「測定器検査」「官能検査」などの種類があります。製品や企業ごとに採用する検査方法は異なりますが、いずれの検査も「不良品を世の中に出さない」という使命は共通しており、企業の評判にも直結する重要な仕事です。
細かな仕事が好きで集中力に自信がある方は、JOBPALの求人一覧から検査作業の仕事をぜひチェックしてみてください。