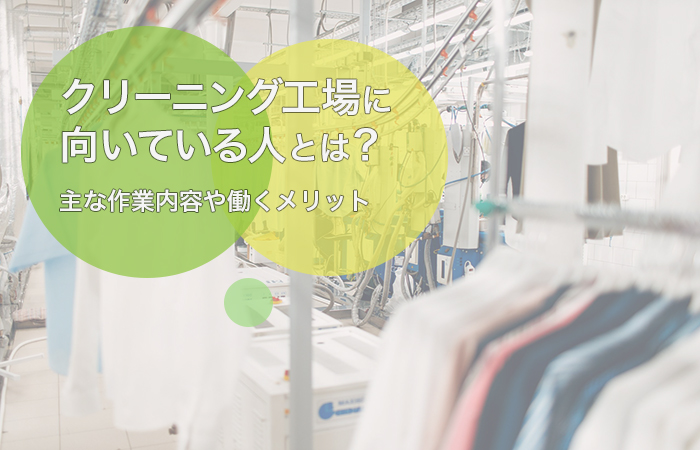エネルギー管理士の仕事とは?主な仕事内容や必要な資格、活躍できる職場、やりがいを解説
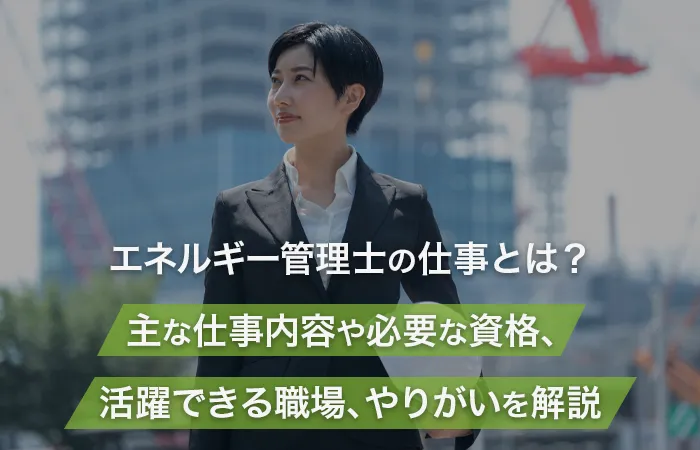
※この記事は6分30秒で読めます。
「エネルギー管理士ってどのような仕事?」
「エネルギー管理士として働くメリットが知りたい」
など、エネルギー管理士に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
エネルギー管理士は、省エネや経費削減により会社や環境問題に貢献でき、キャリア形成や収入アップにつなげることもできるなどの特徴があります。
今回は、エネルギー管理士の概要、やりがい、資格を取るメリットなどを解説します。この記事を読めばエネルギー管理士のことがよくわかり、資格取得の必要性や難易度などが理解できます。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.エネルギー管理士とは
エネルギー管理士の仕事は、主に第一種エネルギー管理指定工場の指定を受けている工場を監視し、改善の指揮を執ることです。第一種エネルギー管理指定工場とは、工場のなかでも特にエネルギー使用量が多い工場のことです。
エネルギー管理士は2006年、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」が改正された際に誕生した、電気や熱エネルギーの使用量などを管理する国家資格です。
それまで、熱管理士や電気管理士という資格はありましたが、法改正によって熱や電気をエネルギーとしてまとめることとなったため、エネルギー管理士という新しい資格が生まれました。
以下の記事では、設備保守について詳しく解説しています。
1-1.エネルギー管理士が必要になった背景
それまでなかったエネルギー管理士という国家資格が整備された背景には、日本のエネルギー資源の乏しさがあります。
経済産業省資源エネルギー庁の調査によると、2018年の日本のエネルギー自給率は11.8%でした。
石油などの輸入依存率はほぼ100%であり、エネルギーの供給が国際情勢などの影響を大きく受ける状態にあります。事実、過去2度にわたるオイルショックで、日本は特に大きな打撃を受けました。
オイルショック以来の日本では、限られた資源を効率的に無駄なく活用することが重要だと認識され、特に大規模施設においては、エネルギーの使用状況を監視する立場の人間が必要だと考えられました。
それに加えて近年は、地球環境に配慮した新しいエネルギーへの転換も進んでいます。そうした状況のなかで誕生したのがエネルギー管理士です。
-
参照:経済産業省 資源エネルギー庁|2020—日本が抱えているエネルギー問題(前編)
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energyissue2020_1.html
1-2.エネルギー管理者とエネルギー管理員の違い
エネルギー管理士は、エネルギー管理士試験に合格した方、またはエネルギー管理研修を修了して免状を受けた方が名乗ることのできる資格です。
この資格をもって実際に働く際には、エネルギー管理者、またはエネルギー管理員という職務に就くことになります。
規定以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場に指定されます。そのなかでも、製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じて1~4人のエネルギー管理者を選任する義務があります。この管理者は、エネルギー管理士の資格取得者から選任されます。
一方、エネルギー管理員は、第一種指定工場よりもエネルギーの使用量が少ない第二種エネルギー管理指定工場で選任される管理員です。エネルギー管理士の資格をもった方のほか、エネルギー管理員新規講習の修了者も選任の対象となります。
| 主な違い | |
|---|---|
| エネルギー管理者 |
|
| エネルギー管理員 |
|
2.エネルギー管理士の仕事内容
エネルギー管理士の主な職場は、第一種エネルギー管理指定工場と呼ばれる大規模な工場となります。具体的には、エネルギー使用量が原油換算で年間3,000キロリットル以上の工場が該当します。
前述のとおり、これらの工場では有資格のエネルギー管理者を1~4人は配置する義務があるため、エネルギー管理士の資格がある方は重宝されます。
エネルギー管理士の仕事内容は大きく分けて以下の5つです。
- エネルギーの管理
- エネルギー管理標準の作成業務
- 管理標準に従った設備の管理と計画の実行
- 報告書の作成
- 中長期計画の作成
エネルギー管理の計画から報告まで、工場全体に関わる幅広い業務を任されるのが特徴です。
それぞれの仕事についてさらに詳しくご説明します。
2-1.エネルギーの管理
エネルギー管理士の重要な仕事の1つが、毎日のエネルギー使用量の管理をすることです。
エネルギーを消費する設備の使用状況を把握し、工場全体のエネルギー管理をおこないます。設備の維持や、場合によっては使用方法の改善などを提案します。
2-2.エネルギー管理標準の作成業務
エネルギー使用設備について、合理的に運転ができるよう運転・管理、計測・記録、保守・点検、新設にあたっての措置などを定めた管理マニュアルであるエネルギー管理標準の作成をおこないます。
これは省エネ法第11条に基づき、事業者による作成が義務付けられている重要な書類です。
2-3.管理標準に従った設備の管理と計画の実行
マニュアルに沿った管理がされているかをチェックすることも、エネルギー管理士の仕事です。
例えば、空調システムや照明設備の使用について、稼働時間や条件に差違が生じていないか定期的に確認するなどの計画を策定し、業務に反映します。
2-4.報告書の作成
特定事業者などに該当する工場は毎年1回、国に対してエネルギーの使用状況についての定期報告書を提出する義務があります。
提出は翌年度7月末日が期限です。この報告書の作成もエネルギー管理士がおこないます。
2-5.中長期計画書の作成
工場は常に将来的な省エネを目標にしていく必要があります。その目標のために中長期(3~5年)的な計画を作成し、中長期計画書として国に提出しなくてはなりません。
省エネに対する取り組みが、優良な事業においてはこの提出を免除される場合もありますが、それ以外の工場ではこの計画書の作成業務もエネルギー管理士が担います。
3.エネルギー管理士が活躍できる職場
大量のエネルギーを消費する工場は、エネルギー管理士が活躍できる職場の一つです。特に、求人情報の資格や手当欄にエネルギー管理士の記載がある職場では、重宝される可能性が高いでしょう。
エネルギー管理者を必要とする第一種エネルギー管理指定工場は、令和4年度7月時点で全国におよそ7,503ヵ所あります。食品工場、化粧品工場、電子機器工場など、ジャンルは多岐にわたります。
工場への転職を検討している場合は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
エネルギー管理士は工場だけでなく、空調設備や電気設備、電気通信工事を担う業界でも需要が高くなっています。また、企業の省エネやCO2削減を支援するコンサルティング会社に就職するという選択肢もあります。
さらに、ほかの資格も取得したうえで、技術士事務所やコンサルタント事務所として独立開業する方もいるようです。
4.エネルギー管理士のやりがい
エネルギー管理士は、多大なエネルギーを消費する工場での節電・省エネを管理することで、災害や事故などのアクシデントに備え、会社や従業員の安全に貢献することができます。
会社の経費削減につながるため、経理や経営面のマネジメントに貢献することも可能です。
また、エネルギーを管理することで地球環境の保全に貢献できる点も、大きなやりがいの一つになります。環境に配慮した経済活動へのニーズはどんどん高まっていることから、エネルギー管理士への需要も増していくと考えられます。
人によっては、エネルギー管理全般を統括する立場としてリーダーシップを発揮できる点がやりがいにつながることもあります。働き方によっては、従業員だけでなく経営陣への提案やアドバイスをおこなう機会も出てくるかもしれません。
5.エネルギー管理士の資格を取るメリット
工場は慢性的に人手不足の状況です。そのため就職先は比較的見つけやすい傾向にありますが、エネルギー管理士の資格を持っていることで、より好待遇で採用される可能性があります。
工場だけでなく電気会社などにおいても重宝される資格なので、仕事の幅も広げられるかもしれません。
また、長期的にみても需要が高い仕事のため安定性があり、資格手当がつくことにより給与面でさらにプラスになる可能性もあるでしょう。将来的にはキャリアアップし、管理職などを目指せるなどのメリットがあります。
エネルギー管理士に限らず、資格は転職時や昇給にプラスの要素となります。希望の職種においてどのような資格が有利になるのか知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
6.エネルギー管理士の資格を取るには?
配置義務があることもあり、大きな工場では需要も高いエネルギー管理士。その資格はどのように取得すれば良いのでしょうか。
6-1.熱分野と電気分野の専門区分がある
エネルギー管理士の試験は、熱分野と電気分野の2つの専門区分があります。
そもそもエネルギー管理士は、熱管理士と電気管理士という2つの資格の区分を廃止し一つの資格になったため、どちらを選んでも合格すればエネルギー管理士の資格を取得できます。
6-2.実務経験がない方は試験を受ける
エネルギー管理士試験を受け実際に免状申請をおこなうには、実務経験1年以上が必要とされます。
ただし、先に試験を受けることも可能なため、実務経験を積みながら試験に合格し、実務経験が1年経ったところで免状申請をすることで、効率的に資格を取得することができます。
6-2-1.受験方法
試験の開催地は北海道、宮城県、東京都、愛知県、富山県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県の全国10ヵ所で、受験手数料は1万7千円(非課税)です。
年に一度の開催で、毎年5月上旬~6月中旬頃が申し込み期間となっています。申し込みは、郵送またはインターネットからおこないます。(※ただし、『旧制度の熱管理士又は電気管理士の免状取得者』(旧制度から現行制度への移行措置)での受験申込みは、インターネットでの申込みは不可。)
申し込みができた受験生は、7月下旬~8月上旬に試験を受けることができます(※年によって変動あり)。
試験は以下4科目のマークシート方式です。
6-2-2.受験科目
受験科目は、熱分野、電気分野とも4科目です。必須共通項目として「エネルギー総合管理および法規」の1科目があり、残りの3科目は以下の内容となります。
【熱分野】
- 熱と流体の流れの基礎
- 熱利用設備およびその管理
- 燃料と燃焼
【電気分野】
- 電気設備および機器
- 電力応用
- 電気の基礎
各科目で60%以上の正答が合格基準となります。
6-2-3.合格率
省エネルギーセンターの公表によると、2021年のエネルギー管理士試験の申込者数は9,574人、受験者数は7,766人、合格者数は2,636人でした。合格率は33.9%です。
合格率は毎年30%前後で推移しており、難易度はやや高めとなっています。合格を目指すには、しっかりとした対策が必要となるでしょう。
6-3.研修を受講して資格を取得する
すでに3年以上の実務経験がある方は、エネルギー管理士研修を受講することで資格を取得することもできます。
6-3-1.受講方法
9月下旬~10月中旬の研修仮申し込み期間に、申し込み研修資格審査を受けます。審査を通過すると、12月中旬からの研修に参加できます。
研修会場は仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国6ヵ所で、受講費用は7万円です。
6-3-2.研修内容
講義6日間と修了試験1日間、合計7日間の研修となります。
研修の内容は試験と同様、熱分野と電気分野のいずれかの専門分野を選択して受けることになります。試験と同じ4科目を、8時限~23時限の講義にて受講します。
6-3-3.修了試験
研修最後の1日は修了試験に充てられます。通常の資格試験と同じ4科目を受験しますが、マークシートではなく記述方式の回答です。
修了試験に合格することで、初めてエネルギー管理士の資格を取得することができます。
6-3-4.合格率
省エネルギーセンターの公表によると、2021年のエネルギー管理研修修了(合格)者は563人でした。申込者数は936人、受験者数は920人で、合格率はおよそ61.2%になります。
資格試験に比べて2倍近い合格率となっており、難易度は比較的低めでしょう。
費用や研修期間はかかりますが、短期間で重点的に学んで試験を受けるぶん、合格率も高くなる傾向にあります。
7.エネルギー管理士の資格取得のための勉強方法
エネルギー管理士の資格を取得するための勉強は、ある程度の知識を持っている方であれば100時間程度の勉強で合格できるといわれています。
しかし、基礎知識のない方がチャレンジする場合は1年~4年はかかるともいわれている難易度です。少しでも効率良く合格に向けて勉強できる方法を解説します。
7-1.通信講座で学ぶ
専用のテキストで学ぶ通信講座は、資格試験の勉強に不慣れな方やエネルギー管理の基礎知識がない方にピッタリの勉強方法です。
テキストのほか、解説動画や質問の受け付け、レポート添削など、講座ごとにさまざまな特色があります。
もともとエネルギー管理についてどれくらいの知識を持っているかによって、適切な講座は異なります。情報収集し、自分に合った講座を選びましょう。
7-2.過去問を解く
エネルギー管理士の試験問題は、過去問と類似したものが多く出題される傾向にあります。5年分の過去問を見れば大まかな試験の傾向がつかめるため、効率良く勉強をしたい方はまず過去問に解くのがおすすめです。
また、エネルギー管理士の試験では暗記問題の配分も多くなっています。過去問と合わせて、日々の隙間時間を活用した積み重ねの学習もおこないましょう。移動時間や休憩時間などを有効活用してみてください。
8.エネルギー管理士の将来性
SDGsにおけるエネルギー関連の開発目標などを踏まえ、日本政府も地球の未来のために省エネルギーを推進しています。その実現のためにも、大規模工場におけるエネルギー管理は必要不可欠です。
代替エネルギーの活用などで今後新しいエネルギー設備などが登場すれば、エネルギー管理士の需要は一層高まることが予想されます。
9.まとめ
国家資格であるエネルギー管理士は、工場やビルメンテナンスなどさまざまな業種で求められています。資格取得には時間や費用がかかりますが、エネルギーに関わる仕事に就きたい方は取っておいて損のない資格です。
エネルギー管理士の資格取得が、キャリアプランの形成につながる方も珍しくありません。少しでも興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
エネルギー管理士の資格が生かせる仕事をはじめ、JOBPALでは製造・工場系の求人を多数掲載しています。製造や工場で働きたい人はぜひ参考にしてください。