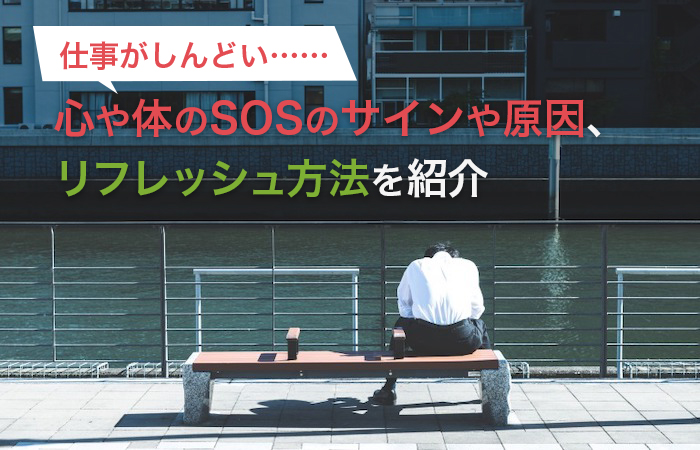仕事を辞めるタイミングはいつがベスト?賢く仕事を辞めるコツ

※この記事は5分で読めます。
「仕事っていつ辞めても良いの?」
「仕事を辞めるベストなタイミングはいつ?」
など、退職に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
仕事を辞めたいと考えるタイミングは人それぞれですが、実際に辞めるとなると、退職願の提出や引き継ぎ業務などが必要になる場合があります。退職時の注意点をふまえたうえで、スムーズに仕事を辞められるよう準備を進めていきましょう。
今回は、仕事を辞める際の基礎知識やベストなタイミング、退職までの流れなどを解説します。この記事を読めば、退職手続きがよくわかり、スムーズに仕事を辞められるようになります。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.仕事を辞める際の基礎知識
仕事を辞めるタイミングを解説する前に、まずは仕事を辞める際の基礎知識を見ていきましょう。
1-1.法律上では退職の2週間前に告知すれば辞められる
民法627条では、仕事を辞める際、退職の意思を伝えた日から2週間を経過すると労働契約が終了するとされています。
-
参照:e-GOV法令検索「民法第六百二十七条」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_8
ただし、会社の就業規則に退職願を届け出る、退職の1ヵ月前に退職の申し出をおこなうなどのルールが記載されている場合は、会社の規則に従うのが大前提です。
退職を希望する場合は、まずは就業規則に退職の条項がないか確認しておくと良いでしょう。
なお、退職の意思表示は、会社側と本人の合意があれば口頭でも認められます。しかし、会社によっては所定の書類による申告が求められる場合もあるため、事前にどのような手続きが必要か確認しておいてください。
1-2.引き継ぎが必要な場合は1ヵ月~3ヵ月前に退職意思を伝える
退職時に引き継ぎが必要な場合は、引き継ぎ期間を考慮して、退職日の1ヵ月〜3ヵ月前に退職意思を伝えましょう。
本来は、必ずしも退職者が引き継ぎをおこなう義務はありませんが、円満退職するなら、ほかの従業員の負担が少なくなるよう、引き継ぎをおこなうことが大切です。
職場への影響を可能な限り抑えるためにも、マナーを守って退職しましょう。
2.急に仕事を辞めることはできるのか?
即日退職が可能かどうかは、雇用期間の有無によって異なります。
雇用期間の定めがある場合、基本的に契約期間中の退職は認められません。ただし、1年以上の勤務実績があり、やむを得ない事由がある場合や、雇用主との合意があれば即日退職可能です。
また、雇用期間の定めがない場合であっても、即日退職は難しいケースが多いでしょう。退職したい場合は、退職の2週間前には退職の意思表示が必要になります。
ただし、有給休暇を活用して退職日まで2週間の休暇を取れれば、実質的に即日退職のような形をとることもできます。
以上のとおり、即日退職が可能かどうかは、パート・アルバイト、契約社員、正社員などの雇用形態によらず、雇用期間の有無によって変わってきます。
基本的には、どのような雇用期間・雇用形態であれ、連絡もなく突然仕事を辞めるのは避けるべきです。即日退職可能であっても、できる限り早めに退職意思を伝え、現場が混乱してしまわないよう注意しましょう。
なお、派遣社員の場合、退職が決まったら、退職に関する書類を用意して、保険証と併せて派遣会社へ提出が必要です。また、契約期間途中に退職した場合、同じ派遣会社から仕事を紹介されることが難しくなる可能性もあるため注意が必要です。
3.仕事を辞めるベストなタイミングはいつ?
仕事を辞めるベストタイミングには、「転職市場が活発な時期」「やりたい仕事が見つかったとき」「業務の閑散期」などが挙げられます。これらのタイミングが退職に向いている理由を、一つずつ見ていきましょう。
3-1.転職市場が活発な時期
スムーズに転職先を見つけたい方は、転職市場が活発に動く10月や3月から転職活動をして、仕事を見つけてから退職するのがおすすめです。
10月に合わせるのであれば12月末、3月に合わせる場合は3月末や4月末頃等のタイミングでの退職を目指してみましょう。
転職市場が活発な時期は、さまざまな業界の求人数が豊富にあるため、比較的転職先を見つけやすいです。
3-2.やりたい仕事が見つかったとき
仕事を通じて社会と関わるなかで、「本当にやりたいことに気が付いた」「将来を見越して、別の選択肢を模索したい」といった気持ちを抱くこともあるかもしれません。
現在の仕事に満足していない場合や、現在の仕事以上に魅力的な仕事が見つかった場合は、退職・転職を検討してみましょう。
3-3.円満退社をしたい場合は閑散期がおすすめ
円満退社したい場合は、業務が落ち着く閑散期に退職するのがおすすめです。繁忙期や参加しているプロジェクトの進行中に退職してしまうと、残されたほかの従業員に迷惑がかかってしまいます。
退職による現場への影響を可能な限り避けられるよう、閑散期を考慮して退職のタイミングを調整しましょう。
4.【正社員】仕事を辞めるまでの流れ
退職意思が決まったら、以下の4ステップの流れで退職の手続きを進めてください。まずは正社員が仕事を辞める流れを見ていきましょう。
4-1.【STEP1】退職意思を会社に伝える
退職意思が固まったら、退職希望日の2週間前までに退職意思を上司や人事に伝えましょう。
退職意思は口頭で伝えても問題ありませんが、あとで話が食い違わないよう、退職願という形で念のため文書で退職の意思を伝えておくのがおすすめです。
4-2.【STEP2】退職日を確定させる
引き継ぎなどがある場合は、会社側と話し合ったうえで退職日を調整してください。
退職までのスケジュールは、引き継ぎ期間をふまえてある程度余裕を持って組むことが大切です。
ただし、転職先の入社日が決まっているようであれば、転職先の都合を優先して、退職のスケジュールを組むようにしましょう。
4-3.【STEP3】業務の引き継ぎをおこなう
自分の退職後に職場が混乱しないよう、引き継ぎ業務をおこないます。業務のマニュアルを残しておくなど、退職後も後任者が困らない環境を整えておきましょう。
引き継ぎ漏れや引き継ぎのミスは、トラブルの原因になる可能性があります。
取引先への挨拶なども含めて、引き継ぎ作業は丁寧におこないましょう。
4-4.【STEP4】退職
退職日には会社から貸与された備品などを会社に返却し、退職後に必要となる書類を受け取ります。
退職時に受け取る源泉徴収票や雇用保険被保険者証、離職票などは退職後の諸手続きで必要になる場合があります。
書類を失くさないよう、大切に保管してください。事務手続きが済んだら、会社や部署単位での挨拶を済ませてから退職します。
5.【派遣社員】仕事を辞めるまでの流れ
続いて、派遣社員が仕事を辞めるまでの流れを解説します。
5-1.【STEP1】派遣会社の担当者に退職意思を伝える
派遣社員の場合、派遣先の会社の上司や人事に退職意思を伝える前に、派遣会社の担当者に連絡する必要があります。
退職理由や希望する退職日などを担当者に伝えておくと、その後のやりとりがスムーズになるでしょう。
5-2.【STEP2】退職が承認されたあと、上司に報告する
派遣会社から退職を承認されたら、派遣先の会社の直属の上司や人事に、退職することを報告します。
正式に退職日が決まるまでは、職場が混乱するのを避けるために、直属の上司や人事以外に退職することを伝えないようにしておきましょう。
5-3.【STEP3】引き継ぎや不要な書類を処分する
派遣社員の場合、契約満了の手続き等は派遣会社の営業担当がおこないます。
直属の上司などにも退職する旨を伝えたあとは、退職に向けて書類を整理し、不要な書類があれば処分します。
引き継ぎが必要な場合は、退職日までに引き継ぎを済ませておいてください。
5-4.【STEP4】退職
退職日には、やり残したことがないかを確認し、職場の方々に挨拶をおこなったうえで退職しましょう。
6.賢く仕事を辞める際のコツ
仕事を辞める際、以下の3つのコツを押さえておくと、よりスムーズに退職の手続きを進められます。
- 失業手当について事前に調べておく
- 転職先を決めてから退職する
- 賞与を考慮し退職する
それぞれのコツについてお伝えします。
6-1.失業手当について事前に調べておく
仕事を辞める際、次の転職先が決まっていない場合は失業手当を受給できます。
失業手当は、再就職を支援するための給付金であり、給付のためには特定の条件を満たさなければなりません。
失業手当(失業保険)については下記関連記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
6-2.転職先を決めてから退職する
退職後、すぐに次の仕事が見つかるとは限りません。
先のことを考えずに退職してしまうと、収入が途絶えて生活に困ったり、職歴に大きな空白期間ができたりする可能性があります。
収入がない状況を避けるためにも、次の仕事が決まってから退職するのがおすすめです。
6-3.賞与を考慮し退職する
賞与時期は会社によって異なりますが、一般的に7月と12月に支給されます。
7月に支給される夏の賞与を受け取ってから退職したい場合は8月末、冬の賞与なら1月末あたりの退職にすれば、賞与を受け取ってから退職可能です。
退職時期を調整できる場合は、賞与を受け取ったあとに退職できないか検討してみてください。
7.まとめ
仕事内容が自分に合っていない、家庭の都合で仕事を続けられない、ほかにもやりたい仕事ができたなど、退職を考えるタイミングは人それぞれです。
仕事を辞めようと思ったら、就業規則等を確認したうえで、スムーズに退職できるよう、準備を少しずつ進めていきましょう。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す