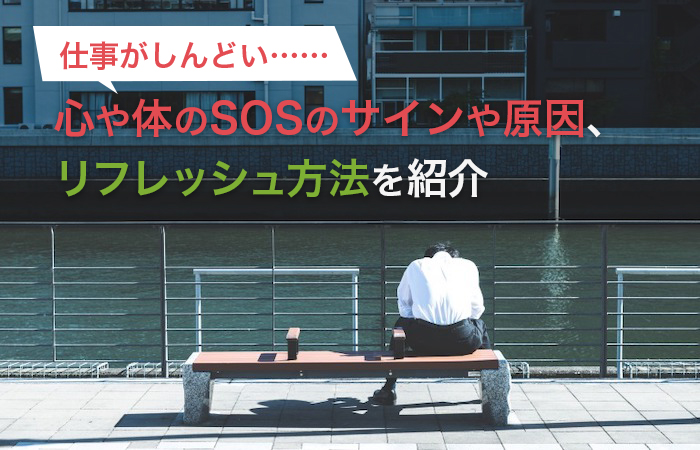新卒で会社を辞めたい方へ|よくある理由と辞めた方が良いケース
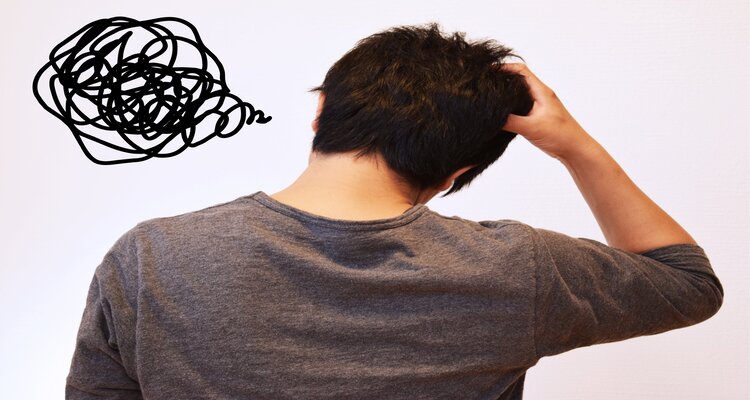
※この記事は6分30秒で読めます。
「新卒入社したばかりだけどもう辞めたい」
「新卒で1年経たずに辞めても良いの?」
など、新卒で仕事を辞めることに悩んでいる方もいるでしょう。
社会人一年目で期待して会社に入社したものの、理想と現実のギャップに悩む方はたくさんいます。
今回は、新卒で会社を辞める方の割合、よくある辞めたい理由、辞めるべきかどうかなどを解説します。この記事を読めば、新卒で辞めたほうが良いのか、今悩んでいることが解決できるでしょう。
エリアから工場・製造業のお仕事を探す
1.新卒3年目以内に会社を辞める方の割合
よく「新卒から3年は会社を辞めるな」などと言いますが、実際に3年目以内に会社を辞める方はどれくらいいるのでしょうか。
1-1.【学歴別】新卒者の離職率
厚生労働省は、就職後3年以内の新卒の離職状況をまとめた結果をプレスリリースで発表しています。これによると、平成31年3月の卒業者を学歴別に離職率を見た場合、以下のようになります。
| 学歴 | 3年以内離職率 |
|---|---|
| 中学卒 | 57.8% |
| 高校卒 | 35.9% |
| 短大卒 | 41.9% |
| 大学卒 | 31.5% |
-
参照:新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001005624.pdf
特に多いのは中学卒による就職後3年以内の離職で、50%を超えており、半分以上の方が辞めていることになります。
1-2.【事業規模別】新卒者の離職率
続いて、事業規模別に新卒者の離職率を見てみましょう。同じく厚生労働省のデータによると、事業規模別新卒者の離職率は以下の通りです。
| 事業所規模 | 高校 | 大学 |
|---|---|---|
| 5人未満 | 60.5% | 55.9% |
| 5〜29人 | 51.7% | 48.8% |
| 30〜99人 | 43.4% | 39.4% |
| 100〜499人 | 35.1% | 31.8% |
| 500〜999人 | 30.1% | 29.6% |
| 1,000人以上 | 24.9% | 25.3% |
-
参照:新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001005624.pdf
1-3.【産業別】新卒者の離職率
最後に、産業別に新卒者の離職率を見ていきます。厚生労働省の調査によると、新卒者の離職率が高い上位5つの産業と、実際の離職率の数値は以下の通りです。
【高校卒】
| 産業名 | 離職率 |
|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 60.6% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 57.2% |
| 教育・学習支援業 | 53.5% |
| 小売業 | 47.6% |
| 医療、福祉 | 45.2% |
【大学卒】
| 産業名 | 離職率 |
|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 49.7% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 47.4% |
| 教育・学習支援業 | 45.5% |
| 医療、福祉 | 38.6% |
| 小売業 | 36.1% |
-
参照:新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001005624.pdf
調査結果からは、高卒と大卒のいずれも宿泊業・飲食サービス業の離職率がもっとも高いことがわかります。
また、上位2位も生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業と同じ産業がランクインしています。
2.新卒で会社を辞めたいと思うよくある理由
それでは、なぜ新卒で会社を辞めたいと思うのでしょうか。よくある理由をお伝えします。
- 業務内容が合わない
- 職場の人間関係が悪い
- 労働条件が悪い
- 給与が低い
- ノルマや責任が重い
それぞれの理由についてお伝えします。
2-1.業務内容が合わない
業務内容が合わないと感じ、退職を考えるケースがあります。その瞬間としては以下のようなタイミングが挙げられます。
- 最初のアシスタント的な仕事が億劫に感じる
- 希望した部署に配属されなかった
- 自社の商品が好きになれない
現実と理想のギャップが原因で、新卒の頃に辞めたいと思うようになってしまいます。
2-2.職場の人間関係が悪い
仕事に問題がなくても、職場の人間関係が悪いと精神的な負担を感じやすく、辞めたいと思うようになります。人間関係が悪いと感じる瞬間は以下の通りです。
- 上司・同僚とうまくコミュニケーションが取れない
- リモートワークにより顔を合わせる機会が少ない
- 上司や周りの人によるパワハラ行為
2-3.労働条件が悪い
労働条件が悪いと身体的な負担が大きく、ときには体を壊してしまうこともあるでしょう。常に疲れている状態が続くため、「会社を辞めたい」と思考も後ろ向きになってしまいがちです。
労働条件が悪いと感じる瞬間は以下の通りです。
- 残業や休日出勤が多い
- サービス残業がある
- 一人当たりの仕事量が多すぎる
- シフトが不規則で身体的に辛い
2-4.給与が低い
給与が低く生活がままならない場合や、欲しいものを気兼ねなく買えない場合、好きなことができない場合は、もっと高い給与が欲しいと思い、「会社を辞めたい」という気持ちにつながります。
給与が低いと感じる瞬間は以下の通りです。
- ボーナスが少ない
- 2、3年後の昇給が見込めない
- 手取り額が少ない
2-5.ノルマや責任が重い
ノルマや責任が重いと、強いプレッシャーを抱えながら仕事をしなければなりませんし、ときには生活にも支障が出ます。そのため、プレッシャーからの解放や充実したプライベートを求めて、退職を考えるようになります。
ノルマや責任が重いと感じる瞬間は以下の通りです。
- 目標達成するまで帰れない
- ノルマを達成しないと怒られる
- 新卒でいきなり重要な顧客を担当させられる
3.離職率が高い業界の特徴・共通点
離職率が高い業界にはいくつかの特徴・共通点があり、BtoC業界であることが大半です。BtoC業界とはホテルや飲食店のように、「消費者」と呼ばれるような一般的なお客さまを対象としたサービスを提供する業界です。
それでは、なぜBtoC業界は離職率が高い傾向にあるのかお伝えします。
3-1.残業や土日勤務が多いため
BtoC業界は、常に新規顧客を獲得する必要があるため、特に営業職や販売職などは厳しいノルマを課される傾向にあります。結果、残業も発生しやすいです。
また、消費者の休みに合わせて土日勤務であるケースが多いことや、消費者によって業務時間が左右されがちなことから、充分な休息を取りづらいという苦労もあります。
3-2.労働時間に合った給与でない
労働時間が長めになりやすいにもかかわらず、給与が見合わないのも離職者が多い原因の1つといえるでしょう。
特に飲食業界は、立ちっぱなしの仕事で体力面が厳しいため、給与が低いと続けるのは難しいといえます。
3-3.教育体制が整ってない
離職率が高い職場は、在籍する少数の従業員に業務が集中するため、新人教育の余裕がなく、業務過多かつ教育不足になり、不満が出やすいです。
結果、新卒の離職者が出るという悪循環に陥ってしまいます。
4.新卒で会社を辞めたいと感じるのは悪いこと?
昔は「終身雇用」という言葉があったように、一度会社に勤めたら定年まで在籍し続けるのが一般的な考え方でした。
しかし、今はこの考え方が変わってきています。また、実際に新卒で辞めている人が多いというデータが出ていることから、同じように悩んでいる人は少なくないことがわかります。
決して間違っている判断をしているわけではありませんし、辞めたいと感じることも悪くありません。
きちんとした理由があって辞めたいと悩んでいるなら、今の悩みを解消するために、辞めるのも選択肢の一つです。
5.新卒でも会社を辞めたほうが良いケース
ここでは、新卒でも会社を辞めたほうが良いケースを見ていきましょう。退職すべきかどうかを考える際の参考にしてください。
- 労働環境・待遇が悪すぎる
- パワハラ・セクハラが横行している
- 違法性がある疑い・問題を会社が抱えている
- 転職してやりたいことが明確な場合
それぞれについてお伝えします。
5-1.労働環境・待遇が悪すぎる
良くない環境で働き続けると心身ともに疲弊してしまうため、限界に達する前に辞めることが大切です。
労働環境・待遇が悪すぎる会社の例は以下の通りです。
- 過剰な残業があり、長時間労働が常態化している
- 残業代が正しく支払われない
- 休日出勤が多い
- 給与が安い
- 給料が規定日に入ってこない
5-2.パワハラ・セクハラが横行している
パワハラやセクハラについて、「自分が我慢すれば良いだけ」と考え働き続けていると、心の病気になる可能性があります。早めに退職を検討するのが良いでしょう。
例えば、以下のような会社の場合、パワハラ・セクハラで辞める十分な理由になるといえます。
- 自分や周りが被害を受けている
- 企業のハラスメント対策の窓口が機能していない
5-3.違法性がある疑い・問題を会社が抱えている
会社が何らかの違法行為をおこなっているという疑いがある場合、在籍し続けることで違法行為を見て見ぬふりをした一人になってしまう可能性が考えられます。そうなる前に見切りをつけましょう。
違法性が感じられる会社の例は以下の通りです。
- 粉飾決算等会計のごまかし
- 公表していない素材を使用した食品偽装の疑い
- 適切に残業代が支払われていない
5-4.転職してやりたいことが明確な場合
資格を取る、留学するなどの目的がある場合や、やりたい仕事が見つかったなど、転職後の希望が明確な場合も、新卒で会社を辞めたほうが良いケースに該当します。
異なる業種・職種へのキャリアチェンジは、なるべく若いうちに転職活動をする方がチャンスが多いです。
特に資格、留学に関しては、方向転換が利くうちにチャレンジしたほうがいいので、早めに決断することをおすすめします。
6.新卒で会社を辞めないほうが良いケース
反対に、新卒で会社を辞めないほうが良いケースも見ていきましょう。
- 人間関係だけがつらいと感じる
- 仕事内容だけ合わないと感じる
- 明確な退職理由がない
高それぞれのケースについてお伝えします。
6-1.人間関係だけがつらいと感じる
人間関係は、時間の経過などで解決できる可能性があります。仕事に不満はないのに人間関係だけで早期退職を決断するのは、少々気が早いといえるでしょう。
例えば、会社によっては席替えや部署移動で人間関係の問題を解決できる場合があるため、人事に相談してみてください。
仮に人間関係が理由で新卒のうちに辞めてしまった場合、同様の職種に再度就職できない可能性が考えられるため、慎重に決めることが大切です。
6-2.仕事内容だけ合わないと感じる
新卒のうちはたくさんの新しいことを覚えなければならず、失敗も多いです。「自分にこの仕事は向いていないかも」と不安に感じることがあるかもしれません。
しかし、新卒の時期は仕事に慣れないのが至極当然で、徐々に慣れていく可能性があるため、仕事が合わないという理由で会社を辞めてしまうのはもったいないと言えます。
仕事の面白い部分を見つけたり、自分でもできるやり方を模索したり、まずは自分なりに仕事に慣れるための手段を考えてみてください。
転職活動をする際は、企業の面接官に合わない仕事への向き合い方を必ず聞かれます。自分なりの工夫をせずに退職し、転職活動を始めると、すぐ面接官にばれてしまうので注意しましょう。
6-3.明確な退職理由がない
もっとも気をつけるべきことは、明確な理由なく退職することです。理由もなく退職してしまうと収入が急になくなり生活が苦しくなりますし、辞め癖がついて転職がうまくいかなくなります。
会社を辞めたいと思うのには必ず理由があるはずです。その理由や問題点を解決できないまま辞めてしまうことは、問題解決能力が身につくチャンスを棒に振ることになります。
また、正当な理由がないと会社に辞める意向を伝えた際に良く思われないことがあり、居づらい空気を味わったり、円満退社ができなかったりという問題も起こるため避けましょう。
7.新卒で会社を辞めたいと思ったら考えるべきこと
もしも新卒で会社を辞めたいと思ったら、まず次のことを考えてみてください。
- 相談できる相手はいるか
- 次の転職先はすぐ決まりそうか
それぞれについて解説します。
7-1.相談できる相手はいるか
仕事を辞めることは一人で決断せず、信頼できる方にまず相談してみましょう。
特に新卒の場合、仕事を辞める経験も初めての方がほとんどなので、自分の判断が本当に正しいのか、親や先輩、上司などに相談してみるのがベストです。
相談すれば退職するときの手続きについても聞けるため、よりスムーズに辞めることができます。
7-2.次の転職先はすぐ決まりそうか
転職先を決めずに勢いで退職してしまうと、貯蓄がなくなり生活が苦しくなる可能性があります。
転職活動には3ヵ月程度かかることが一般的なので、もし辞めるにしてもある程度貯蓄をしておくべきです。
また、「すぐに決まるかわからない」「貯金がなくなりそう」と少しでも不安なら、今の仕事を続けながら新しい仕事を探し、内定をもらってから退職することを検討しましょう。
8.新卒で会社を辞めずに続けるメリット
新卒で会社を辞めたいと思っても、続けることで以下のようなメリットがあります。
- スキルを積み上げることができる
- 継続力が自分の自信につながる
各メリットについてお伝えします。
8-1.スキルを積み上げることができる
長く働けば、その業界の専門的なスキルが自然と身につきます。
身につけたスキルは自分の武器になり、年収アップに繋がったり、転職を有利に進められるため、同じ業界で働き続けたいと考えているなら辞めずにいることも選択肢の一つです。
8-2.継続力が自分の自信につながる
多少つらいと感じる仕事も、続けて乗り越える経験をすることで、「自分は頑張れている」という自信になります。
また、継続して働くことで年収が上がるケースが多く、これもまた自信につながる大きな要素です。
今、わからないことがあったり人間関係で悩んでいたりで気持ちが後ろ向きになっているのであれば、ただ諦めるのではなく、上司や先輩社員に相談して解決の糸口をつかむことも大切です。
9.新卒で会社を辞めるデメリット
反対に、新卒で会社を辞めてしまったときのデメリットも見てみましょう。
- 転職時に選考のハードルが高くなる
- 仕事が続かないと思われる可能性がある
- ボーナスが貰えない可能性がある
- 失業手当が貰えない可能性がある
それぞれについてお伝えします。
9-1.転職時に選考のハードルが高くなる
新卒で卒業すると、転職の際に第二新卒や中途採用という扱いになります。
スキルが何もない状態であると、第二新卒の枠で争いに勝てなかったり、スキルがない人の中途採用をおこなっていない企業が多かったりと、転職活動がかなりハードになるでしょう。
会社を辞めるにしても、即戦力になれるようなスキルを身につけてから転職を考えるのがおすすめです。
9-2.仕事が続かないと思われる可能性がある
基本的にどの会社も、長い期間働いてくれる人材を求めています。
短期で離職したという経歴がつくことで、採用担当者に「採用しても続かないだろう」と思われる可能性があり、転職が難しくなるかもしれません。
どうしても会社を辞めたいときは、前向きな理由を用意しておくことで採用される可能性が上がります。
9-3.ボーナスが貰えない可能性がある
社会人として働いている方のなかには、一定の時期にもらえるボーナスが楽しみという方が多いです。新卒として入社した方も、「ボーナスが入ったら」とやりたいことや買いたいものを考えていることと思います。
しかし、ボーナスは会社が定める在籍期間を満たしている方に支給されるものです。このため、新卒のうちに退職してしまうとボーナスがもらえないという可能性もあります。
特に、ボーナスを期待して後払いで大きな買い物をしてしまったなどの場合は要注意です。ボーナスがもらえる条件をあらかじめチェックしておきましょう。
9-4.失業手当が貰えない可能性がある
雇用保険に加入している方は、退職時に一定期間、失業保険をもらえます。しかし条件として「12ヶ月以上同じ会社に勤務すること」という定めがあるため、早期離職した方は、失業手当がもらえません。
失業手当が支給されないまま退職すると、生活する上で経済的に困窮する可能性があるため、最低でも1年は勤めることをおすすめします。
10.新卒で会社を辞めずに続ける際のポイント
新卒で会社を辞めずに続けるには、以下のポイントを押さえましょう。
- 仕事の取り組みを見直す
- 席移動・部署異動の相談をする
- 別の収入源の確保を検討する
それぞれのポイントについてお伝えします。
10-1.仕事の取り組みを見直す
業務がうまくいかずに悩んでいる場合は、業務の優先順位の整理、やり方の確認、効率の良い作業方法の確認、よくミスする箇所の確認・対処法など、仕事に関することを全体的に振り返ってみましょう。
改善点や工夫の余地が見つかる可能性があります。自分で解決できない場合は上司や先輩社員に相談して、アドバイスをもらうことが大切です。
10-2.席移動・部署異動の相談をする
人間関係で悩んでいる場合は、席の移動や、部署の移動で解決できる可能性があります。まずは人事に相談してみましょう。
また、「この人とは仕事上だけの関係」と自分のなかで割り切ることも大切です。無理に良好な関係を築こうとせず、適度な距離を置いて接しましょう。
10-3.別の収入源の確保を検討する
給料面で悩んでいたり、なるべく早く辞めたいけど金銭的に怖いと考えていたりする方は、副業などで別の収入源を確保することで、悩みが解決できたり、転職できるきっかけになることがあります。
ただし、会社によっては副業NGのところもあるので会社の規則は確認しましょう。
11.新卒で辞めるべきかどうかの判断が難しい場合
新卒だと社会人としての経験が浅いことから、辞めるべきかどうか悩みがちになります。
辞めるかどうかを本当に悩んだ場合は、一度求人サイトや転職エージェントでキャリアパートナーに相談してみるのがおすすめです。
経験豊富なキャリアパートナーに、これまでの経験を通して適切なアドバイスをもらうことで、自分にとってのベストな選択肢に辿りつきやすくなります。
相談だけでなく、自己分析や求人探しのサポート、面接対策や面接日程の調整など、転職活動の最初から最後まで心強い存在になってくれるので、辞めると決断しているときにも活用できます。
JOBPALではキャリアパートナーによるキャリアを受け付けています。新卒で辞めようか悩んでいる方、自分にぴったりの仕事を探したい方はお気軽にお問い合わせください。
12.まとめ
新卒で辞めることにはさまざまなデメリットがありますが、無理に合わない仕事を続けたり、合わない環境に居続けたりすることは心身の健康を損なう可能性があります。この記事を参考に、「本当に辞めるべきか」をじっくりと考えてみましょう。
迷ったときはJOBPALまでご相談ください。キャリアパートナーがあなたの仕事に関する悩み解決をサポートします。
関連記事
人気ランキング
以下の条件から求人を探す
都道府県からお仕事を探す
職種からお仕事を探す